ジャンル別記事
【2025年】介護福祉士は簡単すぎ?合格率や資格取得の難易度を解説
「介護福祉士国家試験は簡単すぎる」という声を聞いたことがあるかもしれません。
簡単か難しいかは人それぞれですが、これから受験を検討している方は難易度について非常に気になるでしょう。
難しいと言われる理由や対策のコツも解説しているので、試験の難易度を知りたい方はぜひ参考にしてください。
介護福祉士は簡単すぎる?

介護福祉士の国家試験は、合格率の高さや、必要な勉強時間が他の国家資格より短いことから「簡単すぎる」と言われますが、必ずしもすべての人に当てはまるわけではありません。
介護福祉士の難易度や取り組みやすさは、受験者の知識や準備状況、実務経験の有無によって大きく異なります。
「簡単すぎる」との意見がある一方で、介護福祉士は介護の専門職として認められるための重要な資格です。
そのため、合格には基礎知識の理解だけでなく、日々の実務経験の積み重ねや、的確な試験対策が必要です。
これらのことから、介護福祉士が「簡単すぎる」と感じるかどうかは、受験者の背景や準備状況によって大きく異なると言えるでしょう。
介護福祉士が簡単すぎと言われる3つの理由
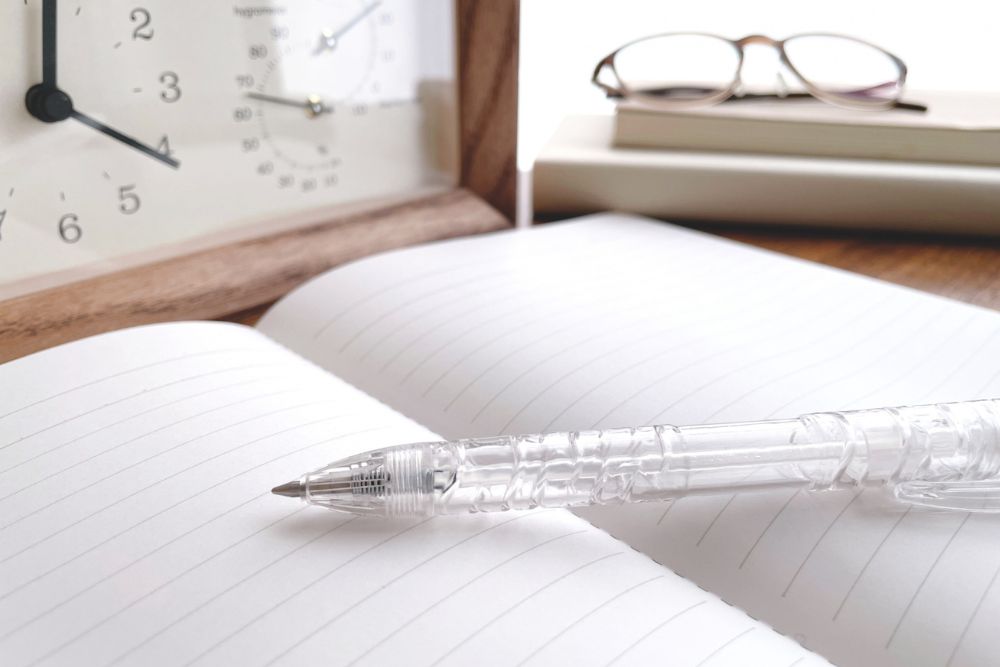
介護福祉士の国家試験が「簡単すぎる」と言われる理由には、以下の3点が挙げられます。
必要な勉強時間が短い
介護福祉士国家試験に合格するためには、勉強時間として約250時間が必要です。
介護福祉士の250時間という勉強時間は、他の国家資格と比較すると短いと感じられることが多いです。
例えば、看護師は約1,900時間、薬剤師は約2,000時間の学習が必要と言われています。
| 試験 | 目安の勉強時間 |
|---|---|
| 介護福祉士国家試験 | 250時間 |
| 社会福祉士国家試験 | 300時間 |
| 行政書士試験 | 1,000時間 |
| 看護師国家試験 | 1,900時間 |
| 薬剤師国家試験 | 2,000時間 |
| 司法書士試験 | 5,000時間 |
このように、介護福祉士は合格に必要な勉強時間が短いことが、介護福祉士が簡単すぎると言われる要因となっているでしょう。
また、介護福祉士の国家試験は、問題の多くが日常の介護現場での実務に基づいた内容となっています。
実際に、生活援助や身体介護に関する問題文も多いことが特徴です。
もちろん、しっかり勉強しなければ答えられないような、高齢者の疾病や介護保険の仕組みなどの専門的な問題文もあります。
しかし、実務経験を持つ人にとって、介護福祉士は特別な知識を新たに学ぶ必要が少なく、実践を通じて得たスキルが試験に役立つことが多いです。
このように、準備の負担が少ないと感じる人がいるため、介護福祉士は「簡単すぎる」と評価されることがあります。
介護福祉士の合格に必要な期間や、1日の勉強時間は以下で解説しているので、ぜひご覧ください。

ほかの国家試験よりも合格率が高い
2024年1月に行われた第36回介護福祉士国家試験では、合格率は82.8%でした。
毎年開催される介護福祉士国家試験ですが、近年の合格率は例年70%前後で推移しており、2024年に関しては過去最高です。
具体的な合格者数や合格点は以下のとおりです。
- 受験者数:74,595人
- 合格者数:61,747
- 合格率:82.8%
- 合格点:67点
この合格率の高さは、介護福祉士の難易度が比較的低いことを示しています。
実際に、他の国家資格と比べて、介護福祉士の合格率の高さは明確です。
| 試験 | 合格率 |
|---|---|
| 介護福祉士国家試験 | 82.8% |
| 精神保健福祉国家試験 | 70.4% |
| 社会福祉士国家試験 | 58.1% |
| ケアマネジャー試験 | 32.1% |
| 行政書士試験 | 13.9% |
参照:
厚生労働省「第36回社会福祉士国家試験合格発表」
厚生労働省「第26回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」
厚生労働省「第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」
一般財団法人 行政書士試験研究センター「年度 受験申込者数 受験者数 合格者数 合格率 令和5年度」
介護福祉士の合格率が、他の国家試験よりも高いことがわかります。そのため、勉強時間同様に、介護福祉士が簡単であると言われているのでしょう。
介護福祉士国家試験の過去10年の合格点・合格基準は、以下にまとめているので、併せてご覧ください。
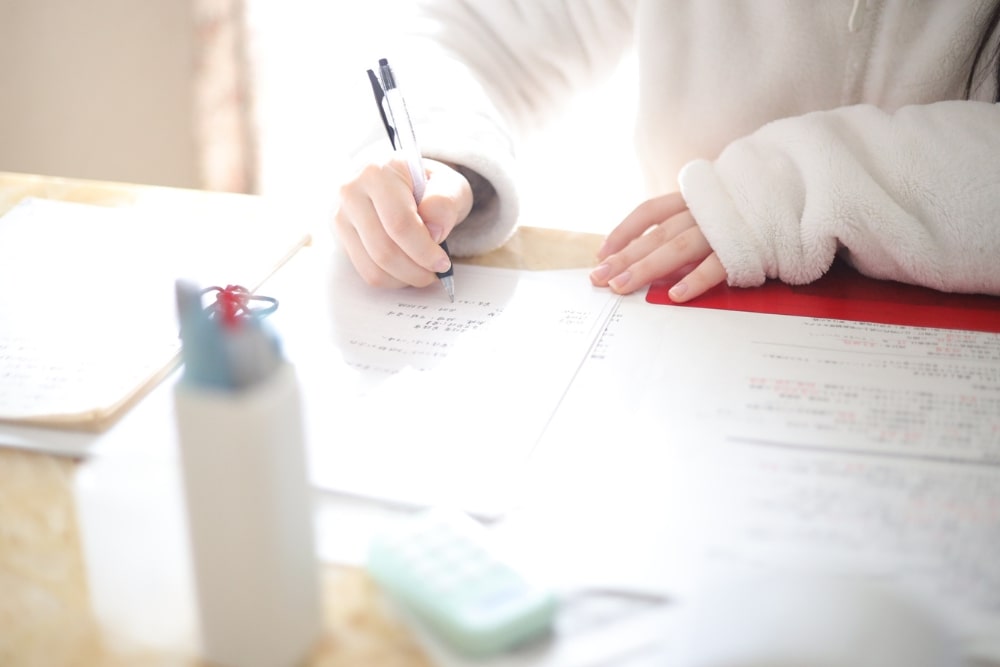
養成施設を卒業する必要がない
介護福祉士の国家資格を取得するために、養成施設を卒業することは必須ではありません。
実務経験ルートと呼ばれ、実務経験を積むだけで介護福祉士の受験資格を得られる仕組みになっています。
過去には、養成施設卒業者の受験は不要とされていましたが、現在は卒業者も介護福祉国家試験の受験が必要です。
これらの変更により、実務経験者が養成施設に通う必要がなくなり、介護福祉士資格取得のハードルが大幅に下がっています。
特に、介護現場で実務経験を積むことで受験資格を得られるため、働いてる間もスキルを磨きつつ資格取得を目指すことが可能です。
また、介護福祉士は、柔軟性が高く、受検回数や年齢に制限がありません。
自分のペースで資格取得を目指せるようになったため、介護福祉士を「簡単すぎる」と感じる人が増えたのでしょう。
介護福祉士の受験資格には4つのルートがあり、各内容について以下で詳しく解説しているので参考にしてください。


\ インストールから登録まで5分! /
介護福祉士が難しいと言われる3つの理由

介護福祉士が難しいと言われる理由は以下の3つです。
介護福祉士は簡単すぎると言われる一方で、難しいと感じる方もいるのが現状です。
そこで以下では、なぜ難しいと言われるのか、その理由について1つずつ紹介します。
受験資格を得るのに時間がかかる
介護福祉士の受験資格を得るには4つのルートがありますが、いずれも取得までに時間がかかります。
そのため、介護福祉士を受けるまでに、一定の時間がかかるのは避けられません。
このように、資格取得までの道のりが長いことが、介護福祉士が難しいと思われる理由の1つです。
養成施設ルート
介護福祉士養成施設に最短2年以上、あるいは福祉系・保育養成施設に通った経験があれば、さらに最短1年以上通学することで介護福祉士の受験資格が取得可能です。
しかし、2017年までは指定の養成施設に通学するだけで介護福祉士が取得できましたが、法改正により現在は卒業後に受験資格を得るルートに変更されています。
2017年4月1日から2027年3月31日までに卒業、または卒業見込みの方には経過措置が設けられています。
経過措置では、試験に不合格でも卒業翌年度から5年間は期限付きで資格を取得できます。その後も、一定の条件を満たせば資格を継続することが可能です。
実務経験ルート
3年以上の実務経験と「介護職員実務者研修」の修了により介護福祉士を取得するのが一般的なルートです。
また、「介護職員基礎研修」を取得し、さらに喀痰吸引等の研修を受けて介護職の実務経験を3年以上積む方法もあります。
どちらのルートも介護職未経験や無資格でも始められるのでおすすめです。
福祉系高校ルート
文部科学省や厚生労働省が指定する福祉系高校に通学することで、介護福祉士養成課程を満たす道のりもあります。
所定のカリキュラムを受ければ、卒業後に国家試験を受験することが可能です。
福祉系高校ルートから介護福祉士を受験する方は実技試験が免除されるため、筆記試験に合格すれば介護福祉士が取得できます。
小学生・中学生の頃から介護の仕事に憧れを持っている方は、福祉系の高校で専門的なスキルや知識を身につけてみてください。
EPAルート
母国での学習や日本語研修など、一定の学力を求められる試験に合格した後、日本に留学することとなります。
その後、日本で実務経験を3年間積んで介護福祉士の受験資格が認められます。
もし試験に不合格となった場合でも、最長5年間の在留延長が可能です。
専門知識が必要な問題が出題される
介護福祉士では、単に基本的な介護スキルを問うだけではなく、専門的な知識や応用力が求められる問題が出題されます。
例えば、介護技術や福祉制度に関する詳しい知識を問う問題、法律や倫理についての知識を前提としたケーススタディ形式の問題など、幅広い内容が含まれています。
特に、実務経験が少ない受験者にとっては、法律や制度に関する問題が難しいと感じることがあるでしょう。
また、介護福祉士では理論的な裏付けを求められる問題も多く、日常業務だけではカバーしきれない部分を独学や試験対策で補う必要があります。
試験準備に時間と労力を要するため、介護福祉士は「難しい」とされる要因となっています。
誰でも受かる試験ではない
介護福祉士国家試験の合格率は70%~80%程度と高めですが、それでも試験内容をしっかり理解し、対策を練らなければ合格は難しい試験です。
実際に、毎年20%~30%の割合で介護福祉士に落ちているのが現状です。
介護福祉士は正答率60%以上が合格基準となっており、基礎的な知識だけでなく、問題を正確に解く力が求められます。
また、試験には全く準備をしていないと歯が立たないような問題も含まれているため、計画的に学習を進めることが必要です。
過去問や模擬試験を活用し、出題傾向を理解したうえで対策を進めないと、不合格となる可能性が高まります。
このように、事前準備を怠れば簡単に合格できない点が、介護福祉士を「難しい」と感じる理由です。
介護福祉士国家試験の概要
ここでは、介護福祉士国家試験の取得方法や試験の概要について解説します。
介護福祉士の資格の取り方
介護福祉士は介護分野で唯一の国家資格であり、受験資格を満たし、国家試験に合格することで得られる資格です。
ひと昔前までは、実務経験のみで受験資格を得ることができ、介護福祉士養成校に通い卒業試験を受ければ国家試験を受けずに資格が貰えていました。
しかし、介護福祉士の資質向上を図る観点から、一定の教育課程を経た後に介護福祉士を受験するという形で、現在までに度々資格取得方法の改定がなされています。
現在の介護福祉士の資格取得方法は、さまざまなものがありますが、どのルートであっても国家試験を必ず受けることが必要です。
介護資格の取り方については、以下で詳しく紹介しているので、介護職としてキャリアを積みたいと考える方は確認しておいてください。

国家試験受験の条件
介護福祉士資格を得るためには国家試験合格が必須であり、受験資格を得るためにはいくつかのルートが存在します。
以下が、介護福祉士の受験資格を得るそれぞれのルートです。
- 養成施設ルート:介護福祉士養成施設に2年以上通う方法(福祉系大学や保育養成施設に通っていれば1年以上の場合あり)
- 実務経験ルート:実務者研修 or 介護職員基礎研修+喀痰吸引等研修を受け介護職員としての実務経験を3年以上積む方法
- 福祉系高等学校ルート:指定の福祉系高校に通う方法
- EPAルート:EPA介護福祉士候補者が実務経験3年を積む方法
いずれにしても国家試験を受ける必要はありますが、多くの人が受けやすい環境は整っています。
また、EPAルート(経済連携協定ルート)は、海外の人を介護福祉士として迎え入れるためにできた制度です。
介護福祉士にはさまざまなルートが存在しますが、実際に一番使われる方法は実務経験ルートです。
介護福祉士受験者の半数以上が実務経験ルート利用者であることから、社会人になってから国家試験を受ける人が大半であることがわかります。
出題形式と試験科目
介護福祉士国家試験の出題形式は、マークシートですべて択一式です。
5つの選択肢から正解を1つ選ぶ形式となっています。
以下13科目の全125問で構成され、1問1点です。
- 人間の尊厳と自立
- 人間関係とコミュニケーション
- 社会の理解
- 介護の基本
- コミュニケーション技術
- 生活支援技術
- 介護過程
- こころとからだのしくみ
- 発達と老化の理解
- 認知症の理解
- 障害の理解
- 医療的ケア
- 総合問題
介護福祉士では幅広い知識が求められ、合格には上記13科目群すべてで得点し、60%以上の正答率を出す必要があります。
ただし、試験の難易度によって毎年合格点は補正されています。そのため、基準以上の正答率を出すよう努めましょう。
受験者数と合格率
介護福祉士国家試験の受験者数と合格率の推移は以下のとおりです。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第36回 | 74,595人 | 61,747人 | 82.8% |
| 第35回 | 79,151人 | 66,711人 | 84.3% |
| 第34回 | 83,082人 | 60,099人 | 72.3% |
| 第33回 | 84,483人 | 59,975人 | 71.0% |
| 第32回 | 84,032人 | 58,745人 | 69.9% |
参照:厚生労働省
介護福祉士の受験者数は毎年約80,000人程度ですが、ここ数年は平均を下回っています。
しかし、合格率に関しては、直近2年間で平均を大きく上回っていることがわかります。
介護福祉士の受検者数減少によって今後は人手不足が考えられる介護職ですが、その分、合格者数は少しずつ増えていくことが考えられるでしょう。
受験資格と科目の変更点
介護福祉士国家試験には、2025年と2026年で以下の変更が加えられます。
- 2025年から実技試験廃止
- 2026年からパート合格制度が導入
従来の介護福祉士国家試験では、筆記試験と実技試験の両方が課される方もいましたが、2025年の第37回試験から実技試験が完全に廃止されます。
これにより、試験内容が学科試験に一本化され、準備の負担が軽減されることが期待されています。
ただし、介護現場で必要なスキルを担保するために、実務者研修での実技指導がより重要になる可能性があるでしょう。
また、2026年の介護福祉士試験からは「パート合格制度」が導入される見込みです。
この制度では、13科目を3つに分けて受験する方法が採用され、片方のみ合格した場合でもその合格が次回以降の試験に持ち越される仕組みです。
これにより、一度にすべての科目を合格する負担が減り、合格率の向上が見込まれます。
特に、介護現場で忙しい受験者にとって、この制度は大きなメリットとなるでしょう。
介護福祉士国家試験とは何かについて、以下で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。

介護福祉士国家試験に落ちる人の特徴
介護福祉士国家試験に落ちる人の特徴は以下のとおりです。
落ちる人の特徴を把握すれば、介護福祉士の国家試験に合格に向けて適切な対策を行えるでしょう。
試験対策の時間を確保していない
介護福祉士が簡単すぎるという言葉を耳にし、学習時間を作らないまま試験日を迎えてしまう方が少なくありません。介護福祉士の勉強を始める際、最も重要なのは時間の確保です。
介護福祉士国家試験は出題範囲が広いため、短期間で一気に学習することは難しい試験です。
そのため、時間が取れない状況をそのままにしてしまうと、必要な知識を網羅することができず、試験で力を発揮できない可能性があります。
1回目の介護福祉士試験で合格するためにも、試験日から逆算してスケジュールを立て、1日1時間でも学習時間を確保するよう努めましょう。
通勤時間や休憩時間などの隙間時間を活用するのも効果的です。短時間だとしても、継続できるような方法・計画を立てることで、介護福祉士の合格に近づけるでしょう。
介護福祉士におすすめの勉強方法を以下で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
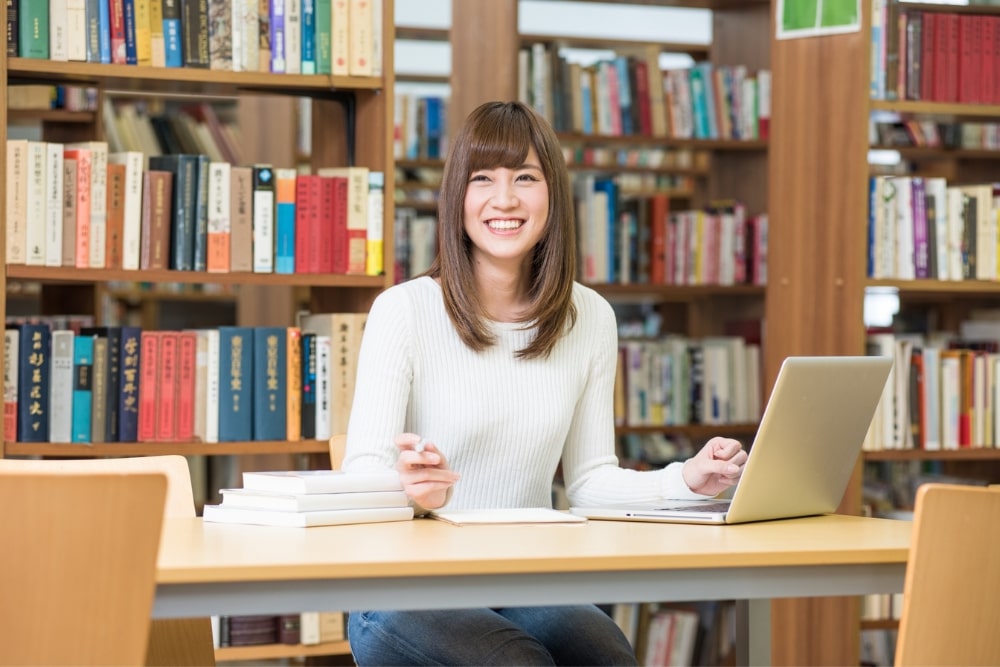
過去問での試験対策をしていない
過去問の活用は、介護福祉士で合格の鍵を握るポイントです。
過去問を解いてないまま試験に挑むと、介護福祉士の問題形式や出題傾向に慣れておらず、時間配分や解答方法に戸惑うことがあります。
また、過去問から介護福祉士の重要ポイントを把握しないままだと、効率の悪い学習になりがちです。
そのため、過去問を繰り返し解き、介護福祉士の試験内容を把握しましょう。特に間違えた箇所を分析し、同じミスを繰り返さないようにすることが重要です。
社会福祉振興・試験センターでは無料で介護福祉士国家試験 過去の試験問題を公開しているので、試験対策に活用してください。
また、介護福祉士の対策では、過去問での学習方法に頼り過ぎず、最新の教材や資料を利用することもおすすめします。
介護福祉士を過去問だけで合格する方法や、利用する際の注意点についても紹介しているので、併せてご確認ください。

苦手科目をそのままにしている
介護福祉士の苦手科目を避けてしまうのは、多くの受験生に共通する問題点です。
苦手科目を克服しないままにすると、試験全体での得点が不足し、不合格の原因になります。
特に介護福祉士試験では幅広い科目から問題が出題され、全科目で得点を取らなければなりません。
1科目でも落としてしまうと、他の科目で得点を取れても不合格になります。
そのため、難しかったと感じる苦手科目をリストアップし、優先的に取り組む計画を立てましょう。
わからない部分はテキストを読み返したり、解説動画や講座を活用したりして補足学習を行う方法が効果的です。
出題形式や傾向を理解していない
介護福祉士の出題形式や傾向を理解していないと、試験本番で適切な時間配分ができず、問題に対応しきれない可能性があります。
介護福祉士国家試験では、選択の問題や事例問題など、思考力を問われる問題が多いのが特徴です。これに対応するには、事前の対策が欠かせません。
試験の形式やよく出題されるテーマについて事前に調査し、予想問題や模擬試験を解き、介護福祉士の内容に慣れることが大切です。
試験の時間配分を意識しながら問題を解く練習を積むことで、正確性と解答スピードを向上させましょう。
介護福祉士に受かる気がしないという方は、落ちる人の特徴とどのような人が受かるのかを知ることが大切なので、以下をぜひ参考にしてください。

介護福祉士国家試験に合格するコツ
介護福祉士国家試験に合格するためには、効率的な学習法と計画性が重要です。
ただ漠然と勉強を進めるのではなく、計画を立てて取り組むことで、合格に近づきます。
以下では、試験合格のためのコツを3つ紹介します。
計画的に試験対策を進める
試験合格の第一歩は、学習計画を立てることです。
試験日から逆算して準備期間を設定し、各科目ごとに学習スケジュールを割り振りましょう。
例えば、以下のような具体的な目標設定が大切です。
- 毎週1科目ずつ絞って重点的に勉強する
- 6ヶ月間、毎日学習時間を2時間確保する
- 仕事が休みの日はいつもより勉強時間を確保する
また、過去問や模擬試験を解くタイミングも計画に組み込むと、試験形式や時間配分に慣れることができます。
さらに、計画は柔軟性を持たせることも重要です。
予想以上に時間がかかった科目や、苦手科目に重点的に取り組む必要が出てきた場合に備え、スケジュールに余裕を持たせておきましょう。
計画通りに進まない場合も焦らず、適宜見直しを行いながら進めることで、効率的に学習を進められます。
介護福祉士の過去問対策アプリやサイトなども使用し、学習効率を高めましょう。

問題集で繰り返し学習する
問題集を活用した学習方法は、介護福祉士国家試験対策の中心となります。
特に、過去問は出題傾向を理解するために欠かせません。
初めて解く際には時間を計り、試験本番を想定した環境で取り組むと良いでしょう。
その後、間違えた問題をピックアップし、解説をじっくりと読み込むことが大切です。
問題を解く際には、「なぜその答えが正解なのか」を深く理解することを意識しましょう。単に暗記するだけでなく、出題の意図や背景にある知識を把握することで、応用力が身につきます。
また、解き直しを繰り返すことで、知識の定着が進むと同時に、苦手科目の克服にもつながります。
加えて、本番でのケアレスミスを避けるために、解答後は再度チェックするクセをつけましょう。
介護福祉士国家試験の合格にはノートを取ることも有効なので、以下でノートの取り方と勉強法について理解を深めましょう。
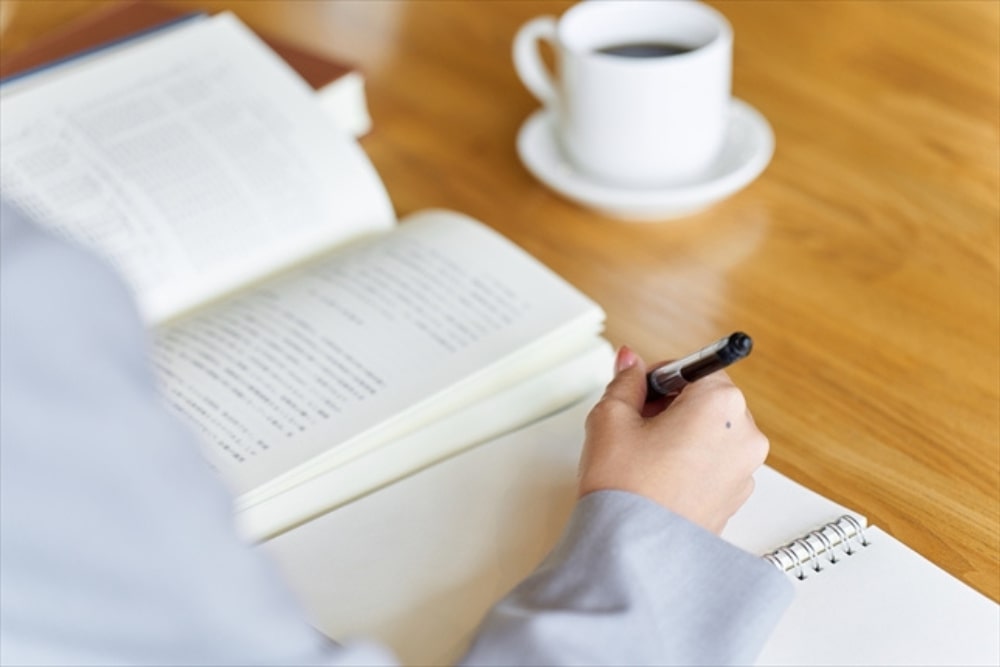
試験対策の講座を受ける
独学に自信が持てない場合や、効率的に学習を進めたい方には試験対策講座の受講がおすすめです。
講座では、試験のポイントを押さえた指導が行われるため、出題範囲を効率よく網羅できます。
また、プロの講師が提供する解説やアドバイスにより、独学では見落としがちな細かなポイントにも気づけるでしょう。
オンライン講座を選べば、仕事や家庭の都合に合わせて柔軟に学習を進めることも可能です。
さらに、模擬試験や予想問題が含まれている講座では、本番さながらの練習ができるため、試験の雰囲気をつかむのに役立ちます。
時間や費用の制約がある場合でも、短期集中型の講座や部分的な対策に特化した講座を活用することで、効果的に学習を進められるでしょう。
介護福祉士に受かるコツは以下でより詳しく解説しているので、合格したいと考える方はぜひご覧ください。

介護福祉士の資格取得のメリット
介護福祉士の資格を取得する3つのメリットを紹介します。
介護福祉士が簡単すぎると言われる中で、資格がなくても働けるため、介護福祉士の必要性を感じない方もいるようです。
しかし、実は資格取得が介護職員にとって大きなメリットとなります。1つずつ紹介するので、参考にしてください。
給料アップにつながる
介護福祉士の資格は、直接的に収入の増加に結びつくことが特徴です。
介護福祉士資格を持つ人を職員として迎え入れるのは施設にとっても大きなメリットがあります。
そのため、介護福祉士資格所有者と無資格者の給料や待遇設定に差をつけている介護施設は多いです。
多くの事業所では約1〜2万円の介護福祉士手当が支給されます。また、介護福祉士は対象の処遇改善手当も存在するため、所有しているだけで給料面を優遇してもらえる可能性は高まります。
介護職員1人あたり月額9,000円、最高で約8万円の手当が支給されるので、給料が大きく上がるでしょう。
厚生労働省の情報によると、資格保有者と無資格者の給料には約6万円の違いがあります。
このように、昇給や昇進での給料アップが難しい場合でも、介護福祉士資格を取得するだけでそれまでの給料よりも上がる可能性がおおいにあります。
就職や転職に役立つ
介護業界では資格保持者の需要が高く、資格を持つことで求人の選択肢が大幅に増えます。特に、有資格者を優遇する求人が多いため、就職や転職活動で採用に有利に進むでしょう。
介護に関する一定のスキルや知識も証明できるため、書類選考で落とされることは少なくなります。
また、人手不足の事業所が多いため、転職活動の際に年収や待遇が良い職場を積極的に選べます。
求職活動において強力なアピールポイントとなるため、即戦力として自己アピールし、自身の希望に合う事業所へ転職しましょう。
キャリアアップできる
介護福祉士資格を取得していることで、介護主任などに昇進しやすいのは事実です。
介護主任でなくても、フロアリーダーやユニットリーダー、サービス責任者など、チームの中心としての役割を任される可能性が高まります。
介護福祉士を持っていることで、専門知識がある職員としてみなされ、責任ある立場を担当できるでしょう。
また、介護福祉士の資格を持つことは、以下の受験要件となっています。
- ケアマネジャー(介護支援専門員)
- 認定介護福祉士
- 介護福祉士基本研修
- 介護福祉士ファーストステップ研修
加えて、施設や学校の教員、研修の講師など、介護現場以外の職種も目指せます。
このように、介護福祉士の資格を持っていれば、キャリアアップに大きく近づくことができます。

勉強することで専門知識が高まる
資格取得のための勉強を通じて、介護に必要な知識とスキルが深まることもメリットの1つです。
介護福祉士の資格取得を目指したい方は、国家試験対策の勉強が必須です。その中で、国家試験対策のための受講や個人学習を経て、更に深い介護知識を得ることができます。
例えば、利用者の身体状態や心理状態を理解し、それに応じた適切なケアを提供する能力が向上します。
また、高齢者や障がい者に対する支援だけでなく、介護予防やリハビリテーションなどの応用知識も身につけられるでしょう。
介護施設側や国が1人でも多くの人に介護福祉士を取得してほしい真の目的は、介護職員の知識と技術向上のためです。
介護福祉士資格を得るために一生懸命勉強したことが、利用者に寄り添うケアにつながり、職場で信頼される存在となるでしょう。
介護福祉士の資格取得のメリットについて触れましたが、以下ではより詳しく介護福祉士のメリット・デメリットを紹介しているのでチェックしてみてください。

介護福祉士国家試験に関するよくある質問
最後に、介護福祉士の国家試験に関する質問に回答していきます。
介護福祉士が簡単すぎると言われる中でも、合格できるか不安に感じる方は、以下の内容を覚えておきましょう。
介護福祉士は何問正解で合格する?
介護福祉士は125問中75問以上の正解が合格基準です。
総得点の60%以上の正答率が必要とされているため、最低でも75問の正解を目指す必要があります。
ただし、1科目で1点以上は取る必要があり、1科目でも落とすと不合格となるので注意してください。
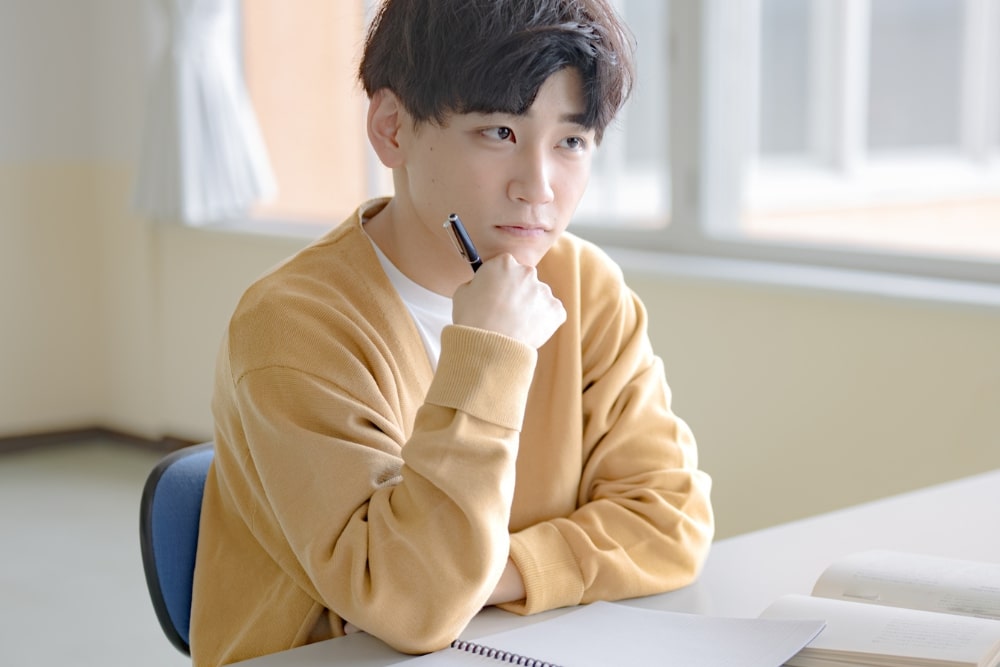
介護福祉士に10回落ちたけど合格できる?
介護福祉士に10回落ちた方でも、原因を探り改善することで合格できます。
何が足りなくて試験に落ちているのか、どの科目が苦手なのかなど、十分に理解したうえで対策すれば合格に近づけます。
出題傾向や会場の雰囲気はある程度理解できていると思うので、これまでの経験を活かして次は合格を目指しましょう。
10回落ちたけど次こそ介護福祉士の国家試験に合格したいという方は、以下で受かるための勉強法を紹介しているので確認してください。

介護福祉士は未経験でも合格できる?
介護福祉士は未経験からでも合格できますが、受験資格を満たすには実務経験や養成施設での学びが必要です。
そのため、未経験の状態では受験資格を得られません。
しかし、養成施設ルートに入学し、学校を卒業すれば、未経験の方でも最短で受験資格を得られます。
つまり、未経験者でも努力次第で資格取得は十分可能です。
簡単かどうかは人それぞれ!難しいと感じるなら十分な対策を
介護福祉士国家試験が「簡単」と感じるか「難しい」と感じるかは、人それぞれの状況や準備の仕方によります。
実務経験を通じて多くのスキルを身につけた人や、計画的に試験対策を進めた人にとっては、比較的取り組みやすい試験と感じるかもしれません。
しかし、一方で知識や経験が不足している場合や、試験に向けた準備が不十分であれば、難しいと感じることもあります。
難しいと思っても、どのような試験も十分な準備をすれば克服できます。
簡単か難しいかを決めるのは他人ではなく自分自身です。介護福祉士国家試験を目指すならば、適切な対策を講じ、自信を持って試験に挑みましょう。
資格を活かして介護現場で働きたいと考える方は、転職エージェントへの相談や介護単発アプリの使用がおすすめです。
中でも、カイテクは有資格者に特化した求人情報を載せており、面接なしで勤務開始できます。
登録自体は5分程度で済むため、あなたの希望に合った求人がすぐに見つけられるでしょう。
サービス利用は無料なので、ぜひこの機会に試してみてください。
カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。
- 「約5分」で給与GET!
- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!
- 働きながらポイントがザクザク溜まる!
27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /







