ジャンル別記事
介護職の夜勤専従は月何回まで?上限回数や高収入を目指せる働き方を紹介!
介護職で夜勤専従として働いていると、「月に何回まで夜勤に入っていいの?」「法律的に問題はない?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
勤務回数が多いと収入が増える一方で、体力面や労働基準法との兼ね合いが気になるところです。
結論、夜勤専従の勤務回数には法的な上限はないものの、変形労働時間制や施設ごとの取り決めに基づいて、月10回前後が一般的な上限とされています。
夜勤専従として無理なく働きたい方は、本記事の内容をぜひ参考にしてください。
また、介護・看護単発バイトアプリの「カイテク」を使えば、1日単位で夜勤専従を経験できます。面接・履歴書などの手続きもなく、勤務後最短5分で入金されるので、自分らしい働き方を目指せるでしょう。
介護職の夜勤専従は月何回まで働ける?
介護職の夜勤専従に法的な「月何回まで」という上限はありませんが、一般的には月8〜10回前後が現場での目安とされています。
これは1回あたりの勤務が16時間前後と長時間におよぶため、過重労働を防ぐために設けられている実務的な上限です。
また、月144時間以内や週72時間を上限とする施設内ルールも多く見られます。勤務回数は施設の運営方針や人員体制によって異なり、施設ごとに細かいシフト調整がなされているのが実情です。
健康を維持しながら長期的に働くには、回数だけでなく労働時間・休息のバランスも重要なポイントです。
夜勤専従に関わる法律と制度

介護職の夜勤専従における働き方は、労働基準法や各種労使協定、施設内ルールなど複数の制度によって定められています。ここでは3つの視点から、夜勤に関連する制度を詳しく見ていきましょう。
労働基準法と変形労働時間制
労働基準法では、原則として1日8時間・週40時間の労働時間が定められていますが、夜勤専従のように1回の勤務が長時間になる働き方では「変形労働時間制」が適用されることが多いです。
例えば、1回16時間勤務であっても、月間の総労働時間が規定内であれば違法ではありません。シフトの柔軟性を確保しつつ、労働者の過重負担を防ぐために導入されている制度です。
72時間ルールと144時間制
夜勤専従でよく聞かれる「72時間ルール」や「144時間制」は、あくまで施設ごとの目安やガイドラインであり、法的な拘束力はありません。
また、1カ月の夜勤総時間を144時間程度に抑える運用もあります。これは1回16時間勤務で月9回が目安となります。いずれも職員の体調管理や安全確保を目的とした、現場での自主的な基準です。
現在144時間制については廃止されていますが、夜勤回数を病院側が一方的に増やすことは推奨されていません。
夜勤協定や施設による取り決め
多くの介護施設では、法定ルールに加えて独自の「夜勤協定」や勤務規定を設けています。これには職員の夜勤回数の上限、休憩時間の取り扱い、連続勤務の制限などが含まれます。
たとえば、労使間で「月の夜勤は最大8回まで」と協定を結ぶ施設もあるでしょう。
夜勤は心身の負担が大きいため、個々の労働者の事情(年齢、健康状態、家庭環境)に配慮して柔軟に調整されることが望ましいとされています。
こうした取り決めは、長期的な人材確保や離職防止の観点からも重要な役割を果たします。

\ インストールから登録まで5分! /
介護職の夜勤専従の働き方
介護職の夜勤専従は、その名の通り夜勤のみを担当する働き方です。基本的に日勤や早番・遅番には入らず、16時〜翌10時など夜間を中心としたシフトで働きます。1回あたりの勤務時間が長いため、月の勤務回数は8〜10回程度が一般的です。
日勤のシフトに入ることはない
夜勤専従として雇用される場合、基本的には日勤や他の時間帯のシフトに入ることはありません。夜勤に特化した勤務形態のため、生活リズムを一定に保ちやすく、日中の時間を自由に使える点がメリットです。
ただし、施設や人員の都合によっては、臨時で日勤を頼まれるケースもあるため、契約内容や職場の体制を確認しておくことが重要です。
日勤を希望しない場合は、夜勤専従として明確に役割が分かれている職場を選ぶようにしましょう。
勤務時間は8~16時間程度になる
介護夜勤の勤務時間は大きく8〜16時間の範囲に分かれます。3交替制の夜勤では8時間勤務が一般的で、勤務時間は22時から翌日の7時頃までです。
【3交替制】
早番:7時〜16時
遅番:13時〜22時
夜勤:22時〜翌朝7時
2交替制の夜勤では夕方の16時頃から翌日の9時頃までの間となります。
【2交替制の場合】
早番:9時〜18時
夜勤:16時〜翌朝9時
夕食介助は早番者が行い、就寝後の排泄介助や体位交換、朝の朝食介助を行います。労働時間が長いため、多く稼げる反面、体力的には負担が大きいです。
少しずつ夜勤の働き方に慣れていきたいと感じる方は、介護・看護単発バイトアプリのカイテクを試してみてください。自分のスキマ時間を活かして1日単位で働けるため、実務経験から夜勤に慣れることができます。
実際にカイテクを利用して夜勤の求人に応募した方にインタビューをしました。
Q:勤務の時間なども教えていただけますか
A:ほとんどが昼間ですが、ショートステイとグループホームではたまに夜勤があります。夜間の利用者の様子を見ると昼間とは違うことが多く、日勤の仕事で新たな対応の方法として応用することができます。
そういう意味ではたまに入る夜勤も、とても大切かなと思っています。
5~6時間から長いと8時間勤務もありますが、自分のスケジュールによって決めています。それもカイテクの良い点です。自分の空いた時間に合わせて仕事ができるので、とても助かりますね。
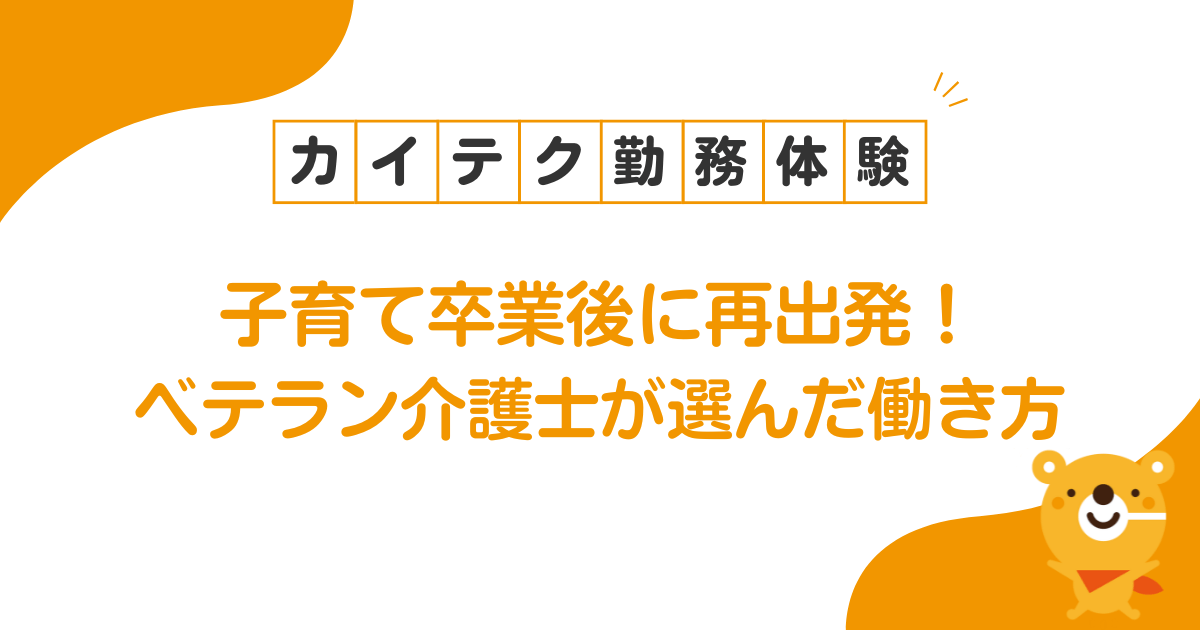
1夜勤20,000円~35,000円得られる
夜勤専従になると、1度の夜勤で20,000〜35,000円近くの収入を得ることができます。
また、労働基準法では22時から翌日5時まで労働する場合、時給が1.25倍される規定があります。時給1,500円の施設なら、1,875円が基本時給となります。
【8時間の夜勤の場合】
1,875円(時給)× 8時間(労働時間)= 15,000円
15,000円 + 6,335円(平均手当額)= 21,335円
時給が高ければ収入は一層増加します。夜勤専従になれば、1度の夜勤で20,000〜35,000円の収入を得ることは容易です。
介護職として働く私自身、介護職の給与に夜勤手当は大きく影響すると感じます。夜勤手当は施設によって金額が異なるからです。待遇のよい職場や二交代制の16時間夜勤をしている施設に勤めることで、そうではない現場と比べると1〜2万円程度の差が出ると思います。
夜勤専従の年収については以下で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

【勤務別】夜勤専従の給与や福利厚生

夜勤専従で働く場合、雇用形態によって給与や福利厚生に大きな違いがあります。
正社員として働くか、パート・派遣などの非正規で働くかによって、安定性や収入の傾向が変わるため、自分のライフスタイルに合った形態を選ぶことが重要です。
ここでは、正社員と非正規社員に分けて、夜勤専従の待遇を比較します。
正社員の給与と待遇
夜勤専従の正社員は、月給制で安定した収入を得られるのが大きな特徴です。給与は地域や施設によって異なりますが、月25万円〜35万円前後が相場で、夜勤手当や深夜割増賃金が上乗せされます。
賞与(ボーナス)や昇給制度があるほか、社会保険、厚生年金、有給休暇などの福利厚生も整っている場合が多いです。また、一定の勤続年数やキャリアアップに応じて役職手当や資格手当がつくこともあります。
長期的に働きたい人や、家族の扶養を支える立場の方には正社員がおすすめです。
非正規社員の給与と待遇
一方、パートやアルバイト、派遣社員などの非正規社員の給与は正社員と大きく変わりません。月に8〜10回の16時間勤務であれば、月収20万円を超えることができます。
しかし、非正規社員の場合、突然解雇されたりボーナスが支給されなかったりすることがあります。
正社員と比較すると、雇用状態や福利厚生が安定しないため、不安を感じる方もいるでしょう。
非正規社員に不安を感じる方は、単発バイトアプリを利用し、自分のタイミングに合わせて働き始めるのがよいでしょうか。1日単位で数時間から働ける求人が豊富に掲載されており、ライフスタイルに合わせて働けます。
以下は、カイテク利用者にインタビューをした、カイテクのメリットです。
Q:Iさんにとってカイテクで働くことの一番大きなメリットはどんな点ですか
A:やはり複数の施設で多くの利用者さんと触れ合うことが、私自身の勉強になっているということです。
ひとつの施設で長く働くことも経験になりますが、カイテクを通していくつもの施設に行くと、それまで見えなかったことが見えてきたり、自分に欠けているものを知るきっかけになっていると思います。
Q:Iさんの経験からご自身のスキルアップにつながっていることがとても分かります。
A:確かに長く務めた施設での自分の行動を今振り返ってみると、仕事に追われてスキルアップのことを考えることができていませんでした。時間に縛られて、気がついたら10年も経っていた感じです。
今はカイテクで働きながら日々が勉強になり、この先の自分の方向性についても展望が見えてきたような気がしています。
またいろいろな施設に行くと、欠点も見えてしまうことがあります。その場合は、自分が通う施設で改善するという方向で生かしています。
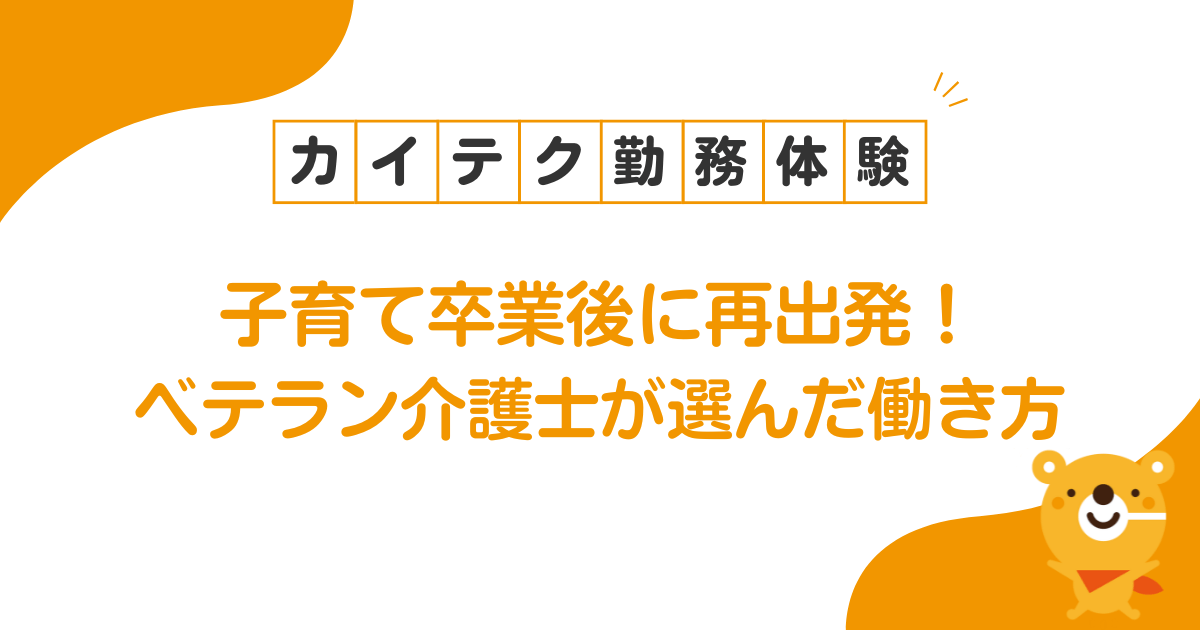
介護の夜勤専従として働くメリット・デメリットを比較
夜勤専従は高収入が期待できる反面、身体的・精神的な負担もある働き方です。勤務形態やライフスタイルとの相性を見極めるためには、メリットとデメリットを正しく理解しておくことが大切です。
このパートでは、夜勤専従で働く利点と課題をそれぞれ具体的に解説し、どのような人が向いているかについても整理します。
夜勤専従の5つのメリット
夜勤専従として働くメリットは以下5つです。
- 収入が高い:夜勤手当や深夜割増により、日勤よりも高収入が得られる
- 出勤回数が少ない:1回の勤務時間が長いため、月の出勤は8〜10回ほど
- 日中の時間を自由に使える:趣味や副業、家族との時間が取りやすい
- 業務に集中しやすい:夜間は利用者の活動が少なく、落ち着いて仕事ができる
- 生活リズムが一定:夜勤だけのシフトで体内リズムが安定しやすい
このように、効率的に稼ぎながら自由度の高いライフスタイルを実現できるのが夜勤専従の魅力です。
デメリットは少なからずあるものの、高給与を目指す方や、日勤には入りたくないと感じる方は、夜勤専従を検討してみてもよいでしょう。
夜勤専従の3つのデメリット
夜勤専従にはメリットがある反面、以下3つのデメリットがあります。
- 体調管理が難しい:昼夜逆転による睡眠不足や体調不良のリスクがある
- 人間関係が限定される:夜間はスタッフが少なく、孤独感を感じる場合もある
- 未経験者にはハードルが高い:急変時の対応など、即戦力が求められるケースが多い
これらの点は事前に理解しておくことで、働くうえでのミスマッチや後悔を防ぐことができます。
夜勤や長時間勤務で疲労が溜まったら、休息することが大切です。睡眠時間を確保したり昼寝をしたりして、身体を休めることを優先します。趣味や出かけることがリフレッシュになることもありますが、疲れが溜まっているときは、休むのが一番です。
向いている人・向いていない人の特徴
夜勤専従の働き方が向いている・向いていないそれぞれの介護職員の特徴は以下のとおりです。
向いている人:
- 一人で黙々と仕事をするのが得意な方
- 収入を重視し、出勤回数を減らしたい方
- 夜型の生活リズムに慣れている方
向いていない人:
- 規則正しい日中の生活を好む方
- 睡眠障害や体調管理に不安がある方
- 職場での人間関係を重視する方
夜勤専従は、体力や生活スタイル、性格の向き不向きが結果に直結します。自分の特性に合わせて働き方を選択しましょう。以下では、夜勤で働く際の注意点を紹介しているので、働き方を選ぶときの参考にしてください。

介護職が夜勤専従として働く方法

夜勤専従として働くためには、一定の準備と就職先の選び方が重要です。夜勤は責任の重い業務も多いため、即戦力として期待される場面が多く、無資格・未経験よりもある程度のスキルや経験がある方が採用されやすくなります。
効率よく理想の働き方を実現したい方はぜひ参考にしてください。
介護資格を取得しておく
夜勤専従で働くには、最低でも「介護職員初任者研修」以上の資格を取得しておくのが望ましいです。
無資格でも応募可能な求人も存在しますが、夜間は限られた人員で利用者をケアするため、一定のスキルや知識を持っている人が優遇される傾向にあります。
介護福祉士などの上位資格があると、給与面や採用率にも良い影響を与えることが多いため、長期的に介護業界で働く意志があるなら資格取得を検討しておくと安心です。
以下では、介護資格の取り方を種類別で紹介しているので、これから資格取得を目指す方はぜひ確認してみてください。

介護職特化の転職サイトに登録する
正社員や契約社員として安定して夜勤専従を希望する場合は、介護職に特化した転職サイトの利用がおすすめです。
サイトによっては「夜勤専従」「高収入」「シフト自由」などの条件で検索できる機能があり、自分の希望に合った求人を効率よく見つけることができます。
また、キャリアアドバイザーが希望条件に合った職場を紹介してくれる場合もあり、非公開求人に出会える可能性も高まります。履歴書作成や面接対策のサポートを受けられるのもメリットです。

介護単発バイトアプリを使用する
「まずは夜勤を体験してみたい」「副業で数回だけ働きたい」という方には、介護単発バイトアプリの活用が便利です。代表的なアプリには「カイテク」があり、勤務地・時間・報酬条件を選んで手軽に応募できるのが特徴です。
特に、週1回や月数回などスキマ時間で働きたい人には最適で、実際の勤務を通じて自分に夜勤専従が向いているかどうかも確認できます。登録から就業までがスムーズで、すぐに収入を得たい人にもおすすめです。

カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。
- 「約5分」で給与GET!
- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!
- 働きながらポイントがザクザク溜まる!
27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /
夜勤専従の働き方で高収入を目指すポイント
夜勤専従は基本給に加えて深夜割増や夜勤手当が支給されるため、日勤よりも高収入を狙いやすい働き方です。しかし、同じ夜勤専従でも、施設や働き方によって得られる収入には大きな差があります。効率よく収入アップを図りたい方は、以下の2点をぜひ実践してみてください。
給与が高い施設で働く
夜勤専従で高収入を得るためには、施設選びが最重要ポイントです。一般的に、特別養護老人ホームよりも、介護老人保健施設(老健)や有料老人ホーム、障害者支援施設などの方が夜勤手当や基本給が高い傾向にあります。
また、都市部の施設や人手不足が深刻なエリアでは、1回あたり35,000円を超える求人も存在します。求人情報を見る際は、時給換算額や夜勤手当の内訳まで確認し、自分のスキルに見合った報酬が得られるかを比較検討しましょう。
日中に単発バイトを入れる
夜勤専従は1回の勤務で長時間働くため、日中や休日に自由な時間が生まれやすいのが特徴です。この空いた時間を活かして、介護系の単発バイトや登録制のスポット勤務に入ることで、月収を大幅に上げることが可能です。
たとえば、日中に3〜4時間の訪問介護や通所施設での補助業務に入るだけでも、1回5,000〜10,000円程度の収入が見込めます。
アプリや転職サイトを活用すれば、自分のペースで働きながら収入アップを実現できるでしょう。また、以下では、夜勤専従の方が掛け持ち可能なのかどうかを紹介しているので、気になる方はぜひご覧ください。

夜勤専従の働き方に関するよくある質問
夜勤専従の働き方は高収入を得られる一方で、体力面や生活リズムへの不安を感じる方も少なくありません。
ここでは、実際に多く検索されている「夜勤専従に関するよくある質問」に対して、端的かつ実用的に回答しています。働き方の検討に役立ててください。
介護の深夜割増賃金はいくら?
労働基準法では、22時から翌日5時までの労働に対して時給が1.25倍されます。
深夜割増賃金は介護業界にも適用されるため、たとえば夜勤専従の時給が1,500円なら、1,875円に増額されます。高時給の施設での勤務により、収入を増やすことができるでしょう。
夜勤専従はきつい?
夜勤専従は高収入を得やすい一方で、生活リズムの乱れや体力的な負担が大きいのが難点です。
特に初めて夜勤に入る方は、睡眠時間の確保や栄養バランスを意識する必要があります。また、勤務時間が16時間前後と長いため、休憩時間が取りづらい施設では疲労が蓄積しやすくなります。
ただし、月の勤務回数が少ないため、日勤よりもプライベートの時間を取りやすいのがメリットです。体調管理ができる人には向いている働き方だといえるでしょう

夜勤専従の1日の仕事内容や流れは?
夜勤専従の基本的な勤務時間は16時頃から翌10時頃までで、16時間勤務に2時間の休憩が含まれることが一般的です。仕事内容は以下のような流れです。
- 日勤スタッフからの申し送りを受ける
- 夕食や服薬の介助
- 就寝介助と巡回(排泄や体位変換)
- 仮眠・交代休憩
- 早朝の起床介助・トイレ誘導
- 朝食介助と記録業務
- 日勤への申し送り
夜間はスタッフが少ないため、一人ひとりに対する責任が重くなりやすい点に注意が必要です。

夜勤専従の看護師は月に何回まで働ける?
法的に明確な上限回数は定められていませんが、変形労働時間制(1ヶ月単位)に基づき、月間総労働時間が原則160〜177時間程度に収まるよう調整されます。1回の夜勤が16時間前後とすると、月に10〜11回程度が限度です。
ただし、施設の「夜勤協定」や自治体の指導により上限が設けられているケースもあ。健康や安全面からも、無理のない勤務数で働くことが望ましいでしょう。
まとめ
夜勤専従は、月10回前後の勤務で高収入が見込める働き方として、多くの介護・看護職の方に選ばれています。
ただし、変形労働時間制や深夜労働の規制、施設ごとの「夜勤協定」など、法的な制限や健康面の配慮が求められる点には注意が必要です。
勤務時間は長く、体力的にはハードですが、そのぶん出勤回数が少なく生活にメリハリがつくメリットもあります。高時給を得るには、給与条件の良い施設を選ぶことや、スキマ時間を有効活用する工夫もポイントです。
自分に合った働き方を見極め、無理のない範囲で夜勤専従を活用しましょう。
カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。
- 「約5分」で給与GET!
- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!
- 働きながらポイントがザクザク溜まる!
27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /







