ジャンル別記事
【2025年最新】介護職員の処遇改善手当はなくなる?加算制度のおさらい
令和6年(2024年)に介護保険の報酬が改定されたため、処遇改善加算の行方が気になる方もいるでしょう。
結論から述べると、処遇改善手当はなくなることなく今後も継続されていきます。しかし、今年は制度の変更や要件の見直しなどがあり重要な年となりました。
カイテクでは介護職の方がスキマ時間を活かして働ける単発バイトアプリを提供しています。最低1日1時間~働けるため、処遇改善手当だけに頼らずとも、収入アップが図れるでしょう。
介護職員の処遇改善加算はなくなる?

結論から言えば、処遇改善加算はなくなるのではなく、制度が再編・一本化されたというのが正確な情報です。
2024年6月の介護報酬改定により、これまで分かれていた「介護職員処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が統合され、新たな加算として整理されました。この再編により、処遇改善が形を変えて継続されることになります。
つまり、「なくなる」という言葉は誤解を生みやすい表現であり、制度そのものはむしろ強化・整理されたと言えます。詳しくは以下で解説するので、ぜひご覧ください。
2024年6月の報酬改定で「一本化」された
2024年(令和6年)6月の介護報酬改定では、処遇改善に関する加算が「一本化」され、新たな加算「介護職員等処遇改善加算」として再構築されました。これまでの加算は以下のように整理されました。
【旧加算】
- 処遇改善加算
- 特定処遇改善加算
- ベースアップ等支援加算
【新加算】
「介護職員等処遇改善加算」に一本化
この一本化により、事業者側の事務負担軽減や、現場職員への処遇改善の配分ルールの明確化が期待されています。実際の加算要件や配分方法については、引き続き自治体や事業所からの説明が行われる見込みです。
制度がなくなるわけではなく、より透明でわかりやすくするための整理である点がポイントです。
処遇改善加算が「一本化」された背景
複数の加算制度が併存していた従来の仕組みでは、制度が複雑すぎて現場での理解・運用が難しいという課題がありました。
たとえば、「どの加算が給与に反映されているのかが不明確」「手当がもらえているか判断できない」といった声も多くありました。
令和5年の処遇改善加算の取得状況は、処遇改善加算が93.8%、介護職員等特定処遇改善加算が77.0%でした。
【令和5年の処遇改善加算の取得状況】
処遇改善加算:93.8%
介護職員等特定処遇改善加算:77.0%
介護職員等ベースアップ等支援加算:92.1%
多くの事業所で加算が取得されている一方、事務作業や制度の複雑さ、給与の公平性を考慮するのが難しいため、加算申請をしない事業所も存在しています。
こうした混乱を受けて、厚生労働省は「一本化することで制度の透明性と公平性を確保し、現場への浸透を促す」という方針を打ち出しました。特にパート職員や非正規雇用の方にとっては、加算が反映されにくい構造も問題視されていたため、一体的な支援措置への移行が求められていたのです。
また、一本化によって賃金改善の実効性を高めることが狙いであり、処遇改善そのものが軽視されたわけではない点も重要です。
職場環境要件を見直す予定
介護業界は深刻な人手不足が続いており、厚生労働省によれば2025年までには介護人材が32万人不足すると発表されています。職員の満足度、指導、育成を強化するため、加算要件の1つである職場環境要件の項目を増やす方向性で意見が一致しています。
厚生労働省が提案している対応案は以下のとおりです。
- 年次有給休暇取得促進の具体的な取組み
- 介護福祉士ファーストステップ研修の実施
- ユニットリーダー研修の導入
今後は、職場環境の整備状況の確認要件が追加される予定です。また、経営の協働化や生産性向上への取り組みも評価される見込みです。
介護職員等処遇改善加算の算定要件
介護処遇改善手当は、介護職員等処遇改善加算を算定している事業所で支払われています。この加算を取得するためには、厚生労働省が定める以下「3つの算定要件」を満たす必要があります。
キャリアパス要件
キャリアパス要件とは、介護職員の職務内容や能力に応じた賃金体系・昇給基準を整備し、従業員に周知していることが求められる要件です。具体的には、以下5つの要件です。
- キャリアパス要件Ⅰ:任用要件・賃金体系
→職位・職責・職務内容に応じた任用要件とそれに応じた賃金体系の整備 - キャリアパス要件Ⅱ:研修の実施等
→介護職員の資質向上のための計画策定、研修の実施・機会の確保 - キャリアパス要件Ⅲ:昇給の仕組み
→定期的な昇給や経験・資格による昇給の仕組みづくり - キャリアパス要件Ⅳ:改善後の賃金額
→経験・技能がある介護職員の1人以上は年額見込み440万円以上 - キャリアパス要件Ⅴ:介護福祉士等の配置
→介護福祉士の人材配置
キャリアアップの仕組みが不明確なままだと、加算要件を満たさないと判断される恐れがあります。処遇改善加算が未算定、あるいは取り消された場合、処遇改善手当も支払われなくなるため、事業所としてはこの要件の整備と職員への周知が不可欠です。
月額賃金改善要件
月額賃金改善要件とは、加算を取得した結果として、介護職員の賃金が一定以上改善されていることを数値で示す必要があるという要件です。
- 月額賃金改善要件Ⅰ:新しい加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善
- 月額賃金改善要件Ⅱ:旧ベースアップ等支援加算額の2/3以上の新規の月額賃金改善
これは、加算で得た報酬が実際に職員の賃金に反映されているかをチェックする指標です。
たとえば、通所介護の加算率は6.3%のため、通所介護が要件を満たすなら、加算率6.3%の1/2以上の賃金改善が必要になります。
この実績が未達成の場合、加算の返還を求められることもあり、その結果として介護職員の処遇改善手当が「なくなる」ケースが起こります。
職場環境等要件
職場環境等要件は、介護職員が安心して働き続けられるような職場づくりに取り組んでいることを示すものです。具体的には以下のとおりです。
- 入職促進に向けた取り組み
- 資質向上・キャリアアップ支援
- 両立支援・多様な働き方の支援
- 心身の健康管理(腰痛も含む)
- 生産性向上に向けた取り組み
- やりがいの醸成
たとえば「業務負担の軽減」「有休取得率の向上」「腰痛予防のための福祉用具の導入」など、実際の改善策を複数項目から選択して実行する必要があります。
加算を算定するには、これらの取り組み内容を具体的に記録し、実地指導などで説明できる状態にしておくことが求められます。職場環境等要件を軽視していると、加算の対象外となり、結果的に処遇改善手当の支給も止まる可能性があるので注意しましょう。

\ インストールから登録まで5分! /
処遇改善加算を取得するための準備と手続き
処遇改善加算を受けるには、事業所側が厚生労働省が定める算定要件を満たし、必要な手続きを行う必要があります。以下では、具体的な申請の流れ、必要書類、相談先について詳しく解説します。
申請の流れと提出期限
処遇改善加算の申請は、原則として毎年度ごとに行われ、計画的な準備が大切です。流れとしては、まず処遇改善計画書(別紙様式2)を作成し、体制等状況一覧表とともに自治体へ提出します。
提出後、自治体による内容確認が行われ、要件を満たしていれば加算が適用されます。さらに、実績報告も年度末に必要となるため、記録の保存や管理体制の整備も欠かせません。
期限を過ぎた場合は加算が受けられなくなるため、スケジュール管理が非常に重要です。
必要書類と作成のポイント
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 処遇改善計画書(別紙様式2)
- 体制等状況一覧表(別紙様式1)
- 就業規則や賃金規程の写し(必要に応じて)
計画書では、賃金改善の内容を具体的に示すことが求められます。
たとえば、「介護福祉士には月5,000円を基本給に上乗せする」など、対象者・金額・支給方法を明確に記載します。
また、キャリアパス要件を満たすためには、職位や職責に応じた研修体系や評価制度を整備しておく必要があります。記載ミスや記入漏れは申請却下の原因になるため、厚労省の記入マニュアルやQ&Aを確認しながら進めましょう。
加算の取得状況は介護職員の処遇に直結するため、正確な書類作成が重要です。
自治体・外部専門家への相談活用法
処遇改善加算の申請や書類作成に不安がある場合は、自治体や外部専門家のサポートを活用するのが効果的です。各都道府県や市区町村には介護保険担当課が設置されており、加算の申請手続きや様式についての相談が可能です。
また、社会保険労務士(社労士)などの専門家に依頼すれば、就業規則の整備や計画書の作成支援を受けることもできます。
さらに、地域包括支援センターや業界団体が主催する研修・説明会も役立ちます。申請ミスを防ぎ、スムーズに加算を取得するためにも、これらのサポートを活用することが賢明です。
特に初めて申請を行う事業所は、早めに相談先を見つけておくと安心です。
2025年以降の処遇改善加算はどう変わる?

2024年6月の介護報酬改定で処遇改善加算が一本化されたとはいえ、制度の変化はこれで終わりではありません。今後も、介護現場の課題や労働市場の動向に応じて、さらなる制度再編や条件変更が検討される可能性があります。
現在議論されている制度再編の方向性
処遇改善加算に関して、今後の制度再編の方向性として厚生労働省が示しているポイントは主に以下の3つです。
- 複数加算の整理統合と透明化
- 賃金改善の実効性確保(処遇改善が給与に直結する仕組み)
- 職場環境やキャリア形成の評価との連動
これらの方針は、処遇改善が形骸化せず、実際に現場職員の待遇改善につながる仕組みづくりが目的です。また、ICT導入や業務効率化など「働きやすさ」を支える要素への加算反映も議論されています。
なお、これらは現時点での方向性であり、今後の審議会や業界団体の意見を踏まえて制度設計が進むため、具体的な加算要件や配分方式は変動する可能性があります。
ベースアップ・特定加算の今後の扱い
2024年の「一本化」により、従来の「介護職員等ベースアップ等支援加算」「特定処遇改善加算」は、形式上は新しい処遇改善加算に統合されました。しかし、要素そのものが消えたわけではなく、内部の配分ルールや要件の中に組み込まれる形で継続されています。
たとえば、特定加算で求められていたリーダー職や経験年数10年以上の職員への重点配分、ベースアップ加算での恒常的賃上げへの活用などは、引き続き新制度でも重視されると見られています。
今後に関しても、2025年には介護職員の給与を2.0%ベースアップすることが検討されているのです。
処遇改善加算のおさらい

処遇改善加算の内容は、介護報酬改定により変化していくでしょう。そのため、処遇改善加算の全体像を掴んでおくと、要件が変更されても理解が早まります。
そこで、ここでは処遇改善加算の概要や詳細について紹介します。
処遇改善加算とは
処遇改善加算は、介護職員の賃金や労働環境の改善を目的として始まった制度です。賃金バランスの改善や研修制度の整備、労働環境の改善などに取り組むことで、事業者が加算を受けられる仕組みです。
介護職員の待遇向上を図ることで、介護サービスの質の向上にも影響することを目指しています。多くの事業所で加算を取得しており、介護職員の給与アップにつながっています。
以下では介護職員の処遇改善加算とは何かを簡単に解説しているので、ぜひ参考にしてください。

処遇改善加算の要件
処遇改善加算には取得要件があり、具体的には以下のとおりです。
- キャリアパス要件
- 職場環境等要件
それぞれ解説します。
キャリアパス要件
キャリアパス要件は、特定の資格を取得する職員がいたり、キャリアアップにつながる研修を実施したりすると得られる加算制度です。加算に必要な条件は大きく分けて3つあります。
- 職務や役職の内容に合った賃金体系の整備
- 資格や経験に応じた昇給制度を設定
- 資格習得の支援やスキルアップ研修の実施
資格取得による昇給や資格支援をしている事業所に加算を増やす仕組みです。職員が長期的にモチベーションを持って働ける職場作りが必要です。
職場環境等要件
職員の増員やマネジメント強化、キャリアアップの支援、体調管理などのいくつかの項目があり、1つ以上の取り組みを実施している必要があります。事業所は定期的に研修を実施したり、面談を設定したりして、職員のスキル向上やモチベーションを管理します。
処遇改善金加算の区分
処遇改善加算は3つの加算率に区分されています。各区分の配分や介護職員1人あたりの支給額を紹介します。
処遇改善加算(Ⅰ)
処遇改善加算(Ⅰ)を得るには、キャリアアップ要件の1.2.3を満たし、職場環境等要件も満たす必要があります。金額は介護職員1人あたり月額37,000円相当です。
処遇改善加算(Ⅱ)
処遇改善加算(Ⅱ)を得るには、キャリアパス要件1.2を満たしたうえで、職場環境等要件を満たす必要があります。金額は介護職員1人あたり、月額27,000円相当です。

処遇改善加算(Ⅲ)
処遇改善加算(Ⅲ)はキャリアパス要件1.2を満たし、職場環境等要件を満たす必要があります。金額は月額15,000円相当です。
処遇改善加算(Ⅳ)処遇改善加算(Ⅴ)は廃止済み
処遇改善加算(Ⅳ)と処遇改善加算(Ⅴ)は、2018年の経過期間を設けて2022年3月に廃止されています。
処遇改善加算を取得している事業所のうち、66.2%が「I」で13.2%が「II」を算定しています。一方「III」は9.4%で、「IV」と「V」は0.8%ずつにとどまっていました。
【処遇改善加算を算定可能な事業所】
処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ):13.2%
処遇改善加算(Ⅲ):9.4%
処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ):0.8%
近年新設された処遇改善加算
処遇改善加算は近年新設されました。ここでは新しい処遇改善加算を紹介します。
介護職員等特定改善加算
介護職員等特定改善加算は、技能・経験を有する介護職員の処遇改善を目的にした制度で、2019年10月から新たに運用が開始されました。所得要件は以下の通りです。
- 処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していること
- 処遇改善加算の職場環境等要件の中で、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の各区分について、1つ以上の取り組みを行っていること
介護職員等特定改善加算では、勤続年数10年以上の介護福祉士に対し、月額平均8万円相当の処遇改善が目指されています。これは既存の処遇改善加算に上乗せされ、介護報酬が加算されます。
介護職員等ベースアップ加算
介護職員等ベースアップ加算は、2022年10月の介護報酬改定によって設立された制度です。
これは、コロナによる経済的な打撃を立て直すために導入された施策で、介護職員1人あたりの収入を基本的に月額約9,000円引き上げることを目的としています。
介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算と併せて、現在も実施されています。
処遇改善手当の支給方法とその決まり方
処遇改善手当は、介護職員の待遇向上を目的として支給されるもので、その支給方法や決定要因は事業所によって異なります。処遇改善手当の適正な受給につなげるためにも、以下の内容を参考にしてください。
支給のタイミングと形式
処遇改善手当の支給タイミングと形式は、各事業所の方針や財務状況により異なります。主な支給方法として以下の3つが挙げられま。
- 毎月の給与に上乗せ:基本給や手当に一定額を加算する形式
- 賞与(ボーナス)として支給:年2回の賞与に上乗せして支給する形式
- 一時金としてまとめて支給:年度末などにまとめて支給する形式
これらの支給方法は、事業所の労使協定や就業規則に基づいて決定されます。
そのため、勤務先の人事担当者や管理者に確認し、自身の処遇改善手当がどのように支給されるのかを把握しておくことが重要です。
支給額を左右する要素
処遇改善手当の支給額は、以下の要素によって決定されます。
- 資格の有無:介護福祉士などの資格を保有しているか
- 経験年数:介護業界での勤務経験がどの程度あるか
- 勤務形態:常勤か非常勤か、フルタイムかパートタイムか
- 事業所の加算取得状況:事業所がどの加算区分を取得しているか
これらの要素が組み合わさり、個々の支給額が決定されます。具体的な支給額やその決定基準については、事業所の人事担当者や管理者に確認することが重要です。
私は介護職として働いていますが、実際に「介護福祉士の資格」は給与アップにつながりました。多くの事業所では介護福祉士を取得すると、資格手当が付与されます。
施設によるものの、1〜2万円の資格手当が給与に含まれるので、給与が上がります。ほかの介護系資格でも資格手当が付与されますが、介護福祉士が最も高く設定されている事業所がほとんどです。
そのため、給与アップを目指すなら介護福祉士がおすすめです。
支給されないケースと注意点
処遇改善手当が支給されない、または減額される主なケースは以下のとおりです。
- 勤務時間が短い:
パートタイムや非常勤で、一定の勤務時間に満たない場合 - 必要な資格を保持していない:
事業所が定める資格要件を満たしていない場合 - 事業所が加算を取得していない:
事業所自体が処遇改善加算を申請・取得していない場
これらの条件に該当する場合、処遇改善手当の支給が行われない可能性があります。自身の勤務状況や資格、事業所の加算取得状況を把握し、必要に応じて資格取得や勤務時間の調整を検討することが重要です。
また私自身、処遇改善に頼らずとも年収アップを図るために、介護だけでなく副業をして市場から収入を得ることも検討しています。自分で事業を持つことで、収入は青天井になるからです。
安定している介護の仕事をしながら副業にチャレンジをして年収を上げていきたいと考えています。処遇改善加算や資格手当など、政府に求めることも重要ですが、自身でも給与を上げる方法を考えていくことも大切だと思います。
見逃さない!処遇改善手当と給与明細・時給の反映パターン
介護職員等処遇改善加算(新加算)は、事業所が要件を満たしていれば継続的に支給されます。
まずは勤務先の支給方法(毎月/賞与時/一時金)を確認し、自分の収入にどう反映されているかを把握しましょう。
時給にすでに組み込まれている場合(派遣・一部パート)
派遣やパートで「処遇改善手当」が見えない場合、実は時給がすでに加算済みのことがあります。
まずは明細の時給内訳を確認し、「+表記」がないかどうかを見てみましょう。
基本給・賞与・各種手当で支給される場合
一部の事業所では、「処遇改善手当」ではなく「賃金改善手当」「特定手当」などの名称、あるいは昇給や基本給への上乗せとして反映されることがあります。
この場合、給与明細の支給項目欄や備考欄に注意し、名称が違うだけかどうかをチェックしましょう。
明細のチェックポイント
明細の確認ポイントは以下です。
- 支給欄に「処遇改善」名があるか
- 時給や基本給が急に高くなっていないか
- 賞与や一時金として処遇改善分が含まれているか
- 備考欄に「賃金改善」等の注記があるか
これらに気づかないと、「もらえない」と誤解することがあります。
事業所に相談しても解決しない場合は外部の相談窓口へ
もし事業所への確認で納得のいく回答が得られなかった場合や、不正・未払いの疑いがある場合は、外部の相談機関に問い合わせることを検討しましょう。主な相談先は以下のとおりです。
| 窓口名 | 内容 |
|---|---|
| 労働基準監督署 | 未払い賃金 雇用契約違反の相談 |
| 自治体の福祉課 | 加算制度の運用や説明不足の対応 |
| 福祉人材センター | 業界慣行や転職を含む相談対応 |
特に「処遇改善加算を含む給与が未払い」「理由の説明がなく配分されない」といった場合は、労働基準監督署への相談が推奨されます。記録(明細や就業契約書など)を準備し、客観的な情報とともに相談することが重要です。
処遇改善加算と他加算制度との違い
介護職員の処遇改善を目的として、「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」の3つの加算が設けられています。これらはそれぞれ目的や対象者、算定要件が異なり、事業所が適切に理解し活用することが求められます。
各加算の目的と対象者は以下のとおりです。
| 加算制度 | 目的 | 対象者 |
|---|---|---|
| 処遇改善手当 | 介護職員全般の賃金改善 | すべての介護職員 |
| 特定処遇改善手当 | 高度なスキルを持つ職員の処遇改善 | 勤続10年以上の介護福祉士が主な対象 |
| ベースアップ等支援加算 | 介護職員の基本給の底上げ | 介護職員以外の職種にも一定割合で配分可能 |
これらの加算は、それぞれ異なる目的と対象者を持ち、事業所の状況に応じて適切に活用することが重要です。
これまでさまざまな処遇改善加算が設けられていますが、実際に僕が介護職を始めたときよりも給与は徐々に上がってきています。平成28年に介護職に就きましたが、令和4年には賞与込みで約8,000円上がりました。
加えて介護福祉士の資格を取得したので、資格手当により給与は上がっています。
介護処遇改善加算に関するよくある質問

介護処遇改善加算に関するよくある質問は以下のとおりです。
- 処遇改善金はパートでも受け取れるの?
- 処遇改善金がもらえない理由は?
- 処遇改善金は廃止される予定は?
介護処遇改善金はパートでも受け取れるの?
処遇改善金は、雇用形態や資格の有無に関係なく受け取ることができます。したがって、パート・アルバイトや派遣社員も支給の対象です。

処遇改善金がもらえない理由は?
事業所が処遇改善加算を受け取っていない場合、処遇改善金は支給されません。厚生労働省によると、処遇改善加算を取得している事業所は9割を超えています。

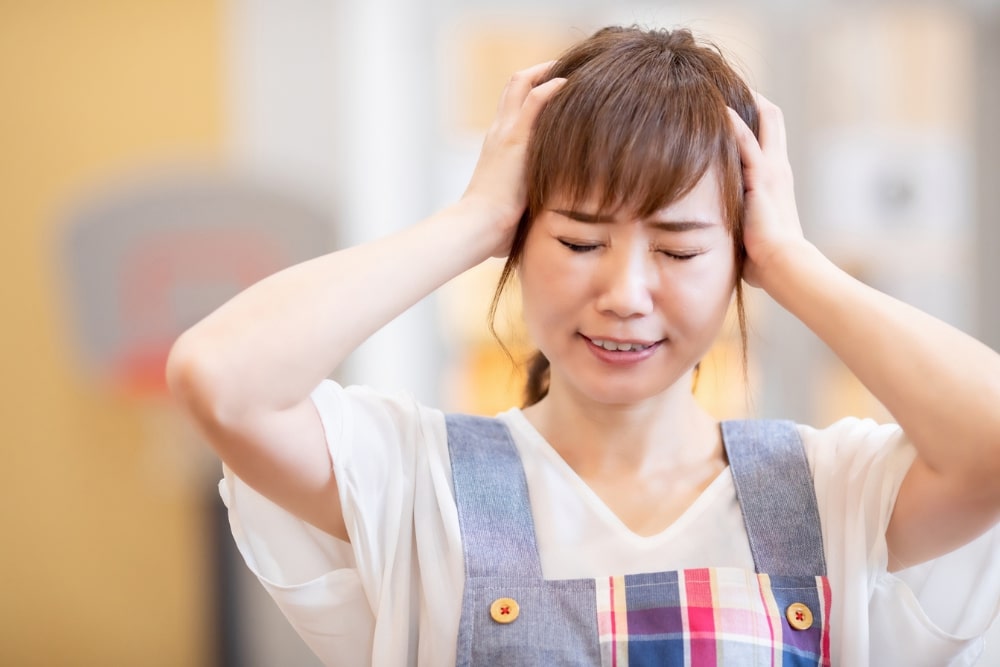
処遇改善金は廃止される予定は?
処遇改善金が廃止される予定は今のところありませんが、将来的にはわかりません。導入当時は介護現場の人材不足により、ユニットや事業所を閉鎖する施設が続出していました。
そのため、処遇改善加算は、人材不足解消の施策として期限付きで始まった制度です。介護職の人材不足が解消されたと政府が判断すれば、処遇改善金の制度を終了する可能性があります。
また、処遇改善金の財源は、介護保険制度から賄われている状況です。
介護保険財政がひっ迫している状況や利用者負担額の増加などを踏まえると、介護職の給与が一定の水準に達したと判断されれば、廃止や制度変更も考えられるでしょう。
処遇改善金はなくならないが、どうなるかはわからない
処遇改善金は介護職の給与アップに大きな影響を及ぼしています。令和6年(2024年)の介護報酬改定では、処遇改善加算がなくなることはありませんでした。しかし、今後はどうなるのかはわかりません。
介護保険の財政が厳しくなると、今後の計画次第で廃止される可能性があります。介護報酬が見直される3年に1度は、情報をキャッチアップしておきましょう。
カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。
- 「約5分」で給与GET!
- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!
- 働きながらポイントがザクザク溜まる!
27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /







