ジャンル別記事
認知症ケアで大切な5つのこと|基本原則と実践方法を解説
認知症の方の対応に「どう接すればいいのかわからない」「何を優先すべきか迷う」と悩みを抱えている方もいるでしょう。また、家族が認知症になり、どのような対応をするべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
適切な知識がないままでケアを続けていると、認知症の悪化や自分が心身ともに疲弊してしまう恐れがあります。間違ったケア方法は認知症の方の尊厳を傷つけ、家族関係にも深刻な亀裂を生じかねません。
家族が心がけるべきポイントまで、専門的な知識に基づいた実践的な解決策をわかりやすく解説します。
最後まで読めば、認知症の方の気持ちに寄り添った適切なケア方法が身につき、介護者自身も無理なく続けられるケアがわかるはずです。
認知症ケアとは?基本の考え方と重要性
認知症ケアとは、認知症の方が尊厳ある生活を送れるよう支援することです。単に介護するだけでなく、その人らしさを尊重し本人のできることを活かしながら生活をサポートします。
認知症は病気ですが、適切なケアにより生活の質は維持することが可能です。
認知症介護研究・研修センターをはじめとする専門機関の研究により、記憶障害があっても感情や感覚は比較的末期まで保たれることが医学的に明らかになっています。
そのため、コミュニケーションに配慮すれば相手に安心感を与えられます。認知症ケアは、医学的側面と人間的側面の両方からアプローチする包括的な支援なのです。
認知症ケアで大切な5つの基本視点
認知症ケアで大切なことは以下の5つです。
- その人らしい生活を尊重する
- 信頼関係を築く
- 「できること」を活かす
- 孤立を防ぎ社会とのつながりを守る
- 安心できる環境を整える
認知症ケアを効果的におこなうには、基本視点を理解し実践が欠かせません。5つの視点を身に付けることで、認知症の方により質の高いケアを提供できます。
1.その人らしい生活を尊重する
その人らしい生活を大切にすることが、認知症ケアの根幹になります。なぜなら、認知症になってもその人が長年培ってきた価値観や生活習慣は変わりにくいからです。
そのため病気になる前の生活歴や好み、得意なことを把握し、それらを活かした支援に活かすことが重要です。
たとえば、料理が得意な方には簡単な調理をお願いしたり、音楽好きの方には好きな楽曲を流したりします。
個人の特性を尊重することで、認知症の方でも自分らしい生活がしやすいようサポートできます。
2.信頼関係を築く
認知症の方と信頼関係を構築するには、感情的になりすぎないことが大切です。認知症の方は記憶力が低下していますが、嫌なことや不安に感じたことは覚えているといわれています。
認知症介護研究・研修センターによると、感情は末期の段階まで保たれることが医学的に確認されているのです。そのため、信頼できる人の存在が安心感につながる場合があります。
否定的な言葉は避け、可能な限り一貫した態度で接するよう心がけましょう。丁寧なコミュニケーションの積み重ねにより、認知症の方から信頼される関係を築きやすくなります。
参考:認知症介護情報ネットワーク「第三話:認知症になってもできること、認知症に対してできること」
3.「できること」を活かす
認知症の方には「できること」をしてもらうことで、自尊心や自立を支援することが大切です。
認知症は進行性の病気ですが、すべての機能が一度に失われるわけではありません。できることを見つけることで、本人の自信や生きがいが育ちやすくなります。
たとえば、洗濯物をたたんだりテーブルを拭いたりなど、昔から取り組んでいた行動や作業は覚えている傾向があります。
認知症の方は役割をもつことで、自分が必要とされていると感じられ、人としての尊厳を保ちやすくなるのです。
4.孤立を防ぎ社会とのつながりを守る
認知症により社会とのつながりが薄れると、症状を悪化させる可能性があります。東京都健康長寿医療センター研究所の研究によると、社会的孤立が認知機能低下や認知症発症のリスク因子であることが多くの研究で支持されています。
そのため、支援者による定期的な声かけや、一緒に時間を過ごして話を聞く姿勢は大切です。
たとえば、食事時間は一緒にテーブルを囲んだり、散歩のときには付き添ったりして、常に誰かが側にいる環境を作ります。
このように人とのつながりを維持することで、認知症の方の孤立を軽減できるでしょう。
参考:東京都健康長寿医療センター研究所「”希薄な社会的つながり”と”独居”は海馬の萎縮に関連するが、その作用は正反対:孤立のパラドックス」
5.安心できる環境雰囲気を整える
安心してくつろげる環境づくりは、認知症の方の心の安定に影響します。認知症の方は認識力の低下により、周囲の状況を理解しにくくなり、不安や混乱を感じやすくなります。
そのため、声のトーンは穏やかにし、強く触れたりつかんだりするような動きはしないよう注意が必要です。五感に配慮した環境を整えることで、認知症の方がリラックスして過ごせる空間を提供できます。
認知症ケアについて学びを深めたいと考える方は、単発バイトを通じてさまざまな施設を経験するのも一つの方法です。カイテクを使えば、スキマ時間を活用して近所で単発バイトができるため、ライフスタイルに合わせて働けます。
以下インタビューも参考に、カイテクの利用を検討してみてください。
Q:時間を有効に使い経験値を高めるために、カイテクは便利なツールかもしれませんね。Iさんがカイテクを選んだポイントはどんな点だったのでしょうか
A:まずは掲載されている施設の数が多いことです。他のサービスも少しだけ見てみましたが、カイテクは圧倒的な掲載数でした。また口コミも見ることができるので、安心感が大きかったですね。
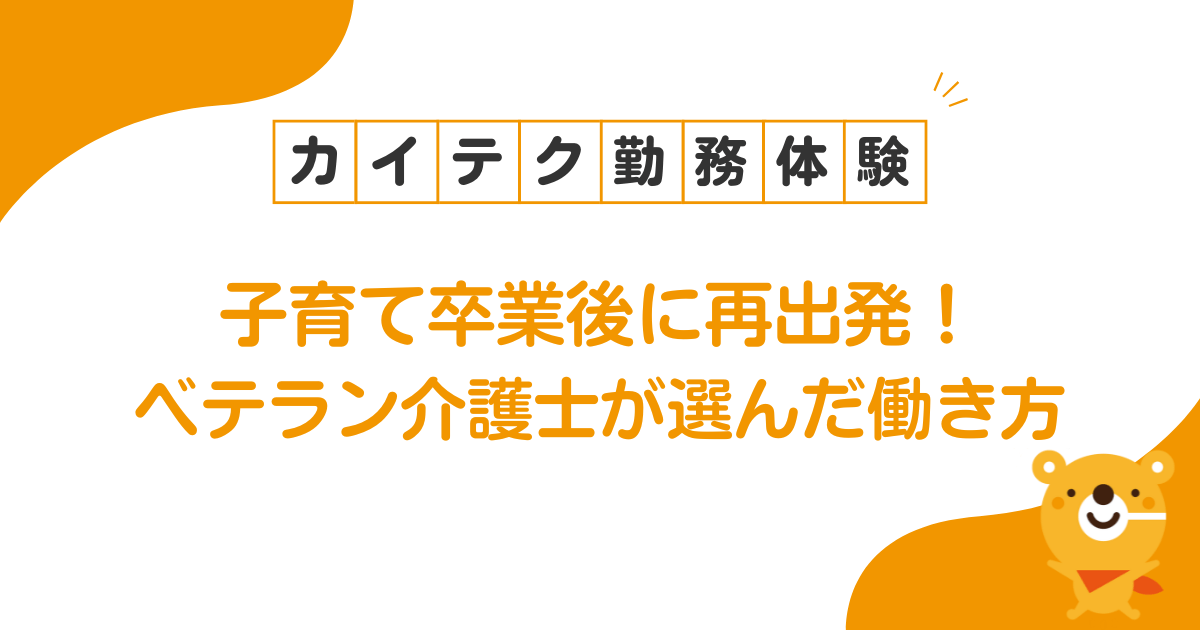

\ インストールから登録まで5分! /
認知症ケアの実践アプローチ【家庭・施設でできること】
ここでは、認知症ケアに対する具体的アプローチを紹介します。
- 見守りと安全確保
- 積極的なコミュニケーション方法(話し方・聞き方の工夫)
- バイタルチェックと健康管理
- 日常生活リハビリ(食事・運動・趣味活動)
- 家族支援と情報共有
認知症ケアでは、さまざまなアプローチを組み合わせることで、より効果的な支援を実現できます。それぞれの手法を適切に活用し、認知症の方の生活の質向上につなげましょう。
見守りと安全確保
見守り支援では認知症の方の安全を確保しながら、自立した生活をサポートします。24時間体制での観察が必要ですが、見守る際には過度な監視にならないよう配慮します。
転倒リスクがある場所へのセンサー設置や、定期的な巡回をして安全を確保しましょう。適切な見守りにより、認知症の方が安心して生活できる環境を提供することが可能です。
積極的なコミュニケーション方法(話し方・聞き方の工夫)
認知症の方は言葉によるやりとりが困難でも、感情や気持ちは伝わりやすいため、コミュニケーションは重要です。相手の目を見て話し、ゆっくりとした口調でわかりやすい言葉を使いましょう。
複雑な説明は避け、簡単な言葉や優しい表情、ジェスチャーを交えるのもおすすめです。認知症の方との意思疎通を図ることで、よりよい関係を維持しやすくなります。
バイタルチェックと健康管理
バイタルチェックは、認知症の方の健康状態を把握するうえでは欠かせません。認知症を発症すると、言葉で自分の身体状態を上手に伝えにくくなる方もいます。
体調の変化を適切に訴えられず、気づいた頃には発熱や感染症を引き起こしているケースもあります。そのため、血圧と脈拍、体温、呼吸状態を定期的に測定し、記録を残しておくことが重要です。
発熱や血圧の変動があれば、医療職と連携して適切な対応を取りましょう。継続的な健康管理により、認知症の方の体調変化を早期発見できます。
日常生活リハビリ(食事・運動・趣味活動)
リハビリテーションは身体機能だけでなく、認知機能の維持・向上も期待できると、日本内科学会雑誌が掲載している論文では説明されています。
倉敷平成病院では、多職種がチームで連携したリハビリを認知症の方に実施しました。
その結果、認知機能の有意な改善は見られなかったものの、認知症の行動・心理症状(BPSD)には、有意な改善効果が認められたと発表されています。
運動療法や音楽療法など、個人の状態に応じたプログラムを実施したことで、一人歩きや興奮状態がアプローチ前よりも低下したと考えられます。
継続的なリハビリテーションをすることは、認知症の進行を遅くする効果が期待できるでしょう。
家族支援と情報共有
家族の理解と協力なしには質の高いケアは実現できないので、家族支援も認知症ケアには欠かせない要素です。具体的には家族に対して認知症の病気について説明し、適切なかかわり方を指導します。
また、介護方法の指導やストレス軽減のためのアドバイス、社会資源の紹介などをします。認知症の方により安定したケアを提供しやすくするためにも、家族のメンタルや環境を整えることは重要です。
認知症ケアのアプローチについては、実践を通じて学ぶ方法が吸収が早くなるでしょう。カイテクを使えば、以下インタビューのIさんのように、認知症の方へのケアを体験できます。
Q:Iさんがこれまでにご利用になった施設での働き方を教えてください
A:これまでにカイテクから行った施設は8~9か所。
今通っている4つの施設は、デイサービス、認知症の方のグループホーム、認知症のショートステイ、それと障害者のグループホームです。それぞれ月に2回ほど通っています。
デイサービスでは入浴介助がメインの仕事です。
ショートステイは同じ認知症でも精神障害のある方や、認知はなくてもご病気で介護が必要な方などさまざまな方が利用されるため、本当に貴重な体験をさせていただいています。
認知症のグループホームは入所されている方もスタッフもみなさん人柄が良い方ばかりで、穏やかな雰囲気に満ちたステキな施設ですよ。
そして障害者の方のグループホーム。実は今はこちらを主に行かせていただいています。 そのほかにも自分の勉強になればいいなと、新しい施設に行くこともあります。
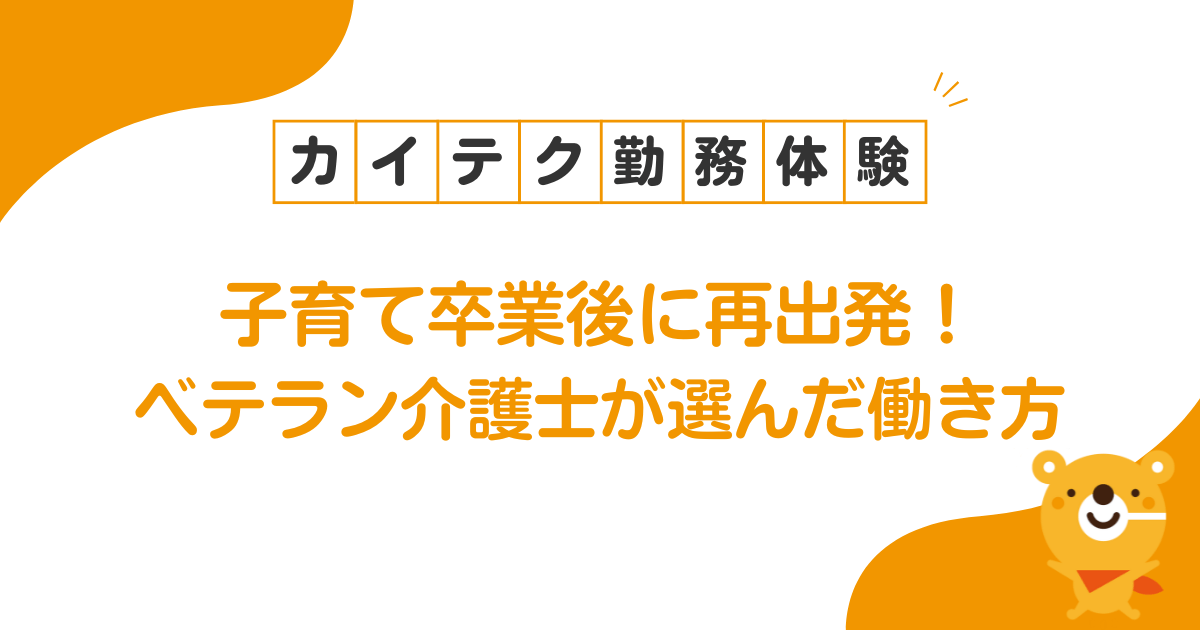
認知症ケアで避けるべきNG対応
認知症ケアで避けるべき言動は以下のとおりです。
- 怒鳴る・叱る
- 失敗を責める
- 子ども扱いをする
- 行動を急かす
- 命令口調になる
- 社会参加を妨げる
間違った言動は認知症の方を傷つけ、症状を悪化させる可能性があるため、十分な注意が必要です。
怒鳴る・叱る
認知症の方に対して、怒鳴ったり叱ったりすることは絶対に避けるべき対応です。なぜなら、認知症の方は感情が敏感になっており、強い口調により恐怖や混乱を感じやすいためです。
たとえば、同じことを繰り返し聞かれても、初めて聞くような気持ちで優しく答える姿勢が求められます。
ただし、症状による行動は本人の意思によるものではないとわかっていても、イライラしてしまうことはあるでしょう。
そのようなときは、他職員に対応を依頼したり、ショートステイサービスを活用したりして、心に余裕を取り戻すことも大切です。
穏やかな対応を心がけることで、認知症の方の心の安定を保ちやすくなり、日常のケアもしやすくなります。
失敗を責める
認知症の方は記憶力が低下していても、感情の変化は残りやすいといわれているので、失敗に傷つきます。失敗したときは責めるのではなく、さりげなくフォローする姿勢をもちましょう。
たとえば、食べ物をこぼしてしまったときも「大丈夫ですよ」と声をかけ、さりげなく片付けを手伝います。
受容的な態度を心がけることで、認知症の方が安心して過ごせる環境を作れます。
子ども扱いをする
子どものような扱いは、認知症の方の尊厳を損なうのでやめましょう。認知症であろうとも年齢に見合った敬意を示し、大人として接することが重要です。
幼稚な言葉遣いを使ったり、タメ口で話したりするのは避けるべきです。一般的な大人と同様に、丁寧語で人生経験を尊重した話題を選びます。
このように大人として尊重することで、認知症の方の自尊心を保ちやすくなります。
行動を急かす
認知症の方は脳機能が低下している傾向があるので、動作がゆっくりになり、判断に時間がかかります。そのため、行動を急かすことは認知症の方にプレッシャーを与えてしまうので、時間に余裕をもって対応し、ゆっくりと待ちます。
たとえば、着替えに時間がかかっても急かさず、必要に応じてさりげなくサポートすることが重要です。
相手のペースに合わせて対応し、認知症の方がストレスなく生活できるように支援しましょう。
命令口調になる
認知症の方でも自分の意思や感情は残っているため、命令されることに不快感を示す方もいます。命令口調での指示は反発を招く可能性があるので、お願いする形で伝えて選択肢を提示することが大切です。
たとえば、「お風呂に入ってください」ではなく「お風呂はいかがですか」と提案します。
小さな配慮ですが、認知症の方が自分の意思で行動できるよう支援できます。
社会に参加を妨げる
社会的な孤立感を感じると、認知機能が低下するリスクがあるので、地域のイベントやデイサービスに参加するのがおすすめです。
近年では「認知症カフェ」と呼ばれる交流の場が全国で運営されています。コーヒーを飲みながら地域の人や同じく認知症の方と話したり講話を聞けたりします。
また、デイサービスに参加すれば、同世代の方とかかわる機会も作ることが可能です。機能訓練を提供している事業所もあるので、認知機能の維持・向上もできるでしょう。
認知症になっても社会とのつながりをもち続けることは、生きがいと自信の維持につながります。家族支援にもつながるので、社会資源は積極的に活用するのがおすすめです。
家族が認知症をケアする際の心がけ
家族として認知症の方をケアする際は、以下の点を意識しておくことが重要です。
- 家族や友人に相談して孤立を防ぐ
- 介護サービスや制度を積極的に活用する
- 行動の背景を理解して受け止める
- ほかの家族やケースと比較しない
よりよい家族関係を維持するためにも、1人で抱え込まず、家族や友人、介護職などに頼ることを忘れてはいけません。
家族や友人に相談して孤立を防ぐ
一人で抱え込むとストレスが蓄積し、適切なケアができなくなる可能性があるため、介護負担を軽減するためにも他者への相談は大切です。
気持ちがいっぱいになる前に、信頼できる人に話を聞いてもらい、アドバイスを求めましょう。
たとえば、「認知症の人と家族の会」と同じ境遇の方が集まる会へ参加したり、親しい友人に愚痴を聞いてもらったりするのはおすすめです。
精神的な負担を軽減しながら認知症介護を続けるためにも、相談できる人を見つけておくことは重要です。
介護サービスや制度を積極的に活用する
介護サービスの活用は家族の負担軽減につながります。すべてを家族だけでおこなうと限界があり、燃え尽き症候群やうつ病になる危険性があります。
そのため、デイサービスやショートステイ、訪問介護など利用できるサービスを検討しましょう。週に数回デイサービスを利用するだけでも、家族の休息時間が確保できます。
専門的なサービスを活用することで、心身の負担を少なくしながら持続的なケアをすることが可能です。
行動の背景を理解して受け止める
認知症による行動・心理症状(BPSD)には必ず理由があり、その背景を理解することが問題解決の鍵となります。
認知症ケアの専門機関では、認知症の方の行動には不安や身体的不調、環境の変化などが影響していることが多いと報告されています。そのため、本人がなぜその行動を取るのかを観察し、原因を推測することが重要です。
たとえば、夜中に起き出す場合は不安や見当識障害が原因で、怒りっぽくなる場合は便秘や腹痛を起こしている可能性が考えられます。
このように行動の背景を理解できれば、具体的な解決策を見つけやすくなり、支援者も感情的になりにくくなります。
ほかの家族やケースと比較しない
ほかの家族との比較は無意味であり、かえってストレスを増大させます。なぜなら認知症の症状や進行は個人差が大きく、同じ対応でも効果が異なるケースがあるためです。
自分たちのペースでケアを進め、小さな改善やよい変化に注目することが大切です。家族介護をしている方は「○○さんの家はうまくいっている」といった比較をやめ、自身の家族ができたことに目を向けます。
自分たちなりのケアを認めることで、前向きな気持ちを維持できるでしょう。
【事例別】認知症の家族をケアする際のポイント
ここでは、認知症の家族をケアする際のポイントを事例別に紹介します。
具体的な内容は以下のとおりです。
- 同じ質問を繰り返すとき
- 帰宅願望が強いとき
- 暴言や物を叩く行動が続くとき
- 徘徊(ひとり歩き)があるとき
- 排せつの失敗があるとき
- 物盗られ妄想があるとき
認知症の症状は多様で、それぞれに適した対策があります。具体的な事例を通じて効果的な対処法を知ると、実際の場面でも落ち着いて対応できるようになります。
同じ質問を繰り返すとき
認知症の方は「今日は何月何日?」「夜ご飯は食べたかな?」など、同じ質問を何度もしてくることがあります。これは、記憶障害によって直前の出来事を覚えていられないために起こる症状の一つです。
家族にとっては「さっき答えたのに」とイライラしてしまい、つい感情的に反応してしまうことも少なくありません。こうしたやりとりが続くと、関係がぎくしゃくしてしまうことがあります。
ケアをするときには、繰り返しの質問は病気の症状であって本人のせいではないと理解することが大切です。
毎回初めて答える気持ちで「今日は○月○日の○曜日ですよ」「夜ご飯はさっき食べましたよ」と、具体的に答えてあげるとよいでしょう。
また、同じ質問の背景に不安が隠れている場合もあるため、原因や要因を探り、家族や他職種と情報を共有しながら対応策を考えていくことも大切です。
帰宅願望が強いとき
帰宅願望は認知症の方によく見られる症状で、現在いる場所を自分の家と認識できないと生じる場合があります。認知症の方にとっては不安な状態なので、「帰れませんよ」や「ここから出られません」など否定してはいけません。
まずは気持ちを受け入れ「そうですね、家に帰りたいですね」と共感しましょう。そして「もう少ししたら帰りましょうね。その前にお茶でも飲みませんか?」と別の話題を提案します。
また、なぜ帰りたいのかを理由を聞くように傾聴することでも、帰宅願望が収まる可能性もあります。相手の気持ちを受け止めながら話を聴くことを意識することが重要です。
暴言や物を叩く行動が続く収まらないとき
机やテーブルを叩く行動がある方の対応方法は、始まる前のサインを見落とさないことです。
たとえば、トイレ介助を拒否したあとに叩く行動が見られる場合は、かかわり方を見直す必要があります。
職員や家族と話し合いをしながら、どのようなときに机やテーブルを叩く状態になるのか、表情や言動を観察してみましょう。
そのうえで、声かけの仕方やトイレ誘導する時間帯を考え、対策を講じる必要があります。対応方法を定期的に振り返ることで、原因が明確になる可能性があります。
徘徊(ひとり歩き)がある見られるとき
ひとり歩きをする認知症の方は、周囲の雰囲気や環境への不安が原因で移動していることがあります。また、便秘や不眠など体調不安を表現できず落ち着けないのかもしれません。
したがって、まずはチームや家族と協力して、認知症の方の日中や夜間状況を確認してみましょう。そのうえで無理に止めるのではなく、安全を最優先にした対応を実施します。
たとえば、居間と廊下を行ったり来たりする方がいるなら、転倒に注意しながら一緒に歩いて見守ったり話しかけたりする対策が考えられます。
危険を回避しながら原因を探り、認知症の方の気持ちに寄り添うような対応をすることが重要です。
排せつのを失敗があるとき
認知症の影響でトイレの場所や膀胱内に尿が溜まっているのがわからないと、排尿を失敗してしまう方もいます。認識力の低下で失禁してしまう場合は、トイレに目印を付けて見つけやすいようにしておくとよいでしょう。
夜間は常夜灯をつけて歩きやすいようにしておくことも大切です。
また大きめの尿パッドを装着し、定時排せつをすれば失禁を防ぎやすくなります。利用者の環境を整えて、排尿の失敗をしないように支援していくことが大切です。
物盗られ妄想があるとき
認知症の方は記憶障害の影響により、自分が何をどこに置いたかを忘れ「物を誰かに盗られた」と思い込んでしまう場合があります。このとき認知症の方は、不安や恐怖を抱えていることも少なくありません。
そのため「誰も盗ってない」と職員や家族が言い返してしまうと、認知症の方は興奮してしまう可能性があります。まずは落ち着いて話を聞き「それは大変ですね」と共感を示すことが大切です。
そして「一緒に探しましょう」と声かけをしながら、探している理由などを聞いていきます。認知症の方が落ち着いてきたら、相槌を打ったり「そうなんですね」と話を否定せずに聞いたりします。
そのあとは、趣味や思い出の話をして別の話題に変えるのもおすすめです。また「通帳はこちらで保管していて、いつでも確認できますよ」など、事実を安心できる形で伝えるのも大切です。
専門職・制度を活用した認知症ケア
認知症ケアは一人で抱え込まず、専門職や制度を活用することで質の高いサポートが受けられます。ここでは、効果的な専門職との連携方法と、活用できる制度について詳しく解説します。
ケアマネジャー・訪問看護との連携
ケアマネジャーと訪問看護師との連携は、認知症ケアの質を向上させる効果的な方法です。 なぜなら、医療と介護の両面から包括的なサポートが受けられるからです。
ケアマネジャーは介護保険サービスの調整役として、認知症の方の状態に応じた最適なケアプランを作成します。一方、訪問看護師は医療的な専門知識をもち、服薬管理や健康状態の観察をするのがおもな仕事です。
たとえば、認知症の進行により薬の飲み忘れが頻繁になった場合、まずケアマネジャーがデイサービスの利用を提案します。
その後、訪問看護師が服薬カレンダーの設置と使用方法の指導をするといった連携ができます。両者が密に連携できていることで、認知症の方でも安心して生活できるケア体制を構築することが可能です。
認知症カフェ・地域包括支援センターの活用
認知症カフェと地域包括支援センターは、認知症の方とその家族にとって心強い地域の支援拠点です。これらの施設は、専門的な相談対応と社会参加の機会を同時に提供しています。
認知症カフェは、同じ悩みをもつ家族同士の交流や専門職による相談対応が受けられる場です。参加者との会話や対話を通して、認知症に関する情報を得たり考えを伝えたりできます。
活動内容はさまざまで、介護予防の体操や音楽会などが提供されている場所もあります。
たとえば、認知症の診断を受けたばかりの方が認知症カフェに参加することで、経験者からの体験談を聞き、不安が軽減されることもあるでしょう。
地域包括支援センターは医療や介護など、さまざまな分野から高齢者やその家族を支援する総合的な相談窓口です。
認知症に関する相談も可能で、適切なサービスへの橋渡しや利用可能な介護サービス・制度について詳しい説明を受けられます。
地域の支援拠点を積極的に活用することで、社会から孤立せず継続的なサポートを受けられるのです。
利用できる公的制度・助成金
認知症ケアには複数の公的制度や助成金が用意されており、経済的負担を軽減しながら質の高いケアが受けられます。
たとえば、認知症により要介護認定を受けることで、介護保険制度を活用できます。
訪問介護や通所介護、福祉用具レンタルなどのサービスが1〜3割の自己負担で利用することが可能です。認知症の症状によっては「精神障害者保健福祉手帳」や「身体障害者手帳」などの障害者手帳の申請もできます。
公共交通機関・公共施設の利用料金の割引や、税金控除や免税を受けたい方は利用を検討しましょう。
認知症と診断された場合には、公的支援を適切に活用し、経済的な不安を軽減しながら必要なサービスを継続利用するのがおすすめです。

認知症ケアで大切なことに関するよくある質問
認知症ケアに関するよくある質問は以下のとおりです。
- 認知症ケアで一番大切なことは何ですか?
- 認知症ケアに役立つ資格はありますか?
- 家族が認知症だと判断された場合、どのように対応すればいいですか?
認知症ケアで一番大切なことは何ですか?
認知症ケアで最も大切なのは、その人の尊厳を守り人格を尊重することです。認知症になっても、その人らしさや感情は残っているので、職員や家族は人間性に寄り添うことが大切です。
そのため、病気の症状に注目するのではなく、認知症の方のよい面や能力に焦点を当てましょう。できないことばかりに目を向けるのではなく、今できることや得意だったことを活かしたケアをします。
人として尊重する気持ちをもち続けることが、認知症ケアの根本となります。
認知症ケアに役立つ資格はありますか?
認知症ケアに役立つ資格は複数あり、知識とスキルの向上に有効です。
無資格・未経験から取得できる資格は以下のとおりです。
【無資格・未経験でも取得できる認知症の資格】
- 認知症ケア指導管理士
- 認知症介助士
- 認知症ライフパートナー
認知症に関する資格は専門的な知識だけでなく、家族や自身のメンタルケアについても学べます。そのため、自身も安心した状態で認知症の方をサポートし続けることが可能です。
家族が認知症だと判断された場合、どのように対応すればいいですか?
家族が認知症と診断された場合は、まず正確に情報収集し、適切な支援体制を整えることが大切です。診断を受けたばかりの時期は家族全員が動揺しやすく、冷静な判断が必要です。
医師から詳しい説明を受け、今後の見通しや利用できるサービスについて相談します。
たとえば、地域包括支援センターに相談したり、介護保険の申請をしたりして、必要な支援体制を作ります。
早期から適切な対応を取ることで、家族全員が安心して過ごせる環境を整えられるでしょう。
まとめ
認知症ケアは単なる介護ではなく、尊厳と人格を尊重した総合的な支援です。そのため、その人らしい生活を大切にし、信頼関係を築き「できること」を活かすという視点が大切です。
見守り支援やコミュニケーション、リハビリテーションなど具体的なアプローチを組み合わせることで社会全体でサポートできます。
また怒鳴ったり責めたりするような否定的な対応は避け、常に受容的な態度で接することが求められます。
家族としてケアする場合は、一人で抱え込まず周囲に相談し、介護サービスも活用しながら持続可能なケア体制を作ることが大切です。
認知症の方がより安心して生活できる環境を提供するために、それぞれの症状に応じた適切な対応方法を身に付けてみてください。
カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。
- 「約5分」で給与GET!
- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!
- 働きながらポイントがザクザク溜まる!
27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /







