ジャンル別記事
特養の生活相談員とは?現場での仕事内容や1日の流れを紹介
「特養の生活相談員はどのような仕事をしているの?」と疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?
特養の生活相談員は利用者や家族と施設を結ぶ重要な職種です。
その役割や業務内容を正しく理解しないまま転職を検討すると、入職後に「思っていた仕事と違う」といった問題に直面する可能性があります。
この記事を読むことで、特養の生活相談員の仕事がイメージでき、転職活動や職業選択の悩みが解決するはずです。
特養における生活相談員の役割
特養の生活相談員は、利用者と家族をつなぐ橋渡し的な存在です。
おもな役割は入所相談や家族との連絡、受診調整などの相談業務です。
例えば新規入所者の面談では、利用者の生活歴や身体状況を聞き取り、契約手続きを進めます。家族からの相談があれば、施設での生活状況を報告することもあります。
このように生活相談員は、利用者やその家族の生活全般にかかわる相談窓口となり、施設運営をサポートする職種です。
ここでは、さらに特養の特徴や他職種との違いを紹介します。特養における生活相談員の役割が明確になるでしょう。
そもそも特養とは
特別養護老人ホーム(特養)は、要介護3以上の高齢者が入所する介護保険施設です。
入浴・排せつ・食事などの基本的な身体介護をはじめ、服薬管理やバイタルチェックといった生活支援まで対応します。
特養を利用される多くの方が終の住処として住まれるので、基本的には終身利用です。
また特養では介護職員や看護職員など、多職種が連携して利用者をサポートしています。
そのため、チームワークが欠かせない職場環境です。
【体験談】
特養での仕事は生活支援よりも身体介護が中心です。
大規模な特養だと、入浴介助や排せつ介助を数十人対応することもあります。
シフト勤務なので、体力も必要です。
特養の生活相談員とケアマネジャーの違い
特養の生活相談員とケアマネジャーは、どちらも相談支援に携わりますが、業務範囲と責任が異なります。
特養の生活相談員は施設内の相談業務に特化し、入居者の日常生活に関する問題解決を担当します。
一方ケアマネジャーは、介護保険制度に基づいてケアプラン作成をするのがおもな業務です。
つまり生活相談員は施設での生活に関する相談、ケアマネジャーは介護者の支援計画を扱うのが仕事です。
そのため両者は連携しながらも、それぞれ異なる専門性を活かして業務にあたっています。
特養と他事業所の生活相談員の違い
特養の生活相談員は、デイサービスや訪問介護事業所の生活相談員と比べて、長期的な視点で利用者とかかわります。
デイサービスでは通所時間内での相談が中心ですが、特養では24時間365日の生活全般を支援対象としています。
例えばデイサービスの生活相談員は、送迎調整や通所回数の変更相談がおもな業務です。
しかし特養では、入所から看取りまでの長期間にわたる相談支援が求められます。
また医療機関や他施設との連携頻度が高いので、幅広い知識と調整能力が必要です。
特養の生活相談員は他事業所と比較すると、総合的な支援スキルが求められる職種です。
特養における生活相談員の仕事内容
特養の生活相談員の仕事内容は以下のとおりです。
- 入退所手続き
- 家族との連絡調整
- 受診調整や付き添い
- 事務手続き
- 見学対応
- 面接・聞き取り
- 入居者の相談対応
- 情報収集
- 現場業務
特養の生活相談員の業務は多岐にわたり、利用者の生活を支えるためのさまざまな調整業務を担当します。
入退所手続き
特養の生活相談員は入退所手続きを担当するのがおもな業務です。
施設の窓口的な役割なので、料金設定・サービス内容を利用者や家族に説明する場面が多々あります。
例えば入所希望者に対しては、家族との連絡調整や面談、書類の準備などをします。
困りごとや悩みがあれば、それに対して回答していくのも仕事の1つです。
入退所手続きの際には、利用者や家族の不安を和らげて安心して施設を利用してもらえるような心がけが必要です。
家族との連絡調整
特養の生活相談員は利用者の家族との連絡調整も仕事の1つです。
入所者の体調変化や生活状況を定期的に家族へ報告し、要望に対応します。
具体的には、利用者の身体状況や食事摂取量、レクリエーション参加状況などを詳しく報告していきます。
急な体調変化があった場合は、すぐに家族へ連絡し、必要に応じて面談を設定することもあるでしょう。
生活相談員が家族と定期的に連絡を取ることで、利用者によりよいケアを提供できる環境を整えられます。
受診調整や付き添い
特養の生活相談員は、利用者の医療機関への受診に関する調整業務を担います。
なぜなら、利用者の症状や日常生活での困りごとを医師に正確に伝えられる人が必要だからです。
具体的には定期受診のスケジュール管理や、専門医への紹介状準備、受診時の付き添いなどをします。
入浴日や家族の面会などの予定を考慮して受診日を決定し、病院までの送迎や添乗に対応します。
入院が必要になった場合は、医療機関や家族と連絡をし、入院準備をサポートすることもあるでしょう。
特養の生活相談員は医療と介護の橋渡し役となるので、利用者の健康を管理するうえでは欠かせない存在なのです。
事務手続き
特養の生活相談員は、新規入所時の契約書や介護保険の更新、各種申請書類の作成などをおこないます。
とくに介護保険の区分変更申請では、利用者の身体状況を正確に把握し、適切な書類を作成する必要があります。
また退所時には精算書や引き継ぎ書類の作成も生活相談員の役目です。
これらの事務手続きは利用者の生活に直結するため、正確性と迅速性が求められます。
見学対応
特養の生活相談員は、入所を検討している利用者やその家族への見学対応をします。
おもに施設の概要説明や居室・共用スペースの案内などの説明をおこないます。
利用者の身体状況や認知症の程度を聞き取り、施設での生活に適しているかを判断するのも生活相談員の役目です。
また、入所費用や利用料金についても詳細に説明し、家族の不安や疑問に丁寧に対応します。
そのため、見学対応は入所につながる重要な業務です。
面接・聞き取り
特養の生活相談員は適切なケアプランを作成するためにも、入所希望者との面接と聞き取りを通して、利用者の基礎情報を収集します。
個別ケアをするためにも、利用者のこれまでの生活スタイルや趣味などを知ることが大切です。
例えば元教師の方には読書環境を整えたり、農業経験者には園芸活動への参加を提案したりします。
また、医療情報や服薬状況も詳細に確認し、看護師や医師との連携に必要な情報を整理します。
面接・聞き取りは、質の高いケア提供の基盤となる仕事です。
入居者の相談対応
特養の生活相談員は、施設に入所している利用者からの相談に対応するのも業務の1つです。
利用者からは、身体の不調や生活環境への不満、他入居者との人間関係など、さまざまな相談を受けます。
例えば、「入浴日を変更してほしい」や「施設の利用料金が払えているか心配」などと言われることがあるでしょう。
それらの悩みに対して生活相談員は、傾聴と共感を基本として相談に乗ります。
利用者の不安を取り除けるよう、一人ひとりに寄り添った対応が求められます。
情報収集
特養の生活相談員は、現場で利用者の情報収集をすることもあります。
なぜなら、他職種や家族から「入居者の状態変化や生活状況について教えてほしい」と言われることがあるからです。
例えば家族から「利用者の骨折後の状態を教えてほしい」と言われることがあります。
その際にはユニットへ出向き、記録を見返したり職員から聞き取ったりして情報を集め、家族に伝えます。
生活相談員が調べた内容をもとに、他職種や家族と連携して利用者の介護を提供することもあるので、情報収集は大切な仕事です。
現場業務
人手の少ない職場で働いていたり現場と兼務していたりする生活相談員は、介護業務にかかわることも少なくありません。
食事介助や入浴介助などの身体介護はもちろん、レクリエーション企画の業務に携わることもあるでしょう。
職員が不足した夜勤帯があれば、介護職員のヘルプでシフトに入る場合もあります。
利用者との日常的なコミュニケーションを通じて、相談業務に必要な情報収集をしている方もいます。
生活相談員が介護業務と相談業務の両方を担うことで、利用者により質の高い支援を提供できるのです。

\ インストールから登録まで5分! /
特養の生活相談員に求められる4つの資質
特養の生活相談員に向いている人の特徴は以下のとおりです。
- コミュニケーション能力
- 学習意欲
- 共感力
- 同時進行で業務を処理する力
特養の生活相談員に向いているかわかることで、職種のミスマッチを防げるでしょう。
1.コミュニケーション能力
特養の生活相談員には、コミュニケーション能力が高い方が向いています。
なぜなら利用者や家族、他職種の相談に対応し、適切な解決策を提案できる能力が必要だからです。
例えば利用者への支援方法について、現場職員と管理職との間に意見の違いが生まれることもあるでしょう。
また場合によっては、家族にとって不都合なことを伝えなくてはいけない場面もあります。
そのようなときでも、対話や傾聴などのコミュニケーションを通して、建設的な解決策を見つけていかなければいけません。
そのため、相手の意見に寄り添いつつも、自身の意見を伝えられる人が生活相談員に向いています。
2.学習意欲
介護保険制度や関連法令について継続的に学習する意欲があり、事務作業を正確におこなえる人も生活相談員に適しています。
介護保険法は3年に1度改正されるので、介護保険制度や加算ルールは変化します。
家族や利用者に正確な情報を伝えるためにも、生活相談員は情報を常にアップデートさせていかなくてはいけないのです。
また生活相談員は、医師やケアマネジャーなどの他職種とかかわります。医療や地域資源の知識がなくては、他職種と利用者を円滑につなげません。
したがって学習意欲がある方が生活相談員に向いています。
3.共感力
相手の悩みに寄り添った対応ができる人が、特養の生活相談員には向いています。
利用者や家族は、「施設に入ることに抵抗がある」「契約方法がよくわからない」など不安を抱えて施設の窓口に相談しに来ることもあります。
そのようなときに生活相談員は相手に共感することが大切です。
自分の意見をすぐに伝えるのではなく、相手の気持ちを汲み取り、対話できる方が生活相談員に向いています。
4.同時進行で業務を処理する力
特養の生活相談員は、1日にいくつもの業務を進めていきます。
例えば、午前中に入所手続きと見学対応、午後には面会と委員会への出席などをします。
人手が足りないときには、現場の業務に入ることもあるでしょう。
1つの仕事がきれいに終わらない場合もあるので、生活相談員には業務を同時進行で進める力が求められます。
特養の生活相談員になるために必要な資格要件
社会福祉法第19条により、生活相談員になるためには以下の資格が必要となっています。
- 社会福祉主事
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 介護福祉士
- 生活支援専門員(ケアマネジャー)
- 未経験や無資格者
社会福祉主事
社会福祉主事は、児童相談所や福祉事務所などの公的機関で、生活保護や福祉サービスの相談・援助などをできるようになる任用資格です。
特養の生活相談員になるための要件に、社会福祉主事の取得が含まれています。
具体的な取得方法は以下のとおりです。
【社会福祉主事の受験資格ルート】
| 学歴・経歴 | 条件 |
|---|---|
| 指定科目を履修した大学卒業者 | 大学・短大・専門学校等で、指定された社会福祉関連科目を3科目以上履修することで任用資格を得られる |
| 厚生労働大臣指定養成機関の修了者 | 22科目1,500時間の講習を受けて任用資格を得られる |
| 都道府県等講習会の受講者 | 19科目279時間の講習を受けて任用資格を得られる |
| 社会福祉士または精神保健福祉士の資格保持者 | 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を取得することで任用資格も得られる |
4年制大学や短期大学での関連科目の履修や、指定研修を受講することで社会福祉主事を取得できます。
大学からの受講の場合、通信教育や夜間講習でも取得できるので、社会人の方でも取りやすいでしょう。
社会福祉士
社会福祉士とは、高齢者や障がい者・児などで、日常生活が困難な方をサポートする仕事です。
福祉制度の説明やサービスの紹介などの相談援助業務をおこないます。
社会福祉士を取得するには、国家試験を受けるための受験資格を取得する必要があります。
具体的な資格取得ルートは以下のとおりです。
【社会福祉士の受験資格ルート】
| 学歴・経歴 | 条件 |
|---|---|
| 福祉系大学(4年)卒業 | ・指定科目履修をしていれば受験可能 ・基礎科目を履修した場合、短期養成施設(6か月以上)の通学が必要 |
| 福祉系短大(3年)卒業 | ・指定科目履修+相談援助業務1年で受験可能 ・基礎科目履修+相談援助業務1年の場合、短期養成施設(6か月以上)の通学が必要 |
| 福祉系短大(2年)卒業 | ・指定科目履修+相談援助業務2年で受験可能 ・基礎科目履修+相談援助業務2年の場合、短期養成施設(6か月以上)の通学が必要 |
| 一般大学(4年)卒業 | 一般養成施設(1年以上)の通学が必要 |
| 一般短大(3年)卒業 | 相談援助業務1年+一般養成施設(1年以上)の通学が必要 |
| 一般短大(2年)卒業 | 相談援助業務2年+一般養成施設(1年以上)の通学が必要 |
| 実務経験(4年) | 一般養成施設(1年以上)の通学が必要 |
| 社会福祉主事養成機関卒業 | 相談援助業務2年+短期養成施設(6か月以上)が必要 |
| 児童福祉司身体障害者福祉司査察指導員知的障害者福祉司老人福祉指導主事実務経験(4年) | 短期養成施設(6か月以上)の通学が必要 |
学習期間は学歴や経歴により異なります。時間はかかりますが、高齢者福祉を体系的に学んでから特養の生活相談員になりたい方にはおすすめです。
社会福祉士について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
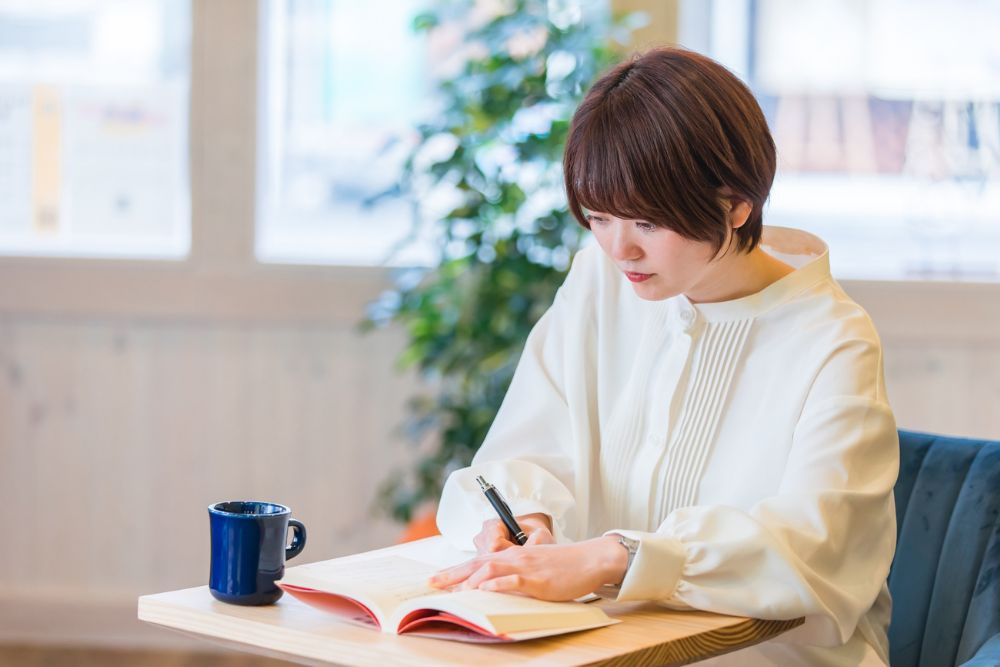
精神保健福祉士
精神保健福祉士とは、知的障がいや精神障がいなどを抱えている方の社会復帰を支援する仕事です。
相談や助言だけでなく、必要であれば機能訓練もおこないます。
精神保健福祉士を取得するには、国家試験を受験するための資格を得る必要があります。
具体的な受験資格ルートは以下のとおりです。
【精神保健福祉士の受験資格ルート】
| 学歴・経歴 | 条件 |
|---|---|
| 保健福祉系大学(4年)卒業 | 指定科目履修をしていれば受験可能 |
| 保健福祉系大学(3年)卒業 | 指定科目履修+相談援助業務1年で受験可能 |
| 保健福祉系大学(2年)卒業 | 指定科目履修+相談援助業務2年で受験可能 |
| 福祉系大学(4年)卒業 | 基礎科目履修+短期養成施設(6か月以上)の通学が必要 |
| 福祉系短大(3年)卒業 | 基礎科目履修+相談援助業務1年+短期養成施設(6か月以上)の通学が必要 |
| 福祉系短大(2年)卒業 | 基礎科目履修+相談援助業務2年+短期養成施設(6か月以上)の通学が必要 |
| 一般大学(4年)卒業 | 一般養成施設(1年以上)の通学が必要 |
| 一般短大(3年)卒業 | 相談援助業務1年+一般養成施設(1年以上)の通学が必要 |
| 一般短大(2年)卒業 | 相談援助業務2年+一般養成施設(1年以上)の通学が必要 |
| 実務経験(4年)卒業 | 一般養成施設(1年以上)の通学が必要 |
| 社会福祉士登録者 | 短期養成施設(6か月以上)の通学が必要 |
精神保健福祉士も社会福祉士と同様に養成施設や実務経験が必要です。
また社会福祉士を保持している場合なら、最短6か月で精神保健福祉士の受験資格を得られます。
介護福祉士
介護福祉士を取得後に生活相談員を目指す方も福祉現場には多い傾向です。
この資格があれば、一定の介護技術や経験をアピールできるので、生活相談員への転職を有利に進められます。
介護福祉士を取得するには、以下の受験資格ルートを通過し、国家試験に合格する必要があります。
【介護福祉士の受験資格ルート】
| 学歴・経歴 | 条件 |
|---|---|
| 高校卒業 | 介護福祉士養成施設(2年以上)で受験可能 |
| 福祉系大学卒業社会福祉士養成施設卒業保育士養成施設卒業 | 介護福祉士養成施設(1年以上)の通学が必要 |
| 実務経験3年+実務者研修修了者 | 受験可能 |
| 実務経験3年+介護職員基礎研修+喀痰吸引等研修修了者 | 受験可能 |
| 福祉系高校(平成21年度以降入学者) | 受験可能 |
| 福祉系高校(特例高校の場合) | 実務経験9か月以上が必要 |
| 福祉系高校(平成20年度以前の入学者) | 介護福祉士資格の登録を申請するまでに「介護過程Ⅲ」を受講し、登録申請時に「介護過程Ⅲ修了証明書」を提出する必要あり |
| EPA介護福祉士候補者 | 実務経験3年以上+介護福祉士資格の登録を申請するまでに「介護過程Ⅲ」を受講し、「介護過程Ⅲ修了証明書」を提出する必要あり |
未経験や無資格から介護職を始めた方は、実務経験を積んだあとに実務者研修を修了して介護福祉士を取る方がほとんどです。
介護福祉士の合格率や試験形式を知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

生活支援専門員(ケアマネジャー)
ケアマネジャーの資格をもちながら特養の生活相談員をしている方もいます。
この資格を取得するには、以下のルートや条件を通過する必要があります。
【ケアマネジャーの受験資格ルート】
| 経歴 | 条件 |
|---|---|
| 法定資格保有者(看護師や介護福祉士、理学療法士などの国家資格) | 実務日数900日(5年以上)が必要 |
看護師や介護福祉士、理学療法士などの国家資格を保持し、かつ実務経験がないとケアマネジャーは取得できません。
そのため介護業界で一定のキャリアがある方のみ挑戦できる資格です。
未経験や無資格者
生活相談員になるための条件は各都道府県により異なります。
そのため、地域によっては未経験や無資格からでも特養の生活相談員になることは可能です。
これから介護業界を目指していて、すぐに生活相談員になりたい方は、お住まいの自治体で確認してみるのをおすすめします。
また以下の記事では、47都道府県すべての生活相談員になるための条件を記載しているので、ぜひ読んでみてください。

特養の生活相談員の給与体系
ここでは、特養の生活相談員の給与体系に関する以下の内容を紹介します。
- 特養の生活相談員の給料
- 他職種との給料差
- 特養の生活相談員の賞与
特養の生活相談員の給料
特養の生活相談員に特化した給料情報はありませんでしたが、生活相談員の給料は以下のとおりです。
【生活相談員の給料】
| 令和5年 | 26万7,120円 |
| 令和6年 | 27万7,800円 |
令和5年の給料は26万7,120円でしたが、令和6年には27万7,800となり1万680円上がっています。
生活相談員の給料は事業所の規模により変化しますが、特養は利用者の人数が多いので比較的高いでしょう。
他職種との給料差
生活相談員と他職種の給料を比較してみましょう。
【生活相談員と他職種の給料】
| 職種 | 給料 |
|---|---|
| 生活相談員 | 27万7,800円 |
| 介護職員 | 25万3,810円 |
| 看護師 | 29万590円 |
| リハビリ職 | 28万6,820円 |
| ケアマネジャー | 29万340円 |
| 事務職員 | 24万8,410円 |
| 管理栄養士・栄養士 | 25万240円 |
医療・福祉職のなかで最も高いのはケアマネジャーですが、生活相談員は3番目なので、比較的高いといえます。
特養の生活相談員の賞与
特養の生活相談員に特化した賞与の情報はありませんでした。
しかし令和4年度介護労働実態調査によると、生活相談員の賞与は68万4,261円と発表されています。
多くの事業所ではボーナスは年2回給付されるので、一度に支給される金額は約34万円です。
福祉職の賞与は階級や勤続年数などによって変化するため、すべての方がこの賞与額とは限りませんが、1つの判断材料になるでしょう。
特養で働く生活相談員の1日の流れは?
特養で働く生活相談員の1日の流れは以下のとおりです。
【生活相談員の1日の流れ】
| 時間 | 業務 |
|---|---|
| 8:00 | 出社 |
| 8:30 | 事務処理 |
| 9:00 | 朝礼 |
| 9:30 | 入所申し込み、施設見学の対応 |
| 11:00 | 問い合わせ対応・面会予約受付 |
| 12:15 | 現場で情報収集 |
| 12:30 | 委員会に出席 |
| 13:00 | 休憩 |
| 14:00 | 入居申込者に面会・聞き取り |
| 15:30 | 入所者の相談対応 |
| 16:00 | ミーティング・書類作成 |
| 17:00 | 退社 |
生活相談員は常に事務処理や入居希望者の面会、委員会への出席などに対応しています。
肉体労働よりも頭脳労働の割合が多くなるでしょう。
特養の生活相談員で働くメリットや魅力
特養の生活相談員で働くメリットや魅力は以下のとおりです。
- 利用者やその家族から感謝の言葉をもらえる
- 日勤のみや夜勤がないため生活リズムが整う
- 調整力が身につく
- 介護保険制度の知識が身につく
特養の生活相談員になることで、感謝の言葉をもらえたり生活リズムが崩れにくくなったりします。
利用者やその家族から感謝の言葉をもらえる
特養の生活相談員は、利用者と家族の困りごとを解決することで、感謝の言葉をもらえる職種です。
入所相談から看取りまで長期間かかわるため、家族との信頼関係も深くなります。
入所時に不安を抱えていた家族が感謝の言葉を伝えてくれるときの喜びは、何物にも代えられません。
また、利用者本人からも「相談しやすい」「話を聞いてくれる」などの言葉をもらえることが多く、人の役に立っている実感を得られます。
そのため生活相談員はやりがいを感じながら働ける仕事です。
日勤のみや夜勤がないため生活リズムが整う
特養の生活相談員は基本的に日勤のみとなるため、規則正しい生活リズムを維持できます。
介護職員のように夜勤や早番、遅番のシフト勤務がないため、プライベートの時間を確保しやすくなります。
例えば平日は9〜17時の勤務で、土日祝日は休みになる場合が多いので、家族との時間を大切にできるでしょう。
また夜勤による体調不良や睡眠不足の心配もなく、健康を維持しながら働けます。
生活相談員は、ワークライフバランスを重視する人にとって魅力的な職種です。
調整力が身につく
特養の生活相談員は、多職種や家族との連絡調整を日常的にするため、高い調整力が身につくでしょう。
医師や看護師、介護職員などさまざまな職種と連携し、それぞれの専門性を理解したうえで利用者の支援方法を検討します。
例えば介護職から「最近○○さんの食事量が減っている」との報告を受けたら、生活相談員は他職種と対応策を考えます。
医師の指示や栄養士の意見、介護職員の観察結果を総合的に判断し、家族に説明しなければいけません。
家族からの要望と施設の方針の調整も必要なので、双方が納得できる解決策を見つける能力が養われます。
介護保険制度の知識が身につく
特養の生活相談員は、施設の事務手続きにかかわるので、介護保険制度の知識を身につけることが可能です。
入退所に関する手続きや各種加算の算定など、介護保険制度の実務を幅広く経験します。
複雑な加算の算定要件を理解し、適切な書類作成をする必要もあります。
また介護保険制度は3年に1度法改正されるので、最新の情報を把握しておくことが大切です。
このような知識は介護業界でのキャリアアップに直結し、将来的にケアマネジャーや施設長を目指す際にも活かせます。
特養の生活相談員で働くデメリットや注意点
特養の生活相談員で働くデメリットや注意点は以下のとおりです。
- 兼務で忙しくなる
- 現場と経営陣の意見を聞かなくてはいけない
- 利用者とコミュニケーションする機会が減る
- 介護保険や加算などの幅広い知識を身につけなくてはいけない
特養で生活相談員を始めたいと考えている方は注意しましょう。
兼務で忙しくなる
特養の生活相談員が相談業務と介護業務を兼務すると、業務量が多くなります。
例えば午前中は相談業務をしつつ、午後は食事介助や入浴介助にも入る場合があります。
人手不足の現場では、緊急時や夜間の呼び出しにも対応する場合があり、精神的な負担も大きくなるでしょう。
1人部署で兼務していると、相談業務が手につかなくなり、書類仕事で忙しくなる可能性もあります。
そのため生活相談員には、時間管理能力と体力の両方が求められます。
現場と経営陣の意見を聞かなくてはいけない
特養の生活相談員は、現場職員と経営陣の間に立つため、両方の意見を調整する必要があります。
現場職員からは人員不足や労働環境の改善要求をされます。
一方、経営陣からは経営効率や収益性の向上が求められることもあるでしょう。
そのため、職員の要求と経営陣の方針の板挟みになることも少なくありません。
どちらの立場も理解し、現実的な解決策を提案する能力が生活相談員には求められます。
利用者とコミュニケーションする機会が減る
特養の生活相談員は、事務作業や調整業務が増えるため、利用者と直接コミュニケーションする機会が限られます。
介護職員のように日常的な介護を通じて利用者との関係を築くことが難しく、相談業務も家族との連絡が中心です。
1日の大半をデスクワークで過ごし、利用者とは挨拶程度しかない日も少なくありません。
また利用者の身体状況や生活の変化を把握するのも、他職員からの報告に頼ることが多くなります。
そのため、利用者との直接的なかかわりを重視する人には、生活相談員の仕事は物足りなく感じる場合があります。
介護保険や加算などの幅広い知識を身につけなくてはいけない
特養の生活相談員は、介護保険制度に関する幅広い知識を常に更新し続ける必要があります。
なぜなら介護保険法は3年ごとに改正されるからです。
そのため例えば、認知症チームケア推進加算や生産性向上推進体制加算など、新しい算定要件を正確に把握しなくてはいけません。
また運営指導への対応も求められ、常に最新の法令や通知を確認する必要があります。
このような継続的な学習負担は、日常業務に加えて大きなプレッシャーとなる場合があります。
よくある質問
特養の生活相談員に関するよくある質問は以下のとおりです。
- 特養の生活相談員は兼務できるの?
- 特養の生活相談員は大変?
- 特養の生活相談員は夜勤をやっている介護職員よりも給料が下がる?
- 特養の生活相談員の求人はどうやって見つける?
特養の生活相談員は兼務できるの?
特養の生活相談員は人員配置基準を満たしていれば兼務が可能です。
特養では入居者数100人に対し、常勤の生活相談員を1人以上配置することが義務付けられています。
この要件が守られていれば、生活相談員と介護職を兼務できます。
ただしローカルルールがあるので、気になる方は自治体のホームページを確認するか、高齢福祉課などに問い合わせてみましょう。
特養の生活相談員は大変?
特養の生活相談員は大変ですが、やりがいもあります。
生活相談員は利用者や職員の意見に板挟みとなり、精神的につらいこともあるでしょう。
監査の時期は書類や記録の整備・提出などをしなくてはいけないので、必要に応じて修正や補足などが発生し忙しくなることもあります。
しかし利用者や家族から「話しやすい」「わからないことが解決した」などと言われて感謝されることも多い仕事です。
職員からは「現場のこともわかってくれている」とポジティブな意見をもらえることもあります。
特養という職場ならではの大変なことや、やりがいが生活相談員にはあります。
特養の生活相談員は夜勤をやっている介護職員よりも給料が下がる?
生活相談員と介護職の給料差は、夜勤の有無だけでなく総合的な待遇を比較することが必要です。
介護職員の夜勤手当は1回あたり5,000〜1万円程度なので、月4回の夜勤をする場合、月額2〜3万円の収入増になります。
一方、生活相談員は基本給が高く、資格手当も支給されるので、年収ベースでは同程度になる可能性があります。
そのため夜勤の有無だけでは一概に判断できません。
特養の生活相談員の求人はどうやって見つける?
特養の生活相談員の求人は、介護専門の求人サイトやハローワーク、施設の公式サイトで見つけられます。
「介護ワーカー」や「カイゴジョブ:などの専門サイトでは、生活相談員の求人を条件で絞り込んで検索することが可能です。
資格要件や給与条件、勤務地などを指定して検索できるので、希望に合った求人を効率的に見つけられます。
また地域の社会福祉協議会や福祉人材センター、施設のサイトでも求人情報を提供しているので、定期的にチェックしてみましょう。
まとめ:特養の生活相談員は大変だがやりがいもある
特養の生活相談員は、利用者と施設をつなぐ架け橋として、入所相談から看取りまで幅広い相談支援をおこなう専門職です。
社会福祉士や介護福祉士などの資格を活かし、他職種との連携を通じて利用者の生活の質向上に努めます。
勤務体系の面では、日勤勤務で規則正しい生活を送りながら働けるので、趣味や家族との時間を確保しやすいでしょう。
一方で現場と経営陣の板挟みになる精神的な負担もあります。
そのため、コミュニケーション能力や責任感をもって介護の仕事に望める方にとっては、特養の生活相談員は魅力的な仕事といえます。
カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。
- 「約5分」で給与GET!
- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!
- 働きながらポイントがザクザク溜まる!
27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /







