ジャンル別記事
看護師がよく使う医療略語一覧!意味や効率的な覚え方まで徹底解説
看護の現場で、先輩や医師の会話でよく使う略語が分からず、不安に感じたことはありませんか?
カルテや申し送りに登場する聞き慣れない言葉に戸惑い、「意味が分からないままで大丈夫かな」と心配になることもあるかと思います。
略語の意味を知らないままだと、情報の理解に時間がかかったり、重要な指示を見落としてしまう可能性があります。その結果、業務に対する自信を失ってしまうこともあるでしょう。
この記事を読むことで、略語に対する苦手意識がなくなり、明日からの業務に安心して取り組める自信がきっと持てるようになります。
なぜ看護の現場では医療略語をよく使うのか?
看護の現場で、略語が使われる主な理由は次の3つです。
- 業務の効率化
- 情報伝達の正確性の向上
- 患者さんへの配慮
新卒の看護師にとっては戸惑うこともありますが、略語が使われるのには明確な理由があります。以下で、それぞれの理由を詳しく説明します。
業務を効率化するため
看護の現場で略語が使われる大きな理由は、業務を効率化するためです。特に、一刻を争う場面や多忙な業務の中での情報共有において、時間短縮は非常に重要です。
カンファレンスや申し送りといった限られた時間の中で、これらの正式名称をすべて口頭で伝えていると、それだけで多くの時間を取られてしまうでしょう。
そこで、略語を用いることで素早く情報共有がされ、その分、患者さんのケアに時間を充てられるのです。
ただし、カルテ記載に関するルールは病院ごとに定められています。効率化のためとはいえ、まずは職場のルールを確認し、それに従って適切に使用しましょう。
看護師の業務で起こしやすいミスや対処法を知りたい方は「避けられない業務上の間違いはどうしたらいい?」看護師が起こしやすいミスや対処方法について」をご参照ください。
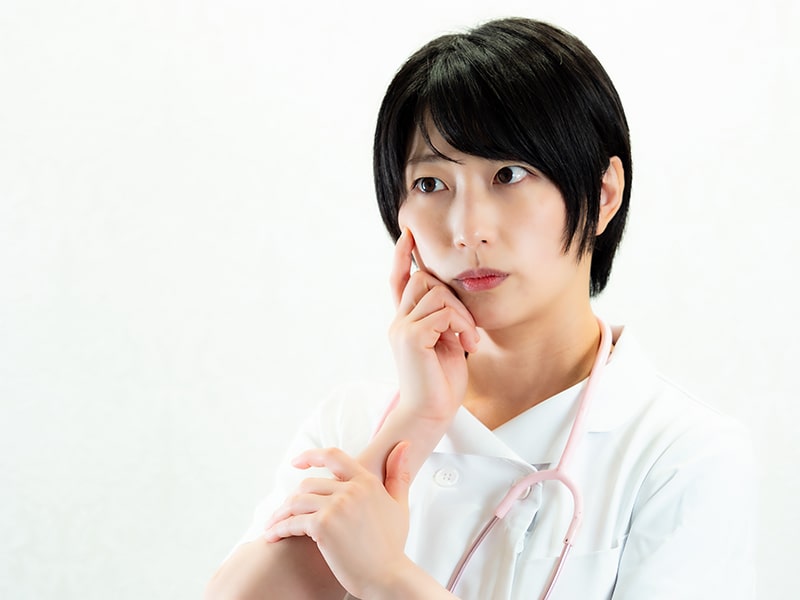
専門家同士で正確に情報を伝達するため
略語は、医療の専門家であるスタッフ同士が、迅速かつ正確に情報を共有するための共通言語として機能します。チームで患者さんのケアにあたる医療現場では、わずかな認識のズレが大きな事故につながりかねません。
共通の専門用語である略語を用いることで、こうしたコミュニケーションの食い違いを防ぎ、医療の質を高めます。
「DM」と聞けば、どのスタッフも「Diabetes Mellitus=糖尿病」のことだと瞬時に、正確な理解が可能です。しかし「血糖値が高い病気」のような曖昧な表現では、人によって解釈が異なってしまう恐れがあります。
医療従事者全員が同じ略語を同じ意味で理解することで、患者さんの状態や必要なケアに関する情報が共通認識されるのです。
これらの専門用語を正しく身につけることは、チーム全体のレベルアップにつながり、看護師として成長するためにも不可欠です。
【体験談】
臨床現場だけでなく、スキルアップのために参加する学会や院外の勉強会でも、講師は当たり前のように略語を使って解説を進めていきます。
話の途中で知らない略語が出てきてしまい、肝心な内容が頭に入ってこない経験がありました。
患者さんへ心理的に配慮するため
略語や専門用語は、患者さんやそのご家族の心情に配慮する目的でも使われます。病名や患者さんの状態を示す言葉の中には、ご本人が直接耳にすると、大きな不安や精神的ショックを受けてしまう可能性があるものが含まれます。
たとえば、患者さんの前で「癌」という言葉を直接的に使う代わりに、ドイツ語由来の「Ca」といった用語を用いる場合です。
これは、患者さんが自身の深刻な病状を不意に耳にして動揺するのを避けるための、医療従事者としての配慮になります。
ただし、最近ではインターネットで簡単に調べられるため、専門用語だからと油断せず、情報管理には常に注意を払いましょう。
【場面別】看護師が臨床でよく使う医療略語一覧
臨床現場で使われる略語は、疾患名から検査や処置、部署名まで多岐にわたります。これらを覚えておくと、医師の指示やカンファレンスの内容がスムーズに理解でき、業務の不安解消につながります。
ここでは、特に使用頻度の高い略語を5つの場面にわけて一覧で紹介します。まずは、よく遭遇する場面の略語から優先的に覚えましょう。
疾患名・症状に関する略語
患者さんの状態を把握し、報告する際に欠かせないのが疾患名や症状に関する略語です。
特に、心筋梗塞や脳血管障害といった緊急性の高い疾患や、糖尿病・高血圧などの慢性疾患に関する略語は、配属先にかかわらず頻繁に使われます。
| 略語 | 正式名称(英語・ドイツ語など) | 意味 |
|---|---|---|
| MI | Myocardial Infarction | 心筋梗塞 |
| SAH | Subarachnoid Hemorrhage | くも膜下出血 |
| HT | Hypertension | 高血圧 |
| DM | Diabetes Mellitus | 糖尿病 |
| COPD | Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 慢性閉塞性肺疾患 |
| CKD | Chronic Kidney Disease | 慢性腎臓病 |
| LC | Liver Cirrhosis | 肝硬変 |
| AP | Appendicitis | 虫垂炎 |
| CA | Cancer / Carcinoma | 癌 |
| DVT | Deep Vein Thrombosis | 深部静脈血栓症 |
疾患名・症状の略語は、患者さんの命に直結する重要な情報を伝える言葉でもあるため、正式名称と合わせて正確に覚えておくことをおすすめします。
検査・データに関する略語
日々の業務では、血液検査や画像検査など、さまざまな検査データをもとに患者さんの状態をアセスメントします。検査値や検査名に関する略語を理解することは、正確な看護実践につながります。
カルテに記載された「BS」の数値を見て、血糖値の変動を把握する場面は多いです。検査関連の略語を知っておけば、医師からの指示や検査結果の報告を迅速かつ正確に理解できます。
| 略語 | 正式名称(英語・ドイツ語など) | 意味 |
|---|---|---|
| VS | Vital Signs | バイタルサイン(体温・脈拍・血圧・呼吸) |
| BS/GLU | Blood Sugar / Glucose | 血糖値 |
| WBC | White Blood Cell | 白血球 |
| PLT | Platelet | 血小板 |
| Hb | Hemoglobin | ヘモグロビン |
| BUN | Blood Urea Nitrogen | 血中尿素窒素(腎機能の指標) |
| Cr | Creatinine | クレアチニン(腎機能の指標) |
| XP/X-P | X-ray Photograph | レントゲン写真 |
| ECG/EKG | Electrocardiogram | 心電図 |
| BGA | Blood Gas Analysis | 血液ガス分析 |
検査データは患者さんの状態を客観的に示す重要な情報のため、略語と基準値をセットで覚えると、異常の早期発見にもつながります。
処置・ケアに関する略語
看護師が日常的に行う処置やケアにも、たくさんの略語が使われます。医師からの指示受けや看護記録、申し送りなどで頻出するため、意味を正確に理解しておきましょう。
「IVから抗菌薬を開始」「明日、NPOでお願いします」といった指示を正しく理解できなければ、安全なケアを提供できません。
注射の種類や食事制限、心肺蘇生など、基本的な看護ケアに関する略語は、新人看護師や看護学生が最初に覚えるべき必須知識の一つです。
| 略語 | 正式名称(英語・ラテン語など) | 意味 |
|---|---|---|
| IV/DIV | Intravenous Injection / Drip Infusion in Vein | 静脈注射/点滴静注 |
| SC | Subcutaneous Injection | 皮下注射 |
| IM | Intramuscular Injection | 筋肉内注射 |
| NPO | Nil Per Os | 絶飲食 |
| CV | Central Vein / Central Venous | 中心静脈/中心静脈カテーテル |
| EN | Enteral Nutrition | 経腸栄養 |
| CPR | Cardiopulmonary Resuscitation | 心肺蘇生法 |
| DNR | Do Not Resuscitate | 蘇生措置拒否 |
| IC | Informed Consent | 説明と同意 |
聞き間違いや解釈ミスがないよう、自信がない時は必ず先輩や同僚に確認する習慣をつけましょう。
薬剤・物品に関する略語
治療で用いる薬剤や医療物品にも、よく使われる略語があります。特に点滴で使う基本的な輸液や、投与方法に関する略語は、安全な与薬のために必ず覚えておかなければなりません。
医師から「NS 500ml全開で」という指示が出た際に、「NS」が生理食塩水のことだと分からなければ、迅速に対応できません。
| 略語 | 正式名称(英語・ドイツ語など) | 意味 |
|---|---|---|
| NS | Normal Saline | 生理食塩水 |
| TZ | Zuckerlösung | ブドウ糖液 |
| PO | Per Os | 経口投与 |
| TPN/IVH | Total Parenteral Nutrition / Intravenous Hyperalimentation | 中心静脈栄養 |
| HOT | Home Oxygen Therapy | 在宅酸素療法 |
| PEG | Percutaneous Endoscopic Gastrostomy | 経皮内視鏡的胃瘻造設術 |
| PM | Pacemaker | ペースメーカー |
| NC | Nasal Cannula | 鼻カニューレ |
| PPE | Personal Protective Equipmen | 個人防護具(マスク、手袋、ガウンなど) |
正式名称と合わせて記憶し、安全な医療提供を心がけましょう。
部署・職種に関する略語
院内での円滑なコミュニケーションには、診療科や他職種を指す略語の知識も役立ちます。特に他部署への連絡や、チーム医療を実践するうえで知っておくと便利です。
「オルトのDr.にコンサルトしてください」「PTさんとリハビリの時間を調整して」といった会話は日常的に交わされます。
診療科の略語はドイツ語由来のものが多く、最初は戸惑うかもしれません。部署や職種を略語で呼ぶことは、医療現場ではごく一般的です。
| 略語 | 由来(英語・ドイツ語など) | 意味 |
|---|---|---|
| ギネ | Gynäkologie | 産婦人科 |
| オルト | Orthopädie | 整形外科 |
| ウロ | Urology | 泌尿器科 |
| デルマ | Dermatologie | 皮膚科 |
| アウゲ | Auge | 眼科 |
| PT | Physical Therapist | 理学療法士 |
| OT | Occupational Therapist | 作業療法士 |
| ST | Speech-Language-Hearing Therapist | 言語聴覚士 |
| MSW | Medical Social Worker | 医療ソーシャルワーカー |
| CE/ME | Clinical Engineer / Medical Engineer | 臨床工学技士 |
部署・職種の略語を知っていると、院内の誰がどんな役割を担っているのかを把握しやすくなり、スムーズな連携につながります。

\ インストールから登録まで5分! /
【要注意】調べても分かりにくい看護師特有の隠語・スラング
医療現場では、正式な略語以外にも、看護師の間で日常的に使われる特有の「隠語」や「スラング」が存在します。
これらは教科書や辞書には載っておらず、転職や異動の際に戸惑う原因になることがあるかもしれません。しかし、意味を知ればスタッフ間の会話がよりスムーズになります。
ここでは特に使用頻度の高い隠語・スラングを由来とともに紹介します。
「マンマ」「ウロ」など身体の部位を指す言葉
看護の現場では、身体の部位や関連する診療科を指す際に、ドイツ語由来の隠語が使われることがあります。これは、患者さんの前で直接的な表現を避け、心理的な負担を軽減するための配慮から定着した文化です。
たとえば「マンマ」は乳房を意味するドイツ語が由来で、乳がんの検査やケアに関する会話で使われます。最初は聞き慣れないかもしれませんが、これらの言葉は特定の診療科で特に頻繁に使われます。
| 隠語 | 由来(ドイツ語など) | 意味 |
|---|---|---|
| マンマ | Mamma | 乳房 |
| アウゲ | Auge | 眼 |
| デルマ | Dermatologie | 皮膚 |
| ガーレ | Galle | 胆嚢 |
| ウロ | Urology | 泌尿器(泌尿器科を指す場合も) |
配属先の隠語を覚えておくと、先輩や医師とのコミュニケーションが円滑になるでしょう。ただし、これらは口頭で使われることがほとんどで、正式な看護記録に記載することはないため注意しましょう。
「デコる」「ステる」など状態変化を表す言葉
患者さんの状態変化を表現する際に、独特の動詞のようなスラングが使われることがあります。これらは、深刻な状況を直接的すぎない言葉で、かつ迅速にスタッフ間で共有するために生まれました。
たとえば、心不全の状態が悪化することを「デコる(Decompensation)」、頻脈になっている状態を「タキる(Tachycardia)」のように表現します。
特に「ステる」は、患者さんが亡くなることを意味するドイツ語(Sterben)が由来の非常にデリケートな言葉です。
| スラング | 由来(英語・ドイツ語など) | 意味 |
|---|---|---|
| デコる | Decompensation | 心不全が増悪する |
| タキる | Tachycardia | 頻脈になる |
| アポる | Apoplexy | 脳卒中を起こす |
| ネクる | Necrosis | 組織が壊死する |
| ステる | Sterben | 亡くなる |
スラングは、意味を知っておくことは重要ですが、患者さんやご家族の前では絶対に使わず、使用場面には最大限の配慮が求められることを心に留めておきましょう。
「プンク」など処置に関する言葉
特定の医療処置や手技を指す際にも、効率化のために定着した隠語が使われます。多くはドイツ語が語源となっており、処置名を毎回正式名称で伝えずに済むため、スタッフ間の連携をスピーディーにします。
代表的な例が、穿刺を意味する「プンク(Punktion)」です。これは「腰椎穿刺(ルンバールプンク)」のように、具体的な処置名と組み合わせて使われます。
他にも、傷を縫い合わせることを「ナート(Naht)」、壊死した組織を取り除くことを「デブリ(Débridement)」と言います。
これらの言葉を覚えておくと、先輩看護師や医師からの指示が瞬時に理解でき、処置の準備や介助がスムーズに行えるようになるでしょう。
| 隠語 | 由来(ドイツ語・フランス語など) | 意味 |
|---|---|---|
| プンク | Punktion | 穿刺 |
| ナート | Naht | 縫合 |
| サクション | Suction | 吸引 |
| デブリ | Débridement | 壊死組織の除去 |
| ケモ | Chemotherapy | 化学療法 |
| ラジ | Radiation therapy | 放射線療法 |
処置で使用するスラングは、口頭での指示や申し送りで多く登場するため、聞き取れるようにしておくことが大切です。
看護師が略語を聞き取れない・分からない時の対処法
医師や先輩看護師の会話で知らない略語が出てきても、その場で質問しにくい場面は多いものです。しかし、分からないまま放置するのは医療安全の観点からとても危険です。
ここでは、略語が聞き取れない・分からない時に、その場で慌てず、後で確実に知識にできる具体的な4つの対処法を以下で紹介します。
- メモを取り、後で必ず調べる
- 文脈から意味を推測する
- 先輩や同僚に確認するタイミングを見計らう
- 電子カルテや過去の記録を参照する
まずは自分にできることから実践してみましょう。
メモを取り、後で必ず調べる
分からない略語に遭遇した際の基本的な対処法として、メモを取りましょう。緊急時やカンファレンスの最中など、会話を中断させて質問はできません。
そんな時でも、聞こえた音をカタカナで書き留めておくだけで、後で調べる手がかりになります。いつでも、メモを取れるようにポケットなどに準備しておきましょう。
業務が落ち着いたタイミングで、院内のマニュアルや信頼できる医療系サイト、書籍などを使って意味を調べます。
調べた略語を自分だけの「略語ノート」にまとめてリスト化しておくと、いつでも見返すことができ、知識が定着しやすくなります。
文脈から意味を推測する
会話の流れや状況から、知らない略語の意味を推測することも有効です。もちろん、推測だけで自己判断するのは危険ですが、話の全体像を把握するうえで役立ちます。
たとえば、呼吸状態が思わしくない患者さんのカンファレンスで「アテレク」という言葉が聞こえたら、「無気肺のことかもしれない」と関連付けて考えることができます。
同様に、消化器系の疾患を持つ患者さんの話で「アッペ」と出てくれば「虫垂炎だろう」と見当がつくでしょう。
患者さんの疾患や状態、行われている処置といった前後の情報と結びつけることで、知らない言葉でも意味を推測できる場面は意外と多いものです。
ただし、推測はあくまで一時的な理解にとどめ、後で必ず正しい意味を確認する習慣をつけましょう。
情報収集する際の基本項目や効率を知りたい方は「看護師が情報収集をする6つのコツと優先順位!基本項目や効率的な進め方も紹介」をご覧ください。

先輩や同僚に確認するタイミングを見計らう
自分で調べても分からない、または推測に自信が持てない場合は、先輩や同僚に質問することも有効な方法です。略語の誤った解釈は、医療ミスにつながる可能性があるため、決して自己判断で業務を進めてはいけません。
質問する際は、相手への配慮としてタイミングを見計らうことが大切です。緊急時や処置中で忙しい時を避け、業務が一段落した休憩時間やカンファレンスの後などに声をかけましょう。
電子カルテや過去の記録を参照する
人に聞きにくい時や自分で調べても確信が持てない場合は、電子カルテや過去の看護記録を参照するのも有効な方法です。カルテには、同じ疾患の患者さんや同じ処置が行われた際の記録が残っています。
略語がどのような文脈で使われているか、あるいは正式名称で記載されている場合もあり、意味を理解するうえで貴重な情報源です。
たとえば、先輩から「次のラパコレの患者さんの準備お願い」と指示された際に意味が分からなくても、過去の「ラパコレ」の記録を検索してみましょう。
すると、手術記録のページに「腹腔鏡下胆嚢摘出術」という正式名称が記載されており、術後の看護計画から具体的な処置内容を把握できます。
このように、過去の記録は実践的な知識が詰まっています。積極的に参照することで、略語の意味だけでなく、実際の看護場面と結びつけてより深く理解することができるでしょう。
看護師が略語を使い際の注意点
略語は業務効率化に役立つ一方、使い方を誤るとトラブルの原因にもなります。ここでは、看護師が略語を使用する際に特に注意すべき2つのポイントを解説します。
- 相手や状況によって意味が正しく伝わらない
- 患者さんには分かりやすい言葉で説明する
便利だからこそ、そのリスクを理解して、適切に使うことが重要です。
相手や状況によって意味が正しく伝わらない
略語が相手や状況によっては意図通りに伝わらず、うまく伝わらない可能性があることです。
医療現場で使われる略語には、一般社会で使われる言葉と同じものがあります。たとえば「DM」は、一般的には「ダイレクトメール」を指しますが、医療現場では「糖尿病(Diabetes Mellitus)」を意味します。
認識のズレは、医療知識のない人に限らず、その領域に精通していないスタッフ間でも起こり得ます。相手に合わせて正式名称を使ったり、補足説明を加えたりするなど、誰にでも正確に伝わるコミュニケーションを心がけましょう。
患者さんには分かりやすい言葉で説明する
患者さんやそのご家族への説明に、略語や専門用語をそのまま使わないことです。看護師は日常的に「禁食」や「安静」といった言葉を使うため、専門用語であるという意識が薄れがちです。
しかし、患者さんにとっては聞き慣れない言葉であり、意味を誤解してしまう恐れがあります。
「今日は禁食です」と伝えただけでは、「食事はダメだけど、ゼリー飲料くらいならいいだろう」と患者さんが独自に解釈してしまうかもしれません。
説明不足を防ぐには、「夜9時以降は、お食事もお水も口にしないでくださいね」というように、誰が聞いても分かる具体的な言葉に置き換えましょう。
看護師が良く使う略語に関するよくある質問
ここでは、看護師が略語を使ううえで特に疑問に思いやすい点について、分かりやすく解説します。まずは、看護記録における略語の扱いの基本から見ていきましょう。
看護記録で略語がダメな理由はなぜですか?
看護記録は、誰が読んでも正確に理解できる「公的な文書」だからです。看護記録は、院内の他職種スタッフはもちろん、転院先の病院も閲覧します。さらには情報開示によって患者さん本人や家族が目にする可能性があります。
その部署だけで通用する略語では、他の人には意味が伝わらず、継続的なケアに支障をきたす恐れがあるのです。また、万が一医療訴訟に発展した場合、看護記録は法的な証拠として扱われます。
意味が曖昧な略語は解釈の食い違いを生む原因となるため、記録としての客観性や信頼性を損なってしまいます。
看護記録で書いてはいけないことは何ですか?
看護記録には、客観的な事実以外のことを書くべきではありません。
具体的には、以下になります。
- 個人の感情や憶測
- 人権を侵害する差別的な言葉
- 医療者が優位に立つような表現
看護記録は、法的な証拠にもなり得る公的な文書です。そのため、記録には客観性と倫理的な配慮が求められます。たとえば、「不機嫌そう」といった主観的な解釈ではなく「声かけに返答がない」という観察した事実を記載します。
また、「ボケ」などの差別用語や、「〜させる」といった高圧的な表現は、患者さんの尊厳を傷つけるため不適切です。
看護記録を作成する際は、常に客観的な事実に基づき、患者さん一人ひとりへの配慮を忘れない姿勢が大切になります。
まとめ|よく使う看護師の略語をマスターして業務の不安を解消しよう
看護現場で使われる略語を正しく理解することは、業務の効率化やチーム内の円滑な情報伝達に重要であり、医療安全の向上に直結します。
まずは、疾患名や処置といった使用場面別の基本的な略語から覚え、徐々に知識を広げていきましょう。
また、もし分からない略語に遭遇した場合は、安易に推測せず、メモを取って後で調べ、タイミングを見計らって先輩に.確認することが大切です。
日々の業務の中で一つひとつ着実に身につけていくことが、コミュニケーションへの不安を解消し、自信を持って看護を実践するための第一歩となります。
本記事で学んだ知識を、ぜひ明日からの臨床現場で活かしてください。
カイテクは、「近所で気軽に働ける!」看護単発バイトアプリです。
- 「約5分」で給与GET!
- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!
- 働きながらポイントがザクザク溜まる!
27万人以上の看護師などの有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /







