ジャンル別記事
ダメな施設長の9つの特徴とは?危険なブラック介護施設の見分け方を徹底解説!
ダメな施設長やブラックな介護施設は、社員の意見を受け入れなかったり、現場を知らずに何か主張したりします。
現場に負担がいき、スタッフ間のコミュニケーションのトラブルにつながってしまいます…忙しくなることで、利用者にも良質なサービスを届けられずに落ち込んでしまうスタッフもなかにはいるでしょう。
自分に合った施設を見つけたい方は、カイテクを使ってみるのがおすすめです。履歴書・面接なしで最短1時間から単発バイトで働けます。自分が希望する施設があれば転職意欲を伝えられるので、ぜひ試してみてください。
ここが不満!ダメな施設長の9つの特徴

ダメな施設長の特徴を知ることで、職場を選ぶときや今の職場がどうなのかを判断できます。あなたの時間を奪う存在にもなるので参考にし、気をつけてみてください。
- 介護現場の業務を理解していない
- 現場をまとめる決断力がない
- 怒ったり前とは違う発言をしたり気分で仕事をしている
- 問題を放置して人間関係のトラブルを見て見ぬふりする
- ハラスメント行員や暴言を容認・黙認している
- 利用者や家族への対応が雑
- 上層部の意向に従うばかりで現場を守らない
- 職員の労働環境・健康管理に無関心
- 現場改善や職員育成への意欲が見られない
介護現場の業務を理解していない
介護現場を理解できていない施設長は危険です。別の業種から転職してきて施設長になっている場合は、介護現場のことや高齢者のことを理解できておらず、極端に利益のことばかり考えている方がいます。
例えば、理想論を掲げて、それを無理やり共有してくるような方です。
現場を知らない理事長の意見しか取り入れずに、スタッフの意見を無視したような目標を立てる人もいます。
介護職も理想を持って仕事に取り組んでいますが、現場の状況を理解しないで、言葉ばかり気持ちのいいことを言っている施設長は気をつけましょう。
現場をまとめる決断力がない
施設長は時に舵を取り、決断をしなくてはいけません。ダメな施設長は、決断ができずに問題をうやむやにしている方がいます…特に人間関係でのトラブルはスタッフの定着率にも関わる問題です。
それなのに見て見ぬふりをしたり、スタッフからの相談を受け流したりしている施設長は信頼を得られません。施設長にはリーダーシップを持って、改善に向けた前進する力が大切です。
怒ったり前とは違う発言をしたり気分で仕事をしている
施設長の機嫌でスタッフを怒ったり、前回の会議と違うことを言い出したりするダメな施設長もいます。
施設長が気分で仕事をすることによって現場の雰囲気も悪くなり、利用者にも伝わってしまうことがあるでしょう。そしてスタッフが利用者に向き合える環境ではなくなってしまうため、いいケアができなくなってしまいます。
心身ともに疲弊する原因になるので、距離を置くか早めに転職をするのがおすすめです。
問題を放置して人間関係のトラブルを見て見ぬふりする
介護現場では、職員同士の人間関係が業務に大きく影響します。ダメな施設長は、スタッフ間で明らかにトラブルが発生していても、「現場の問題は現場で解決して」と放置してしまう傾向があります。
このような対応は、いじめやパワハラを助長し、職場の雰囲気を悪化させる原因になりかねません。信頼関係が崩れると、報告・連絡・相談が機能せず、利用者へのケアの質にも影響します。
施設長には、職員の変化やSOSに敏感であることが求められます。状況を的確に把握し、早期に仲裁や対応を行う姿勢が、健全なチームづくりの鍵です。
ハラスメント行為や暴言を容認・黙認している
職員に対するパワハラや暴言が日常化しているにもかかわらず、ダメな施設長がそれを見て見ぬふりする環境では、安心して働くことはできません。たとえ加害者がベテラン職員であっても、施設長は毅然と対応しなければなりません。
ハラスメントを容認する姿勢は、組織の信頼を損ね、若手や新規職員の離職を加速させます。また、利用者や家族に対する不適切な発言も、放置すれば施設全体の評価に直結します。
介護現場での「言葉の暴力」は、職員の心に深く傷を残すものです。トップの態度が、職場全体の安全文化を左右することを忘れてはなりません。

利用者や家族への対応が雑
ダメな施設長のなかには、利用者やその家族との対応を形式的に済ませたり、相談やクレームに対して適当にあしらう人もいます。介護サービスは、信頼関係の上に成り立っており、施設長の姿勢ひとつで家族の安心感が大きく変わります。
例えば、家族からの要望や不安の声に耳を傾けず、「うちはこういう方針なので」と一方的に話を打ち切る対応では、苦情やトラブルの火種になります。
施設長が現場職員と連携しながら、丁寧に状況説明や謝意を伝えることで、信頼を積み重ねることができます。
上層部の意向に従うばかりで現場を守らない
法人本部や経営層の方針が現場にそぐわないとき、施設長には現場側の立場に立って調整する役割が求められます。しかし、ダメな施設長は「本部が言っているから」と言って、現場の意見や負担を無視しがちです。
このような姿勢は、職員のモチベーションを下げ、組織内に不信感を生みます。
例えば、無理な人員配置や突然のルール変更を一方的に進めるケースがそれにあたります。
良い施設長は、上層部と現場の“橋渡し役”として両者の声を調整し、現場の声を代弁する責任を果たします。
職員の労働環境・健康管理に無関心
人手不足の介護業界において、職員のメンタルや体調への配慮は非常に重要です。しかし、ダメな施設長は「忙しいのは皆一緒」「気合で乗り切って」と言い放ち、職員の不調を軽視しがちです。
結果、過重労働による体調不良や、精神的な疲弊からの退職が相次ぐことになります。有給取得率の低さ、シフトの偏り、深夜明けの連勤などを見直さない姿勢は、職場の持続可能性を損ないます。
職員の状態を日常的に観察し、休息・相談のタイミングを見逃さないことが、施設長には必要です。
現場改善や職員育成への意欲が見られない
施設の運営は、日々の改善と人材育成の積み重ねで成り立っています。しかし、ダメな施設長は業務改善や教育体制の整備に関心を示さず、場当たり的な対応でやり過ごそうとする傾向があります。
新しい職員に十分なOJTが提供されなかったり、マニュアルが整備されていなかったりすると、スタッフの不安や負担は増す一方です。加えて、「前からこうだから」「余計なことをするな」といった姿勢は、現場の成長を阻害します。
変化を恐れず、スタッフが提案しやすい風土を作ることが、真に求められるリーダー像です。
なぜダメな施設長が生まれてしまうのか
介護業界で「ダメな施設長」とされる人が一定数存在する背景には、個人の資質だけでなく、制度的・構造的な問題が複雑に絡み合っています。以下では、ダメな施設長が生まれてしまう3つの理由を紹介します。
人材不足で現場経験の少ない人が登用されている
介護業界は深刻な人手不足に悩まされており、厚生労働省の推計では2040年に約280万人の介護職員が必要とされています。現場が人手で回らない状況では、管理職にふさわしい人材を十分に育成する余裕もなく、結果として介護経験が少ない人が施設長に抜擢される例が後を絶ちません。
その結果、現場職員から見れば「何もわかっていない上司・ダメな施設長」と映り、不信感が募る要因となります。
法人内の人事評価・昇格制度が機能していない
施設長の選定プロセスに問題があるケースも多く存在します。
例えば、中小規模の法人や地方施設では、明確な評価制度が整っていないことも多く、「とりあえず長く勤めている人」「前任者の推薦があったから」といった理由で施設長が決まることも少なくありません。
こうした環境では、以下のような事態が起こりやすくなります。
- 管理者としての研修や教育が不十分なまま就任
- 上司の顔色をうかがい、現場の声を軽視
- 問題が起きても「見て見ぬふり」で済ませてしまう
職員にとっては、能力よりも年功や関係性で昇進する姿を見て、やる気を失う原因にもなります。
制度上、施設長に必須資格がないケースもある
施設長という肩書から、特別な資格が必要と誤解されがちですが、実際には施設の種別によっては無資格でも就任が可能です。
| 施設種別 | 資格要件 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 国家資格は不要 |
| グループホーム | 介護支援専門員でなくてもOK |
| 民間施設 | 経営母体の方針によっては無資格可 |
この制度的な「緩さ」により、介護・福祉に関する専門性がない人が経営重視で施設長に就くケースもあり、現場との乖離を生む大きな要因となっています。


\ インストールから登録まで5分! /
ダメな施設長とどう向き合う?介護職としてできる対処法
すべての施設長が理想的なリーダーであるとは限らず、中には現場の声を十分に汲み取れない、あるいは適切な判断を下せないケースも見受けられます。そのような状況下で、介護職員としてどのように対処すべきかを考えてみましょう。
- 現場の信頼できるスタッフと共有する
- 感情的に対立せずに冷静に距離を取る
- 職場改善の提案を仲間と協力して行う
- 自分がまきこまれないよう「報連相」を記録して残す
- 法人本部・上位機関へ適切に相談する
- 改善が見込めないなら転職も視野に入れる
現場の信頼できるスタッフと共有する
まず、同僚や信頼できるスタッフと現状を共有しましょう。1人で悩むと視野が狭くなりがちですが、他のスタッフと情報を共有することで、問題の全体像が明確になります。
また、同じ悩みを持つ仲間がいることで、精神的な支えにもなります。
- 現状の整理
- 信頼できる同様との共有
- 情報の集約
このプロセスを通じて、問題が個人的なものなのか、組織全体の課題なのかを判断する材料が得られます。
感情的に対立せずに冷静に距離を取る
ダメな施設長に対して不満や怒りを感じる場面は、介護現場では少なくありません。しかし、正面から感情的にぶつかってしまうと、状況は悪化し、かえって自分が評価を下げるリスクもあります。
特に上下関係があるなかでの言い合いや対立は、精神的なストレスも大きく、職場の雰囲気を悪くしてしまいがちです。そうしたときは、無理に関係性を改善しようとせず、必要最低限の業務連携だけを保ち、心理的距離を確保するのが現実的な対応です。
施設長に過度な期待をせず、割り切って接することで、自分のペースとメンタルを守ることにつながります。
職場改善の提案を仲間と協力して行う
施設長に不満があるとき、1人で意見を伝えるのは精神的なハードルが高いものです。そんなときは、同じような問題意識を持つ仲間と協力し、複数人で改善提案をまとめて提出するのが効果的です。
例えば、シフトの不公平感や人間関係の問題、利用者対応のルール改善など、現場で起きている課題を「提案書」や「ミーティング」で共有する形で届けましょう。
個人の愚痴ではなく、組織全体にとっての改善提案として示すことで、施設長側の受け取り方も変わります。建設的な姿勢を見せることが、自分自身の信頼にもつながります。
自分が巻き込まれないよう「報連相」を記録して残す
ダメな施設長ほど、過去の発言を覚えていなかったり、「そんなことは言っていない」と話をひっくり返したりすることがあります。そのような職場では、「言った・言わない」のトラブルに巻き込まれないよう、報告・連絡・相談(報連相)は必ず記録に残す習慣が重要です。
日報や業務連絡のメモ、LINEやメールなど、内容が確認できる形で残しておけば、いざというときに自分の立場を守る証拠になります。また、相談や意見を伝えた際も「○月○日にお伝えしました」と振り返れるようにしておくと安心です。記録は、自己防衛だけでなく、現場の透明性を保つ意味でも有効です。
法人本部・上位機関へ適切に相談する
現場での共有だけでは解決が難しい場合、法人本部や上位機関への相談を検討します。ただし、感情的な訴えではなく、客観的な事実と具体的な事例をもとに伝えることが重要です。
相談時のポイントは以下のとおりです。
- 事実の記録:問題行動に関して日時や内容を詳細に記録
- 影響の明示:業務や利用者にどのような影響を与えているか示す
- 改善提案:具体的な改善策や提案を併せて伝える
このように、冷静かつ建設的なアプローチを取ることで、上位機関も真剣に対応を検討しやすくなります。ダメな施設長に悩む方は、ポイントを押さえたうえで機関へ相談するようにしましょう。
改善が見込めないなら転職も視野に入れる
上記の対処法を試みても状況が改善されない場合、自身のキャリアや精神的健康を守るために転職を考えることも1つの選択肢です。無理に現状に留まることで、ストレスやバーンアウトのリスクが高まる可能性があります。
転職は大きな決断ですが、長期的なキャリアや生活の質を考慮すると、前向きな選択となる場合もあります。以上の対処法を参考に、冷静かつ計画的に行動することで、より良い職場環境を築く一助となるでしょう。
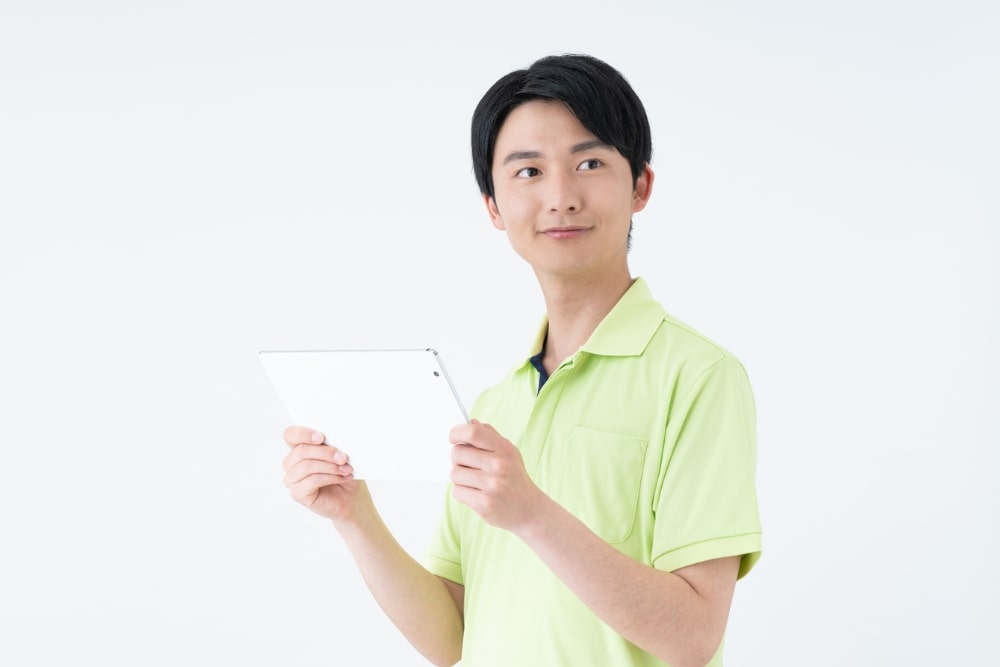
気をつけよう!ダメな施設長がいるブラック施設の特徴

ダメな施設長がいると、ブラックな施設になってしまいます。健全な目標がなくスタッフが働く意欲を失っていたり、その態度が利用者に移ったりし、不適切なケアにつながっていたりする可能性があるためです。
ここからは危険な施設を見分ける方法を紹介します。労働力や時間を無駄にしないためにも、ぜひ参考にしてみてください。
労働環境が悪い
ブラックな環境の1つに、労働環境が悪いことが挙げられます。
- 残業代が出ない
- 残業が極端に多い
- 休日出勤をさせられる
- 有給が取れない
夜勤が3日間続いたり、長時間労働が当たり前になっていたりする現場は危険です。
ブラックな施設には労働時間が長いにもかかわらず、給与が少ない施設もあります。労働環境が悪いということは、スタッフや利用者のことを大切に思っていないのと同じ意味です。
利用者からの被害がある
利用者からの被害を放置している職場はブラック施設です。
例えば、セクハラ行為が常態化していたり、暴力被害が出ていたりする状態は、ブラック施設であり、ダメな施設長がいる可能性が非常に高いです。
残念ながら、スタッフがセクハラ行為を受けてしまう事態はどの施設でも多発しています。厚生労働省も介護人材の確保は課題と考えており、ハラスメントが起きた場合には必要な措置を講じることを求めています。
それにもかかわらず、何も対策をしていない場合は認識の低い施設です。スタッフが施設長や上司に訴えても改善の余地がない場合は、転職も考えましょう。
人間関係が悪い
人材の入れ替わりが激しかったり、スタッフ間で悪口を言い合っていたりする施設は、人間関係に問題を抱えている可能性が高いです。
さらに介護は他職種との連携が不可欠ですが、看護師と介護職の仲が悪くコミュニケーションが取れていないために、利用者への対応が変わってしまっている施設は危険です。
人間関係のトラブルが利用者にまで影響してしまっている状況はブラック施設といえるでしょう。
見学時に見分ける!人が辞めにくい良い施設の特徴とは

ブラックな施設を避けるには就職する前に見学に行くことをおすすめします。施設の雰囲気やスタッフ・施設長の様子がわかるためです。
ここからは見学時に良い施設を見分ける方法を解説します。
スタッフが挨拶をする
施設を訪れたときには、スタッフや現場の雰囲気を確認してみてください。スタッフが挨拶をして利用者にも笑顔で接している現場は良い施設の可能性があります。
スタッフが無言で仕事をしていたり、利用者の表情が暗かったりする施設は要注意です。
人間関係が良好であれば、現場の雰囲気も明るいでしょう。その1つの目安としてスタッフが挨拶をするというのは大切なポイントです。
施設が綺麗に掃除されている
施設全体の様子も見てみてください。綺麗に整理整頓されていて、物品も補充されている施設はおすすめです。なぜなら細かい部分まで気を配る余裕があるからです。
ブラック施設では常に人材不足なため、細かい部分まで気を遣う余裕がない可能性があります。
いい施設はスタッフの定着率も高いので、現場の清潔感を保つ余裕があり、施設が綺麗になっています。
良い面も悪い面も伝えてくれる
施設の良い面だけでなく、現状の問題点なども伝えてくれているか確認しましょう。問題点に対してどのように取り組み、どう対応していくかを一緒に考えていく姿勢であれば、スタッフの意見を大切にしてくれています。
報酬や休みについて伝えたら即日に内定が出たり、採用を急いでいたりする施設は注意が必要です。
もし施設の悪い面を話していないと感じたら、こちらから質問しましょう。聞きづらいかもしれませんが、良い施設なのか、ダメな施設長はいないのかを見分けるためには重要です。
スタッフの離職率や利用者の満足度などを誠実に答えてくれるか聞いておきましょう。
口コミやSNSでも評判がいい
最近では口コミやSNSで評判がいい施設がわかります。見学に行った人の意見は客観的な視点なため、参考になるでしょう。またSNSで発信している施設は見学に行くのをおすすめします。口コミや評判も集まりやすく、本当に人気のある施設かがわかりやすいからです。
新しいことを取り入れる風土もあるので、スタッフの意見に耳を傾けてくれる可能性もあります。TwitterやInstagramで確認し、足を運んでみてください。

理想の施設長に共通する特徴とは
ダメな施設長に特徴があるように、職員や利用者、利用者家族が思う理想の施設長にも共通する特徴があります。以下では、4つの特徴について紹介するので、職場の施設長や、これから勤務する施設の方に当てはまるかチェックしてみましょう。
現場経験を理解し、職員の声を聞く姿勢がある
理想的な施設長は、介護現場の大変さや業務負担を理解したうえで職員と接します。実際に介護職としての経験があるかどうかに関わらず、記録業務の煩雑さ、身体介助の負荷、人手不足の苦しさなど、現場が抱える課題に共感しようとする姿勢が大切です。
加えて、職員一人ひとりの声に耳を傾け、「どんな支援があればもっと働きやすいか」といった対話を重ねることで、信頼関係が生まれます。頭ごなしの指示ではなく、現場の視点に寄り添った提案や改善策を一緒に考えてくれる施設長は、スタッフのやる気と定着率を高める存在です。
組織全体を俯瞰しつつも現場と連携できる
施設長には、職員の業務状況だけでなく、利用者・家族の満足度、収支や人材配置など、施設全体を見渡す視野が求められます。しかし、理想的なのは、ただの「管理者」にとどまらず、現場の職員と一緒に動ける柔軟性を持つ人です。
例えば、急な欠勤で人手が足りないときに手伝ってくれたり、新人教育に積極的に関わったりする施設長は、職員からの信頼が厚くなります。
トップが現場を理解し、必要に応じて自らサポートする姿勢を見せることで、施設全体の一体感が生まれ、チーム力の強化にもつながります。
怒らず・押し付けず・支えるリーダーシップがある
怒鳴ったり威圧的な言動で職員を動かすダメな施設長は、短期的には従わせることができても、長期的には信頼を失います。理想の施設長は、指示や注意をする際も冷静で落ち着いた態度を保ち、職員の立場に立った説明や助言を行う人です。
ミスがあっても頭ごなしに責めるのではなく、「どうすれば防げたか」を一緒に考える姿勢が、職員の成長を促します。また、業務の押しつけではなく、困っている人を見逃さず支えるリーダーシップは、現場に安心感と尊敬の気持ちを生みます。
感情ではなく信念で導く姿が、理想的なトップ像です。
スタッフや利用者に誠実な対応を続けている
理想的な施設長は、どんな立場の人に対しても誠実な態度を崩さず、信頼を積み重ねる人です。スタッフには感謝と労いの言葉を忘れず、悩みにも耳を傾けて対応します。
利用者やそのご家族に対しても、丁寧に説明を行い、不安や疑問には真摯に向き合います。たとえ忙しい中でも、「話を聞いてくれる」「対応が丁寧」と感じられる振る舞いを積み重ねることで、施設全体に安心感が広がるでしょう。
不都合なことが起きたときも隠さずに説明し、責任を持って対応する姿勢は、信頼されるリーダーに不可欠な資質です。
理想の施設長を見極める面接の質問例
介護施設での面接は、施設の雰囲気や運営方針を知る絶好の機会です。特に施設長の考え方や姿勢を理解することで、働きやすい環境かどうかを判断できます。
以下に、理想の施設長を見極めるための具体的な質問例を紹介します。
「職員の定着率」について尋ねてみる
職員の定着率は、職場環境や人間関係、労働条件などを反映する重要な指標です。高い定着率は、スタッフが長く働き続けられる環境が整っていることを示します。面接時に以下のように質問してみましょう。
「こちらの施設では、職員の平均勤続年数や定着率はどのくらいでしょうか?」
具体的な数値や、定着率を向上させるための取り組みが示されると、施設が職員の働きやすさを重視していることがわかります。定着率が低い場合、その理由や改善策についても尋ねると、施設の課題や対応策を知る手がかりになります。
「どんな職員を評価しているか」を聞く
施設がどのような基準で職員を評価しているかを知ることで、自身の働き方や価値観がマッチするかを判断できます。以下のように質問してみてください。
「御施設では、どのような姿勢やスキルを持った職員が高く評価されていますか?」
具体的な評価基準や、評価に基づく昇進・昇給の仕組みが説明されると、施設が職員の成長をどの程度支援しているかが理解できます。評価基準が曖昧な場合、働く上でのモチベーションやキャリアパスに影響を及ぼす可能性があるため、詳細を確認することが重要です。
「課題と改善策」について素直に聞く
施設が現在直面している課題や、それに対する改善策を尋ねることで、施設の運営状況や将来性を把握できます。以下の質問を試してみましょう。
「現在、施設が直面している課題と、その解決に向けた取り組みについて教えていただけますか?」
具体的な課題と、それに対する明確な改善策が示されると、施設が問題解決に積極的であることがわかります。課題に対する取り組みが不明確な場合、施設の将来性や安定性に不安を感じる要因となるため、深掘りして確認することが望ましいです。
ダメな施設長や施設がいたら転職を考えよう
ダメな施設長やブラックな施設に長くいることは、スタッフにとってメリットがありません。人間関係に悩み、体調を崩したりハラスメントを受けたりして介護に対する不信感が募り仕事を辞めてしまう方もいます。
既に労働環境が悪く、転職などを検討されている方には「カイテク」がおすすめです。
カイテクは面接なし・給与即金の介護単発バイトアプリです。
現在、100,000人以上の介護士、介護福祉士など介護の有資格者が登録
- 面倒な手続き不要:面接・履歴書無し!
- 給与は最短当日にGET:アプリで申請・口座に振込!
- 転職にも利用できる:実際に働いて相性を確認!
- 専門職としてスキルアップ:様々なサービス種類を経験!

\ インストールから登録まで5分! /







