ジャンル別記事
障害者グループホームでのあるあるトラブル6選|トラブル発生時の対処法も解説
「障害者グループホームであるあるのトラブルを知りたい」と考える方も多いでしょう。
利用者や職員が直面しやすい問題とその解決方法を解説するので、実際に働き始めても焦らず対応できるはずです。また、自身の心身を守るうえでも役立つ内容のため、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
障害者グループホームで利用者が引き起こすあるあるトラブル4選
障害者グループホームで利用者が引き起こすあるあるトラブルは以下のとおりです。
障害者グループホームは一軒家で運営されていることが多いため、行方不明や騒音トラブルが起こりやすいです。
このような問題がなぜ発生するかを知ることは、障害者グループホームで働くうえでは大切なので、ぜひ確認してみてください。
行方不明や無断外出
障害者グループホームでは、利用者の行方不明や無断外出といったトラブルが発生することがあります。なぜなら、軽度の障がいがある方は、事前に職員へ申請すれば外出が認められる場合があるからです。
さらに、一軒家をリフォームしただけの施設もあり、厳重な施錠が難しいケースもあります。そのため、美容室へ出かけた利用者が迷子になったり、夜間に施設を抜け出してしまったりするケースも見られます。
長野県健康福祉部障害者支援課の調査によると、行方不明の事故は13件発生しています。
| 種別 | 行方不明の事故数 |
|---|---|
| 障害者支援施設 | 4件 |
| 共同生活援助 | 5件 |
| 就労サービス | 1件 |
| 障がい児入所・通所施設 | 2件 |
| その他 | 0件 |
このように、障害者グループホームは玄関から出やすい構造のため、行方不明や無断外出のトラブルが発生しやすいのです。
参考:長野県健康福祉部障害者支援課「障害福祉サービス事業所等における事故等の状況」
騒音や大声
騒音や大声などによるトラブルも頻繁に発生する事案です。
共用部分と隣接する家が近いとテレビの音量や話し声が漏れて、地域住民から苦情が来るケースも珍しくありません。近隣からクレームが寄せられると、障害者グループホームが周囲のコミュニティに悪い印象を与えてしまいます。
地域と協力体制を築くためにも、吸音材や防音パネルの設置、利用者との対話などを通じて、騒音問題に適切に対処する必要があります。
他の利用者や職員への暴力・暴言
障害者は感情のコントロールが難しい方が多いので、暴力や暴言を発することがあります。
そのため、レクリエーションの勝敗にこだわりすぎるあまり、他の利用者とケンカをしてしまうケースもあります。利用者だけでなく職員まで殴ってしまい、怪我をしてしまうこともあるので注意が必要です。
生活リズムの乱れによる問題
利用者の生活リズムが乱れることで、トラブルが発生することがあります。障害者グループホームの生活はスケジュールが固定されているため、環境の変化が苦手な方にとっては、適応するまでに時間がかかることがあります。
生活リズムが整うまでは、症状の悪化や心身の不調を引き起こすこともあるでしょう。その結果、不眠や暴力行為につながることも少なくありません。
障害者グループホームで職員が引き起こすあるあるトラブル2選
障害者グループホームの職員が引き起こすトラブルのあるあるを2つ紹介します。
虐待や窃盗は多くの施設で発生している事案なので、これから働きたいと考えている方は状況を知っておきましょう。
虐待をする
障害者グループホームでは、利用者に暴力を振るったり暴言を吐いたりなどをしている世話人や職員がいます。厚生労働省によると、4,346件の事実確認調査のなかから1,022件の虐待が認められています。
利用者に対しての虐待は、職員が引き起こすトラブルの1つといえます。
窃盗をする
近年では、世話人が窃盗をする事件が発生しています。
容疑者は70代の男性入居者のキャッシュカードで、現金約100万円以上を引き出した疑いが持たれています。「生活にゆとりが欲しくてやった」都容疑を認めており、警察は慎重に調査を進めています。
障害者グループホームでは利用者に代わり、職員が銀行に行くこともあります。そのため、職員による窃盗が起こる可能性もあるのです。
トラブルを避けて働きたい方や、ほかの職場も経験してみたい方は、カイテクを使ってみるのがおすすめです。スキマ時間を活用して単発バイトができるため、お金を稼ぎつつ、経験を積むことができます。
以下は、カイテク利用者のKさんへのインタビュー内容です。
Q:Kさんがカイテクを使い始めるきっかけから教えていただけますか。
A:すきま時間を使って働きたいと思っていたところ、単発バイトのアプリを利用したことがある友人から「空いている時間を活用できて楽しいよ」と聞いて、私もやってみようと。
実はカイテクに登録する前から他の単発バイトアプリを使っていました。
その頃はデイサービスの施設でパートとして働いていたのですが、自分の将来が見えなくなっていた時期でした。違うところにも行ってみたいなと感じ始めていたんです。
正社員の中にも休みの日には勉強を兼ねてカイテクを利用している人や、介護仲間が集まる会でもカイテクを使っている人がいたんです。
いろいろな施設に行っているという話を聞いて、楽しそうやなと思っていました。
それで思い切って登録して使い始めてみたら「自分に合った働き方ができる」と感じて、今ではカイテク1本で仕事をしています。カイテクで働き出してから、もう半年以上が経ちました。
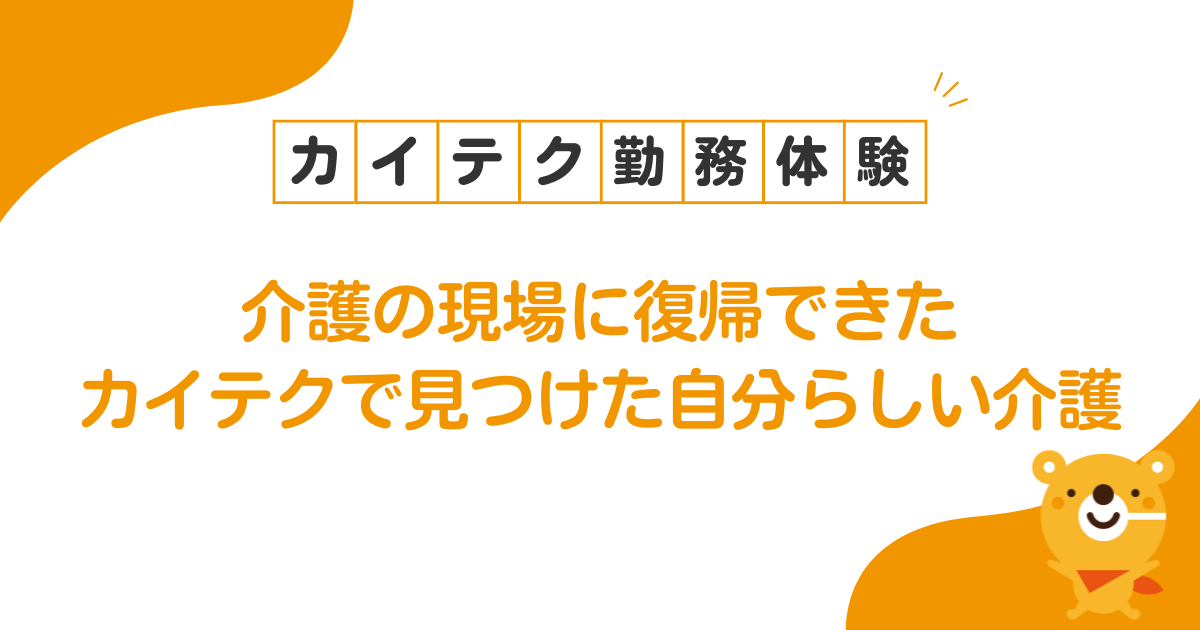

\ インストールから登録まで5分! /
障害者グループホームで利用者が引き起こしたトラブルへの未然対策
障害者グループホームで利用者が引き起こしやすいトラブルへの未然対策は以下のとおりです。
未然対策を知っておくことで、障害者グループホームに勤めても不安なく働けます。
緊急時の対応方法を明確にする
障害者グループホームで発生するトラブルに備え、緊急時の対応方法を明確にしておきましょう。そうすることで、トラブルが発生しても迅速に対応でき、利用者の安全を確保するだけでなく、職員や現場の負担も軽減できます。
たとえば、利用者が行方不明になった際に対応方法が不明確だと、職員は適切な対応が取れません。
その結果、対応が遅れ、利用者を安全に発見できなくなる可能性があります。
問題が深刻化する前に対処できるよう、行方不明を確認したら、警察やサービス管理責任者へ速やかに連絡するルールを定めておきましょう。緊急時の対応方法を明確にしておくことは、利用者の安全を守るためにも重要です。
定期的に会議を実施する
職員やサービス管理責任者が定期的に会議を開き、職員の状況を把握することが大切です。
そのため、会議を開くことで「AさんはBさんとトラブルがあった」「Cさんは最近、徘徊が増えている」といった利用者の状況を職員間で共有できるでしょう。
その結果、トラブルの兆候を放置せず、未然に対策を講じることができます。最低でも月に1回は会議を開き、現場の状況を把握しましょう。
利用者の気持ちや状況に寄り添う
精神障がいや知的障がいの影響で気持ちの変化が激しくなる方もいるため、職員は利用者の心身に寄り添うことが求められます。
上手く話せない方の場合には、丁寧な傾聴や他職種と連携して情報を集めることがポイントです。このように障害者グループホームで働く世話人や職員には、利用者の気持ちや状況に寄り添う力が必要なのです。
障害者グループホームの世話人が引き起こすトラブルへの未然対策
障害者グループホームの世話人が引き起こすトラブルへの未然対策は以下のとおりです。
虐待や窃盗などは裁判になり、損害賠償や懲役刑など、職員の人生を大きく破綻させてしまうことがあります。そのような事態を防ぐためにも、現場では未然に防ぐ努力が求められるのです。
職員の心身状況を認識する
職員が今何を感じて仕事をしているのかを確認しておくことが大切です。
問題が起こる前から定期的な1on1やアンケートを実施して、職員の心身状況を認識しておきましょう。職員の心身ケアは、問題が起こる前に対策をしておくことが重要です。
研修や勉強会を開催する
研修や勉強会を開催することも、トラブルを未然に防ぐうえでは大切です。世話人が障がいへの理解を深めることで、職員目線だけでなく利用者目線に立って物事を判断できるようになるからです。
研修や勉強会では障がいの症状や特性について学べるので、利用者が今何を感じているのか、どのような対応が適切かを判断できるようになります。
その結果、あらゆる状況でも冷静に対応できる力が身に付くので、定期的に研修や勉強を開催することは重要です。
資格を取得する
資格を取得することで、利用者に対してイライラしたり怒ったりすることが減ります。なぜなら、資格の勉強を通じて、障害者への専門的な対応方法を学べるからです。
たとえば、障害者グループホームでは、強度行動障がいの方のケースが挙げられます。
強度行動障がいとは、他人を叩いたり、食べられない物を口に入れたりするなど、日常生活に影響を及ぼす行動が見られる障がいです。
このような方を適切に支援するためには、「強度行動支援者養成研修」と呼ばれる資格の取得が有効です。この研修を修了することで、強度行動障がいに対する支援技術や特性を正しく理解できるようになります。
その結果、利用者に対してすぐにイライラしたり怒ったりすることが少なくなるでしょう。障害者を支援するうえで資格を取得することは、トラブルを未然に防ぐうえでも役立ちます。
障害者グループホームでトラブルが発生した場合の対策
障害者グループホームでトラブルが発生した場合は、以下の順序で対応していくことが大切です。
問題を再度発生させないためにも、事故後の対策が重要です。施設の信頼性にも影響してくるので、ぜひご確認ください。
1.利用者や職員のケアを実施する
トラブルが発生した場合は、利用者や職員のケアを最優先にすることが大切です。現場の職員は速やかに安全を確保し、二次被害の発生を防がなくてはいけません。
不安定になっている利用者には、安心感を与えるように寄り添いましょう。職員が怪我をしている場合は、ただちに処置や救急搬送などを行う必要があります。
業務中の怪我であれば、労働災害が認定される可能性もあるので、サービス管理責任者は職員と治療中や治療後の話をしておくことも大切です。
2.家族や関係機関へ報告・説明する
障害者グループホームでトラブルが発生した場合、速やかに家族や市町村へ連絡をしなくてはいけません。
悪質に隠蔽したと判断されれば、利用者やその家族から損害賠償を請求される可能性もあります。行政からも厳しい処罰が下され、指定事業所の取り消しや業務停止といった処分を受けることも考えられます。
家族や関係機関への第一報は電話を使用して速やかに状況説明をしましょう。
3.トラブルの原因を調査する
当事者のケアや家族と連絡がついたら、トラブルの原因を調査します。原因を特定することで再発防止策を検討でき、よりよいケアの提供につながります。
会議の実施や事故報告書の作成などをして、原因を調査しましょう。
調査をする際には感情的にならず、客観的な事実に基づいた分析が大切です。
4.職員間で情報共有をする
次に会議や事故報告書の内容をもとに決まった対応策を職員間で共有します。
そのため、申し送りノートや事故報告書を使用し、事故原因と対策を共有することが大切です。同じ事故を繰り返さないためには、職員間での情報共有の徹底が重要です。
5.再発防止策を策定して実行する
最後に家族や職員間で決定した再発防止策を実行します。
再発防止策は、職員一人ひとりが危機感や問題意識を持ったうえで実行することが大切です。
問題意識がないと、事故対策は形骸化してしまう可能性があるからです。対策を文書化するだけでなく、マニュアルを作成して職員を指導しておくとよいでしょう。
定期的に研修や勉強会を行うことで、職員の意識も高まり事故の抑制にもつながります。
まとめ
障害者グループホームでは、世話人や利用者が起こすあるあるのトラブルがあります。このような事故は、事前に対策を立てておくことが可能です。
その際には原因を調査し、次の対策を講じる必要があります。同じトラブルが起きないよう、職員や家族、行政などに速やかに連絡し、次の対処法を実行していくことが大切です。
カイテクは、「近所で気軽に働ける!」看護単発バイトアプリです。
- 「約5分」で給与GET!
- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!
- 働きながらポイントがザクザク溜まる!
27万人以上の看護師などの有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /







