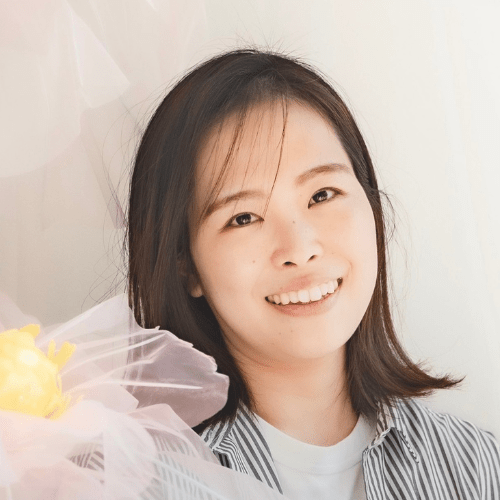ジャンル別記事
認定看護師とは?役割や目的・なるためにかかる費用や期間を解説
「認定看護師とはどんな資格?」「取得のメリットや難しさを知りたい」と思っている方は多いのではないでしょうか。
認定看護師は特定分野の高度な看護技術と知識を持つ資格で、取得には研修や審査が必要です。費用や時間の負担が大きく、計画的な準備が求められます。
また、2026年に制度が廃止され、新制度へ移行予定です。
読むことで、認定看護師を目指すための具体的なステップが明確になり、キャリア選択の参考になります。
認定看護師とは?
日本看護協会が定める600時間以上の認定看護師教育を受け、認定看護師認定審査に合格することで取得できます。どのような役割があるのか、認定看護師の種類など詳しくみていきましょう。
認定看護師の役割
認定看護師は、「実践・指導・相談」この3つの役割を通して、看護の質の向上に日々貢献しています。
実践とは、専門的な知識や技術を活かして、患者に対する質の高い看護を提供することです。
次に指導とは、臨床現場で、後輩や同僚の看護師に対して専門知識や技術の指導を行うことを指します。
そして相談とは、認定看護師は、医師や他の医療スタッフと連携し、適切なケアを提供するための助言や調整を行います。
認定看護師は、病院や訪問看護師ステーションやクリニック・診療所だけではなく、介護施設などで活躍しています。
参考:日本看護協会
認定看護師の数
2021年時点で、日本国内には2万2000人の認定看護師がいます。
認定看護師の分野は19あり、それぞれの分野で活躍する人数にばらつきがあります。
一番多い分野は、皮膚・排泄ケアで約2,000人です。医療の高度化によって、看護師に求められる役割も増加していることから、認定資格を取得をする看護師も増加していると考えられます。
参考:日本看護協会
認定看護師と専門看護師の違い
認定看護師と専門看護師では求められる役割が異なります。
認定看護師は、特定の看護分野で高度な技術と知識を活かし、質の高い看護を実践することが求められます。
一方で専門看護師は、複雑で解決が困難な看護問題を抱える個人や家族などに対し、専門的な知識と技術を活かして、質の高いケアを効率的に提供することが役割です。
その他の違いについて、以下にまとめました。
| 認定看護師 | 専門看護師 | |
|---|---|---|
| 役割 | 実践・指導・相談 | 実践・相談・調整・倫理調整・教育・研究 |
| 分野 | 19分野(感染管理、皮膚・排泄ケアなど) | 14分野(がん看護、小児看護など) |
| ケアの対象者 | 患者さんへの直接的なケア中心 | 患者さんとそのご家族への総合的な看護 |
| 受験資格 | 実務経験5年以上+所定の教育機関において所定の教育6ヶ月が必要 | 実務経験5年以上 +看護系大学院にて2年間で38単位の取得が必要 |
| 更新 | 5年ごとに更新審査あり | 5年ごとに更新審査あり |
このように、さまざまな違いがあります。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

参考:専門看護師

\ インストールから登録まで5分! /
認定看護師の種類
認定看護師の資格は、分野ごとにわかれています。
認定看護分野は、保健・医療・福祉の現場において、熟練した看護技術と知識が求められる看護分野であり、日本看護協会によって定められています。
2026年度より認定看護師の制度が改正されるため、A課程とB課程に分かれています。それぞれ詳しく見ていきましょう。
A課程
A課程の認定看護分野は、21分野あります。
| 分野名 | 知識と技術 |
|---|---|
| 救急看護 | ・救急医療現場における病態に応じた迅速な救命技術、トリアージの実施 ・災害時における急性期の医療ニーズに対するケア ・危機状況にある患者・家族への早期的介入および支援 |
| 皮膚・排泄ケア | ・褥瘡などの創傷管理およびストーマ、失禁等の排泄管理 ・患者・家族の自己管理およびセルフケア支援 |
| 集中ケア | ・生命の危機状態にある患者の病態変化を予測した重篤化の予防 ・廃用症候群などの二次的合併症の予防および回復のための早期リハビリテーションの実施 |
| 緩和ケア | ・疼痛、呼吸困難、全身倦怠感、浮腫などの苦痛症状の緩和 ・患者・家族への喪失と悲嘆のケア |
| がん化学療法看護 | ・がん化学療法薬の安全な取り扱いと適切な投与管理 ・副作用症状の緩和およびセルフケア支援 |
| がん性疼痛看護 | ・痛みの総合的な評価と個別的ケア ・薬剤の適切な使用および疼痛緩和 |
| 訪問看護 | ・在宅療養者の主体性を尊重したセルフケア支援およびケースマネジメント看護技術の提供と管理 |
| 感染管理 | ・医療関連感染サーベイランスの実践 ・施設の状況の評価と感染予防・管理システムの構築 |
| 糖尿病看護 | ・血糖パターンマネジメント、フットケア等の疾病管理および療養生活支援 |
| 不妊症看護 | ・生殖医療を受けるカップルへの必要な情報提供および自己決定の支援 |
| 新生児集中ケア | ・ハイリスク新生児の病態変化を予測した重篤化の予防 ・生理学的安定と発育促進のためのケアおよび親子関係形成のための支援 |
| 透析看護 | ・安全かつ安楽な透析治療の管理 ・長期療養生活におけるセルフケア支援および自己決定の支援 |
| 手術看護 | ・手術侵襲を最小限にし、二次的合併症を予防するための安全管理(体温・体位管理、手術機材・機器の適切な管理等) ・周手術期(術前・中・後)における継続看護の実践 |
| 乳がん看護 | ・集学的治療を受ける患者のセルフケアおよび自己決定の支援 ・ボディイメージの変容による心理・社会的問題に対する支援 |
| 摂食・嚥下障害看護 | ・摂食・嚥下機能の評価および誤嚥性肺炎、窒息、栄養低下、脱水の予防 ・適切かつ安全な摂食・嚥下訓練の選択および実施 |
| 小児救急看護 | ・救急時の子どもの病態に応じた迅速な救命技術、トリアージの実施 ・育児不安、虐待への対応と子どもと親の権利擁護 |
| 認知症看護 | ・認知症の各期に応じた療養環境の調整およびケア体制の構築 ・行動心理症状の緩和・予防 |
| 脳卒中リハビリテーション看護 | ・脳卒中患者の重篤化を予防するためのモニタリングとケア ・活動性維持・促進のための早期リハビリテーション ・急性期・回復期・維持期における生活再構築のための機能回復支援 |
| がん放射線療法看護 | ・がん放射線治療に伴う副作用症状の予防、緩和およびセルフケア支援 ・安全・安楽な治療環境の提供 |
| 慢性呼吸器疾患看護 | ・安定期、増悪期、終末期の各病期に応じた呼吸器機能の評価および呼吸管理 ・呼吸機能維持・向上のための呼吸リハビリテーションの実施 ・急性増悪予防のためのセルフケア支援 |
| 慢性心不全看護 | ・安定期、増悪期、終末期の各病期に応じた生活調整およびセルフケア支援 ・心不全増悪因子の評価およびモニタリング |
なお、こちらは2026年度をもって教育が終了となります。A課程の資格を取ろうとしている人は注意しましょう。
なお、A課程の認定審査は2029年度まで受けられます。5年ごとの更新審査は継続されるため、A課程で資格を取得したとしても、資格が停止することはありません。
B課程
2020年度より、19分野のB課程が開始されています。
| 分野名 | 知識と技術 |
|---|---|
| 感染管理 | ・医療関連感染の予防・管理システムの構築 ・医療管理感染の予防・管理に関する科学的根拠の評価とケア改善 ・医療関連感染サーベイランスの立案・実施・評価 ・感染兆候がある患者へ薬剤の臨時投与ができる知識・技術 |
| がん放射線療法看護 | ・放射線治療を受ける対象の身体的・心理的・社会的アセスメント ・再現性確保のための支援 ・急性期および晩期有害事象に対する症状マネジメントとセルフケア支援 ・医療被曝を最小限にするための放射線防護策、安全管理技術 |
| がん薬物療法看護 | ・がん薬物療法の適正な投与管理とリスクマネジメント、ばく露対策 ・がん薬物療法に伴う症状緩和 ・自宅での治療管理や有害事象に対応するための個別的な患者教育 ・患者・家族の意思決定支援と療養生活支援 |
| 緩和ケア | ・痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題のアセスメント ・全人的問題を緩和し、QOLを向上するための症状マネジメント ・家族の喪失や悲嘆への対応 |
| クリティカルケア | ・急性かつ重篤な患者の重篤化回避と合併症予防に向けた全身管理 ・安全・安楽に配慮した早期回復支援 ・侵襲的陽圧換気・非侵襲的陽圧換気の設定の変更、人工呼吸管理の患者に対する鎮静薬の投与量の調整、人工呼吸器からの離脱ができる知識・技術 ・持続点滴中の薬剤の投与量の調整を安全・確実にできる知識・技術 |
| 呼吸器疾患看護 | ・呼吸症状のモニタリングと評価、重症化予防 ・療養生活行動支援および地域へつなぐための生活調整 ・症状緩和のためのマネジメント ・侵襲的陽圧換気・非侵襲的陽圧換気の設定の変更、人工呼吸管理の患者に対する鎮静薬の投与量の調整、人工呼吸器からの離脱ができる知識・技術 |
| 在宅ケア | ・生活の場におけるQOLの維持・向上とセルフケア支援 ・対象を取り巻くケアシステムの課題に対する解決策の提案 ・生活に焦点をあてた在宅療養移行支援および多職種との調整・協働 ・意思決定支援とQOLを高めるエンド・オブ・ライフケア ・気管カニューレの交換が安全にできる知識・技術 ・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換が安全にできる知識・技術 ・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去が安全にできる知識・技術 |
| 手術看護 | ・手術侵襲およびそれによって引き起こされる苦痛を最小限に留めるためのケア ・手術中の患者の急変および緊急事態への迅速な対応 ・患者および家族の権利擁護と意思決定支援 ・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整ができる知識・技術など |
| 小児プライマリケア | ・重篤な状態にある児もしくは医療的ケア児に対する重症化予防 ・外来および地域等のプライマリケアの場におけるトリアージ ・家族の家庭看護力・育児力向上に向けたホームケア指導 ・不適切な養育または虐待の予防、早期発見と、子どもの事故防止 ・身体所見および気管カニューレの状態を病態判断し、気管カニューレの交換が行える知識・技術 |
| 新生児集中ケア | ・ハイリスク新生児の急性期の全身管理 ・障害なき成育のための個別ケア ・ハイリスク新生児と親への家族形成支援 ・不適切な養育または虐待のハイリスク状態の予測と予防 ・身体所見および気管カニューレの状態を病態判断し、気管カニューレの交換が行える知識・技術 |
| 心不全看護 | ・心不全症状のモニタリングと評価、重症化予防 ・療養生活行動支援および地域へつなぐための生活調整 ・症状緩和のためのマネジメント ・持続点滴中の薬剤の投与量の調整を安全・確実にできる知識・技術 |
| 腎不全看護 | ・疾病の進展予防、合併症の早期発見と症状マネジメント、セルフケア支援 ・腎代替療法の選択・変更・中止にかかわる自己決定に向けた支援 透析療法における至適透析の実現に向けた支援 ・急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作および管理を安全・確実にできる知識・技術 |
| 生殖看護 | ・性と生殖の機能、その障害とリスク因子に関する知識に基づく妊孕性の評価 ・性と生殖の健康課題に対する、多様な選択における意思決定支援 ・患者・家族の検査期・治療期・終結期の安全・安楽・納得を守る看護実践とケア調整 ・妊孕性温存および受胎調節に関する指導 |
| 摂食嚥下障害看護 | ・摂食嚥下機能とその障害の評価 ・摂食嚥下機能の評価結果に基づく適切な援助・訓練方法の選択 ・誤嚥性肺炎、窒息、栄養低下、脱水の増悪防止に向けたリスク管理 |
| 糖尿病看護 | ・血糖パターンマネジメント ・病期に応じた透析予防、療養生活支援 ・予防的フットケア ・インスリンの投与量の調整ができる知識・技術 |
| 乳がん看護 | ・後合併症予防および緩和のための周手術期ケアと意思決定支援 ・ライフサイクルの課題を踏まえた、治療に伴う女性性と家族支援 ・乳房自己検診、リンパ浮腫等の乳がん治療関連合併症の予防・管理 ・創部ドレーンの抜去ができる知識・技術 |
| 認知症看護 | ・認知症の症状マネジメントおよび生活・療養環境の調整 ・認知症の病期に応じたコミュニケーション手段の提案と意思決定支援 ・家族への心理的・社会的支援 ・抗けいれん剤、抗精神病薬および抗不安薬の臨時の投与ができる知識・技術 |
| 脳卒中看護 | ・重篤化回避のためのモニタリングとケア ・早期離床と生活の再構築に向けた支援 ・在宅での生活を視野に入れたケアマネジメントと意思決定支援 ・抗けいれん剤、抗精神病薬および抗不安薬の臨時の投与ができる知識・技術 |
| 皮膚・排泄ケア | ・褥瘡のトータルマネジメント ・管理困難なストーマや皮膚障害を伴うストーマケア ・専門的な排泄管理とスキンケア ・脆弱皮膚を有する個人・リスクがある個人の専門的なスキンケア ・地域包括ケアシステムを視野に入れた同行訪問実施とマネジメント ・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去および創傷に対する陰圧閉鎖療法ができる知識・技術 |
A課程とB課程では、救急看護と集中ケアがクリティカルケアとして統合されたり、緩和ケアとがん性疼痛看護が緩和ケアと統合されたりしました。
また、分野名も9分野で変更(がん化学療法看護から、がん薬物療法看護へや、訪問看護が在宅ケアへなど)されています。
認定看護師になるには?
認定看護師になるには、どのような要件があるのでしょうか。
- 認定看護師の受験資格と要件
- 認定看護師になるためにかかる費用
- 認定看護師になるための期間
これらについて詳しく解説します。
どれも認定看護師を目指すうえで重要な項目ですので、確認していきましょう。
認定看護師の受験資格と要件
認定看護師の受験資格を得るには、実務経験と認定看護師教育機関の修了が必要です。
具体的な受験資格は以下のとおりです。
- 看護師免許を保持していること
- 看護師免許取得後、通算5年以上の実務経験があること(うち3年以上は認定看護分野の実務経験)
まず、これらの条件を満たした上で、認定看護師教育機関に入学・修了する必要があります。
その後、認定看護師認定審査を受け、合格すると認定看護師として活躍できます。
また、資格取得後は5年ごとに更新が必要なため、忘れずに手続きを行いましょう。
認定看護師になるためにかかる費用
認定看護師になるには約200万円の費用がかかります。
主な費用として、入試検定料や授業料、実習費、認定審査料などで約100万円が必要です。さらに、家賃や引っ越し費用、交通費、書籍代、パソコン購入費など、個人の状況によって変動する費用が約100万円かかります。
これに加えて生活費も必要です。
病院によっては支援制度や奨学金があり、日本看護協会の奨学金では最大120万円の支援を受けることができます。
認定看護師になるための期間
認定看護師の取得には、実務経験5年以上を前提として約2年かかります。
▼スケジュール例
- 2025年7月:入学願書提出
- 2025年9月:入学試験
- 2025年4月:授業開始(A課程:615時間 / B課程:800時間+実習)
- 2025年3月:授業修了
- 2025年5月:認定審査
- 2025年7月:合格発表・登録申請
- 2025年8月:認定証受領
教育機関での学習時間はA課程615時間、B課程800時間+実習が必要です。
授業のスケジュールは平日中心や週末のみなど機関によって異なるため、6ヶ月以上通えば取得できるとは限らない点に注意しましょう。
認定看護師の資格取得の流れ
認定資格の要件を満たした後の流れについて解説します。
要件を満たしても、資格取得には認定審査を受ける必要があります。以下のポイントを確認し、しっかり対策を行いましょう。
認定審査の内容
認定審査の方法は筆記試験です。
マークシート方式で四肢択一で問題が全40問出題されます。試験時間は100分間です。
なお、問題の出題形式と配点は以下の表を参照してください。
| 出題形式 | 出題数 | 配点 |
|---|---|---|
| 問題1 客観式一般問題 | 20問 | 50点 |
| 問題2 客観式状況設定問題 | 20問 | 100点 |
| 合計 | 40問 | 150点 |
出題範囲は、共通科目を含めた各認定看護分野の教育基準カリキュラムとされています。
認定審査の合格率や合格者数は未発表
認定看護師の合格率は、90%以上と言われています。
現在、合格発表の公開期間が終了しているため、詳しい数字の確認はとれておりません。しかし、日本精神科看護協会によると、令和5年度の試験結果は以下の通りでした。
| 受験者数(名) | 合格者数(名) | |
|---|---|---|
| 認定試験 | 78 | 69 |
| 更新審査 | 149 | 149 |
分野ごとに合格率は違うでしょうが、認定試験は90%の合格率に加えて、更新審査においては100%の合格率となっています。
しっかりと、勉強し試験の対策を行えば合格は狙えるといえます。
認定看護師になる3つのメリット
認定看護師になることで得られるメリットは、以下の3点が挙げられます。
- 専門的なスキルを向上できる
- キャリアアップの機会が増える
- できる業務の幅が広がる
実際に、どのようなスキルが上がるのかや、できる業務の幅が広がるとはどういうことなのか詳しくみていきましょう。
専門的なスキルを向上できる
認定看護師の資格を取得することで、専門的な知見を得られるためスキルの向上が可能です。
看護師は、オールラウンダーのため幅広い知識が必要です。一方で、認定看護師であれば自身の専門としたい領域をより深く学ぶことが可能となります。
そのため、より高度なスキルと知見を身につけられ、患者さんに合わせた適切なケアをより行えるようになります。
キャリアアップの機会が増える
認定看護師は、看護師の上位資格のためキャリアアップの機会が増えます。
認定看護師の資格を取得するということは、その分野において深い知見があることを示せるようになるということです。一般的なな看護師よりも、専門的な知見と技術を持っているため、他の看護師への教育も可能となります。
こうした、スキルの向上によりキャリアアップにつながります。認定看護師のキャリアアップについては、こちらで詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

できる業務の幅が広がる
認定看護師は指導や教育の役割も担うため、活動の幅を広げられます。
専門分野において深い知識と技術を持つ認定看護師は、配属先にとどまらず、他部署への出向や勉強会・セミナーの開催など多岐にわたる業務を行います。
特定の業務に縛られずに働ける点は、大きなメリットと言えるでしょう。
認定看護師のデメリット
認定看護師は、メリットばかりではなくデメリットもあります。以下にデメリットを3つ挙げていますのでそれぞれ確認していきましょう。
資格取得のハードルが高い
認定看護師は、資格取得までのハードルが高いことがデメリットといえます。
資格取得には、5年以上の実務経験が必要です。しかも、うち3年は希望する専門分野での実務経験が必要です。
それに加え所定の教育機関での履修も必要な点が、ハードルが高いと言われる理由です。
学費や研修費用の負担
認定看護師は、取得時や取得後も諸費用が必要になります。この費用の負担が、デメリットといえるでしょう。
資格取得だけでも、200万円掛かると言われています。資格取得後も自己研鑽のための研修やセミナーを受けることが必要です。
これらの研修やセミナーのための費用は、自己負担となることもあるため、認定看護師は費用の負担がデメリットとなります。
更新制度がある
認定看護師の資格には、更新制度があります。この更新制度があることが、デメリットと感じる方がいます。
更新制度は、認定看護師の質を担保するために必要です。
更新のためには、過去5年間に看護実践時間(2,000時間以上)に加え、自己研鑽実績が必要とされています。
この自己研鑽については、項目ごとに点数が決まっており提出物もあります。
資格取得後も、学びが続くことは看護師として当たり前のことですが、書類の提出などを負担に感じる方もいるでしょう。
参考:日本看護協会
認定看護師に向いている人の特徴
認定看護師に向いている人の特徴を3つ挙げました。自身が、向いている特徴に当てはまるか確認していきましょう。
高度な専門知識を身につけたい
認定看護師に向いている人は、高度な専門知識を身につけたいという向上心のある人です。
認定看護師の資格をとるためには、時間もお金も必要です。また、資格取得後も自己研鑽が必要になるため、知識欲があるかどうかは重要です。
高度な知識を身につけたいと考えている人は、継続的に学べるため、認定看護師に向いているといえるでしょう。
臨床現場でリーダーシップを発揮したい
認定看護師には、リーダーシップを発揮できる人が向いています。
医師や看護師、薬剤師と協働する中で、自身の専門知識を活かし、主体的にリーダーシップを取る場面が多く求められるためです。
教育や指導に関心がある
認定看護師の役割には、教育や指導も含まれているため、これらに関心がある人は向いているといえるでしょう。
認定看護師は、自身の深い知見や技術を他の看護師への指導や教育が求められます。
これらができることは、認定看護師の役割を遂行する上で重要といえるため、関心がある人は認定看護師に向いています。
認定看護師に関するよくある質問
認定看護師に関するよくある質問をまとめました。
認定看護師の資格取得にかかる費用は?
認定看護師にかかる費用は、約200万円と言われています。資格取得後も、自己研鑽のために費用がかかるため注意しましょう。
認定看護師の試験の難しさは?
試験は、90%程度が合格しているため難易度はそれほど高くないといえるでしょう。
認定看護師の資格更新の条件は?
認定看護師の資格更新には、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 過去5年間に看護実践時間(2,000時間以上)
- 自己研鑽実績(50点以上)
なお、自己研鑽の点数についてはこちらをご覧ください。
参考資料:認定看護師 研修実績および研究業績等申告表項目一覧
試験はありませんが、審査書類の提出が必要です、また、審査料の振り込みが30,800円必要となります。
参考:日本看護協会
認定看護師がなくなるというのはなぜですか?
認定看護師は、なくなりません。
しかし、2026年度より、A課程からB課程に移行します。それに伴い、受験資格の要件も変更になっていますので注意しましょう。
制度の移行についてはこちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

認定看護師のまとめ
認定看護師は、特定の看護分野で高度な知識と技術を持ち、実践・指導・相談を通じて看護の質向上に貢献する資格です。
取得には5年以上の実務経験や教育機関での研修が必要で、費用は約200万円かかるため、計画的な準備が求められます。
また、2026年度から制度が改正され、A課程が廃止されB課程に統合されるため、最新情報の確認が重要です。
認定看護師の制度やメリット・デメリットを理解し、自身の目指す看護師像に合った選択をしましょう。
カイテクは、「近所で気軽に働ける!」看護単発バイトアプリです。
- 「約5分」で給与GET!
- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!
- 働きながらポイントがザクザク溜まる!
27万人以上の看護師などの有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /