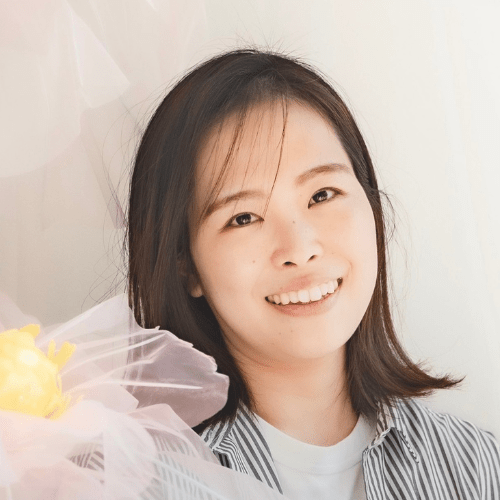ジャンル別記事
看護師国家試験が難しかった年は?難易度や合格率をチェックして国家試験に備えよう!
「看護師国家試験は難しい」という評判は本当なのか気になる方もいるでしょう。試験の傾向や合格基準を知らないまま対策を進めてしまうと、効果的な勉強ができず、不合格となる可能性があります。
結論、看護師国家試験が難しかった年は、2024年の第113回です。
さらに、第115回試験に向けた効果的な勉強法や試験当日の対策についても詳しく解説しているので、参考にしてください。
看護師国家試験で難しかった年は2024年(第113回)
看護師国家試験を知るには、まず過去のデータを確認しましょう。合格率や過去10年のボーダーラインについて詳しく解説します。
看護師国家試験の合格率
過去10年の合格率の推移は、以下の表のとおりです。
| 回(年度) | 受験者数 | 合格者数(合格率) |
|---|---|---|
| 第105回(2016年) | 62,154人 | 55,585人(89.4%) |
| 第106回(2017年) | 62,534人 | 55,367人(88.5%) |
| 第107回(2018年) | 64,488人 | 58,682人(91.0%) |
| 第108回(2019年) | 63,603人 | 56,767人(89.3%) |
| 第109回(2020年) | 65,568人 | 58,513人(89.2%) |
| 第110回(2021年) | 66,124人 | 59,769人(90.4%) |
| 第111回(2022年) | 65,025人 | 59,344人(91.3%) |
| 第112回(2023年) | 64,051人 | 58,152人(90.8%) |
| 第113回(2024年) | 63,301人 | 55,557人(87.8%) |
| 第114回(2025年) | 63,131人 | 56,906人(90.1%) |
表から見てもわかるように、第113回は近年最も低い合格率です。このことから、国家試験で難しかった年は第113回といえます。
過去10年の一般問題と状況設定問題のボーダーライン
一般問題と状況設定問題は、年によって変動します。そこで、過去10年のボーダーラインを見てみましょう。
| 回(年度) | ボーダーライン(点数) | 満点 |
|---|---|---|
| 第105回(2016年) | 151点 | 247点 |
| 第106回(2017年) | 142点 | 248点 |
| 第107回(2018年) | 154点 | 247点 |
| 第108回(2019年) | 155点 | 250点 |
| 第109回(2020年) | 155点 | 250点 |
| 第110回(2021年) | 159点 | 250点 |
| 第111回(2022年) | 167点 | 250点 |
| 第112回(2023年) | 152点 | 249点 |
| 第113回(2024年) | 158点 | 250点 |
| 第114回(2025年) | 148点 | 250点 |
毎年、設問が不十分で正解が得られないなどの理由で、採点除外の扱いを受ける問題が出てくるため、満点の点数は変動があります。
【予測】第115回看護師国家試験の合格率・難易度
第115回看護師国家試験(2026年実施予定)の合格基準は、現時点で未定ですが、例年の傾向から予測することが可能です。合格基準は、次のような2つの要件を満たす必要があります。
| 試験区分 | 予測される合格基準 |
|---|---|
| 必修問題(40問) | 80%以上(32問以上) →絶対基準 |
| 一般問題+状況設定問題(240問) | 60%程度(144~150点) →相対的な得点基準 |
第113回では、必修問題のミスによる不合格が目立ったことから、115回も引き続き必修対策の重要性が強調されると考えられます。特にコロナ禍で臨床経験に差が出た世代が中心になるため、臨地実習や状況設定問題の比重が高まる可能性もあります。
また、近年の傾向から、「災害対応」「地域包括ケア」「ヤングケアラー支援」など、時事的・制度的トピックが頻出するでしょう。これらに対応する形で、新傾向問題や応用的設問の割合が増加することが予想されるため、過去問+最新の医療福祉動向への理解が必須です。

\ インストールから登録まで5分! /
第114回看護師国家試験の合格率・難易度
第114回看護師国家試験(2024年実施)の合格基準は、厚生労働省より以下のように発表されています。
難易度に関しては、「必修問題は基礎的だが正確な知識が必要」「一般問題・状況設定はオーソドックスな傾向」という声が多く、全体的には標準的という評価です。
一方で、医療制度や感染対策、社会的課題(ヤングケアラー、LGBTQ支援)など、時事性の高いトピックが複数出題され、直前対策や情報アップデートが不十分だった受験者には難しく感じられた可能性もあります。

第113回看護師国家試験の合格率・難易度
第113回看護師国家試験では、厚生労働省より正式に以下の合格基準が発表されています。
特に注目されたのが「必修問題の難化」です。基礎知識中心ながら、選択肢の引っかけや文面の紛らわしさが増え、ケアレスミスで不合格になる受験者が例年より多く見られました。
また、出題範囲の広がりと応用的な判断力が問われたことも、得点のばらつきを生んだ一因です。
第113回看護師国家試験が難しかった背景
第113回看護師国家試験が難しかった背景には、以下の4点が考えられます。
必修問題の難化と合格基準の厳格化
第113回看護師国家試験では、必修問題の難易度が例年より高く、合格のハードルが上がったとされています。必修問題は全40問中32問(80%)以上正解しなければならない絶対評価であり、他の科目で得点してもここを落とすと合格はできません。
特に「誤っているものを選ぶ」形式や「二重否定」による混乱など、ケアレスミスを誘発する設問が受験者の得点を下げた要因とされています。また、保健・医療制度分野の出題では新制度に関する知識も問われており、情報更新が不十分な学生は対応が難しかったようです。
一般・状況設定問題で細かい知識や判断力が求められた
第113回看護師国家試験では、一般問題および状況設定問題において「選択肢の微妙な違いを見抜く力」や「状況の意図を読み取る力」が強く問われました。
特に一般問題では、以下の場面において、単なる暗記では通用しない設問が増加したようです。
- 災害対応
- 感染症
- 倫理的判断
応用力や実践的な思考力を必要とする内容に、多くの受験者が戸惑ったのでしょう。
また、状況設定問題では、1問あたりの文章量が多く、内容も抽象的だったため、読解に時間がかかり、「時間が足りなかった」という声もSNS上で多数見られました。
設問内に含まれる情報の取捨選択や、正確な状況把握ができないと誤答しやすく、試験全体の印象を「難しかった」と感じさせる要因となっています。
出題範囲の拡大と新傾向問題の出現
第113回看護師国家試験では、従来の主要科目に加えて「新制度」や「地域包括ケア」「多職種連携」など、近年の医療・福祉の動向を反映した出題が目立ちました。
たとえば、在宅医療に関する設問では「訪問看護指示書を出せる職種」に関する具体的な知識が必要となり、単なる看護技術や疾患知識だけでは対応しきれない問題構成となっていました。
また、以下の社会的課題に関する設問も増加したようです。
- ヤングケラー
- 災害看護
- 自殺予防
これらは教科書には載っていても詳細が少なく、過去問対策だけでは不十分な分野です。さらに、これまで出題されにくかった「情報共有の方法」や「職場内での指導・相談対応」なども問われ、臨床現場に即した判断力が求められたことも難化要因の1つです。
新型コロナの影響で実習・学習機会が制限された世代
第113回の受験者は、看護学生時代に新型コロナウイルスの影響を強く受けた世代です。
臨地実習が制限され、代替のオンライン実習やシミュレーションに変更された学校も多く、実際の臨床現場での経験を積む機会が減少しました。そのため、状況設定問題や応用的な場面設定に対する対応力に不安を感じた学生が少なくありません。
また、グループ学習や国家試験対策の合同勉強会が制限されることで、学習の質と量にばらつきが出やすい環境下にありました。講義もオンライン中心で行われることが多く、教師との双方向のやりとりが難しく、内容が定着しにくいと感じる学生もいたようです。
これらの要因は、「情報を多角的に捉える」「状況を適切に判断する」といった試験で問われる力の育成に影響を及ぼしたと考えられます。
【仮説】看護師国家試験で合格率が下がった次の試験の特徴
看護師国家試験では、前回の試験で合格率が大きく下がった場合、次回試験で調整が行われる傾向があります。過去の試験データを分析すると、以下のような特徴が見られます。
- 必修問題の難易度がやや下がる可能性
- 一般問題・状況設定問題のバランス調整
- 基本的な知識を重視した出題傾向
必修問題の合格基準は80%(40点/50点)と固定されているため、難易度が高すぎる場合は調整される場合があります。
過去に合格率が低下した後の試験では、臨床現場で必要な基礎知識を問う問題が増える傾向がみられるため、基礎をしっかり固めることが、次回試験の合格への鍵です。
第113回看護師国家試験の必修問題・一般問題・状況設定問題の出題傾向
必修問題・一般問題・状況設定問題に分けてそれぞれの出題傾向を解説します。出題傾向がわかることで、学習計画も立てやすくなるため、ぜひ抑えておきましょう。
必修問題:基礎が中心だが高難易度の問題もあり
第113回試験の必修問題は、例年通り基礎知識を問う内容が中心でした。しかし、一部の問題では多くの情報の中から適切な情報を抜き出す判断力を要する設問があり、受験生の間で「難しかった」との声も上がっていました。
内容としては解剖生理学や看護技術の基本に加え、倫理的判断や法の知識を問う問題も注目され、総合的な理解が必要とされた点が特徴です。
一般問題:基本的には例年通り
一般問題は大きな変化がなく、過去問をしっかり解いていれば対応できる範囲でしたが、難しいと感じる受験者も多かったようです。
特に病態生理に関する問題では、基礎知識に加え、実際の臨床判断を求められるケースが多く出題されました。
状況設定問題:状況設定が細い傾向あり
第113回では、状況設定問題の情報量が多く、細かい状況判断を求める問題が増えました。
近年、状況設定問題の設定はより詳細になっており、必要な情報を瞬時に把握する力が求められていることがうかがえます。
看護師国家試験に落ちる人の特徴
看護師国家試験は合格率が80~90%と比較的高いですが、それでも毎年1万人以上が不合格になります。下記では、不合格になる人の5つの特徴を挙げています。
不合格になる人の特徴をしっかりと理解し、同じ失敗をしないように以下で確認しましょう。
必修問題の対策・勉強をしていない
必修問題対策をしていないと、看護師国家試験に不合格になる可能性があります。なぜなら、必修問題は50問中40点以上を取れなければ不合格となるためです。
必修問題は基礎的な学力を問うものですが、学習を怠ると失敗する可能性があります。一般問題や状況設定問題で高得点を取っても、必修で基準を満たせなければ不合格となるため、注意が必要です。
簡単そうに見えますが、細かい知識を問われる問題も多く、対策をしていなければ不合格のリスクが高まります。合格基準をクリアするために、最優先で対策を進めましょう。
試験対策を始めるのが遅い
試験対策を始めるのが遅いと、看護師国家試験に合格するのが難しくなります。なぜなら、試験直前に詰め込んでも、理解が浅くなり本番で応用できないからです。
最低でも6か月前から計画的に学習を始めることが重要です。また、看護師国家試験の出題範囲は膨大で、看護学生が3〜4年かけて学んだ内容が問われます。これまでの学校の試験とは異なる点を理解し、早めに対策を始めましょう。
過去問で対策をしていない
過去問を解かずに試験に臨むと、出題傾向を把握できず苦戦します。必ず過去5年分の問題を解き、出題パターンに慣れ、出題傾向を把握しましょう。
予想問題は、あくまで予想にすぎません。過去問だけ、予想問題だけという偏った勉強はせずに、どちらも上手に使いましょう。
体調管理をしていない
体調管理を怠ると、看護師国家試験で本来の力を発揮できません。なぜなら、無理な勉強を続けると体力が落ち、試験直前に体調を崩すリスクが高まるからです。
規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけましょう。特に、試験が行われる2月は寒さが厳しく、体調を崩しやすい時期です。試験本番と同じ時間帯に勉強し、睡眠時間と運動時間をしっかり確保することが大切です。
試験当日の空気や緊張に慣れていない
本番の雰囲気に慣れていないと、緊張して実力を十分に発揮できない可能性があります。
あらかじめ「わからない問題は深追いしない」「1つの設問は〇分以内に解く」など、自分なりのルールを決めておくのが効果的です。
看護師国家試験に向けた効果的な勉強法
看護師国家試験に合格するためには、計画的かつ効率的な勉強が必要です。特に、過去問を活用した学習や模試を通じた実践力の強化が重要になります。ここでは、合格に向けた具体的な勉強法を紹介します。
過去問研究を徹底的に行う
過去問を解くことで、試験の出題傾向や頻出テーマを把握できます。特に、過去5年分の問題を分析し、繰り返し出題される内容を重点的に学習するのが効果的です。
一般・状況設定問題は、同じような内容でも出題の仕方が変わる可能性があるため、しっかりと理解を深める必要があります。単に、暗記だけに頼らず理解することを目標とし勉強を進めましょう。
予想問題集を活用する
過去問だけでなく、最新の出題傾向を反映した予想問題集も活用しましょう。特に、試験範囲の中でも新しいガイドラインや診療基準が関わる分野は、最新の問題集で対策することが重要です。
また、過去問だけで勉強していると次第に、問題と答えを丸暗記してしまいます。新しい問題に触れることで、しっかりと問題を読んで解く癖をつけましょう。
模試を活用して弱点を克服する
本番の形式に慣れるために、全国模試や予備校の模試を活用しましょう。模試を受けることで、時間配分の練習や苦手分野の把握ができます。模試活用のポイントは、以下の3点です。
- 最低でも2回は受験し、1回目と2回目の結果を比較する
- 間違えた問題を復習し、同じミスをしないよう対策する
- 本番と同じ環境で模試を受け、試験当日の雰囲気に慣れる
模試を2回は受験することで、自身の実力の変化がわかります。必ず2回は受験することがおすすめです。また、何を間違えたかしっかり分析することが重要です。そして、なぜ間違えたかを明確にしましょう。
会場の雰囲気で緊張して間違える場合もあるため、模試の雰囲気に慣れ復習をすることで、合格により一層近づきます。
隙間時間を活用して勉強する
集中して勉強する時間が取れない場合でも、隙間時間を有効活用しましょう。看護師国家試験の勉強は長期戦のため、コツコツ積み上げられることが重要です。
おすすめの隙間時間の活用法は、以下の3つの方法です。
- アプリや音声教材で通勤時間に学習する
- 通勤・通学時間や休憩時間に1問解く習慣をつける
- 友人と問題を出し合いながら勉強する
このように、隙間時間を有効活用することで勉強を継続できます。最近は過去問が収録されているアプリもありますので、携帯ゲームやSNSを開く代わりに勉強の時間に当ててみましょう。
また、トイレや休憩の前に必修問題を軽く解くという習慣も、コツコツと積み上げれば可能です。
看護師国家試験の勉強は長丁場になります。友人と支え合いながら、取り組むことでモチベーションの維持にもつながりおすすめです。

看護師国家試験の概要
看護師国家試験の受験資格、スケジュールについて解説します。当日のスケジュールを確認し、試験へのイメージをしっかりとつけましょう。
受験資格
看護師国家試験を受験するには、以下のいずれかの資格を満たしている必要があります。
- 看護師養成課程(専門学校・大学・短大など)を修了した者
- 看護師養成課程の修了見込みの者
- 外国の看護師資格を持ち、厚生労働省の認定を受けた者
近年は、外国人の受験者もいます。今後、受験者数の割合が変わってくることで合格率も変動があるかもしれません。
試験日程と当日のスケジュール
看護師国家試験の日程と当日のスケジュールは以下のとおりです。
試験日:令和7年2月16日(日曜日)
▼試験時間
- 午前の部:9:50~12:50(180分)
- 午後の部:14:00~17:00(180分)
当日は、集合時間に遅れないように余裕を持って会場に向かうことが重要です。また、試験中に焦らないために、事前に試験の流れを把握しておくと安心です。
長丁場になるため、自分がリラックスできるよう、工夫をしましょう。
看護師国家試験が難しかった年に関するよくある質問
看護師国家試験が難しかった年によく聞かれる質問をまとめました。
看護師国家試験で満点とった人の特徴は?
満点を取る人の特徴は以下の3点がみられます。
- 試験範囲を網羅し、徹底的に過去問研修をしている
- 模試を複数回受け、出題パターンを完全に理解している
- 正確な知識に加え、問題の意図を読み取る力がある
満点を目指すよりも、合格ラインを超えることを意識した学習が重要です。
看護国家試験で落ちる人は何人くらい?
毎年の合格率は約88~91%で推移していますが、それでも1万人以上が不合格になっています。
| 回 | 受験者数 | 合格者数(合格率) | 不合格者数 |
|---|---|---|---|
| 第109回 | 63,603人 | 56,767人(89.2%) | 7,055人 |
| 第110回 | 64,488人 | 58,682人(90.4%) | 6,681人 |
| 第111回 | 62,534人 | 55,367人(91.3%) | 6,434人 |
| 第112回 | 62,154人 | 55,585人(90.8%) | 5,895人 |
| 第113回 | 60,947人 | 54,871人(87.8%) | 8,222人 |
第113回は合格率が低下した年であり、不合格者が8,000人を超えました。試験の難易度が上がることもあるため、油断せずに対策を行いましょう。
看護師国家試験で落ちた人の点数は何点?
看護師国家試験に落ちた人の点数は公表されていません。しかし、以下の条件を満たしていない場合、試験に不合格となります。
- 必修問題の正答率80%以上
- 一般問題と状況設定問題の合計が152点以上
逆にいうと、上記が合格ラインとなるので、ボーダーを明確に把握したうえで、対策を進められるでしょう。
看護師国家試験のボーダーの決め方は?
看護師国家試験のボーダーラインは、過去試験の難易度や受験者の成績によって決められ、厚生労働省によって発表されます。ボーダーラインは毎年変動するため、必ず確認することが大切です。
看護師国家試験は簡単すぎる?
一部では「合格率が毎年90%前後だから簡単」と言われることもありますが、実際はそうではありません。高い合格率は、受験資格に実習や学習課程を終えた看護学生が受験する仕組みが背景にあります。
問題自体は幅広い知識を問われ、必修問題で基準点を落とすと即不合格となる厳しさもあります。また、年度によっては「難しすぎて必修落ちが続出した」というケースもあるため、決して油断できる試験ではありません。
まとめ
看護師国家試験に合格するためには、過去問研究・予想問題集・模試の活用・隙間時間の有効活用が欠かせません。また、不合格になりやすい人の特徴を知り、同じ失敗をしないように対策を立てることが重要です。
本記事で紹介した勉強法を実践し、万全の準備を整えて試験本番に臨みましょう。
カイテクは、「近所で気軽に働ける!」介護単発バイトアプリです。
- 「約5分」で給与GET!
- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!
- 働きながらポイントがザクザク溜まる!
27万人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /