ジャンル別記事
処遇改善加算をピンハネされてる?疑わしいときの対処法を紹介
「もしかして、うちの職場が処遇改善加算を不正利用しているのではないか?」と疑問を抱き始めたら、答えを知りたくなるのが自然な反応です。
特に「給料が低い」と感じている場合、処遇改善加算の不正利用を疑うことがあります。
給料が低いと感じている方のために、給料アップの方法も紹介しますので、ぜひご覧ください。
また、手軽に給料アップを目指すなら、単発バイトをするのがおすすめです。カイテクでは、介護の求人が豊富に掲載されており、面接・履歴書なしで働き始められます。
ぜひこの機会に、以下から「カイテク」を無料でお試してください。
処遇改善加算ってピンハネできるの?

「処遇改善加算のピンハネは本当に可能なのか?」と考える方は多いと思います。気になるなら、まずは処遇改善加算について理解を深めることが大切です。
そこで以下では、処遇改善加算の概要やピンハネが可能かどうかを解説していきます。
処遇改善加算とは
厚生労働省の「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の仕組み」では、処遇改善加算について以下のように記載しています。
○ 新しい経済政策パッケージ(抜粋) (平成29年12月8日閣議決定)
介護人材の確保をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点を置きつつ、介護職員の更なる処遇改善を推進する。
具体的には、他の介護職員の処遇改善にこの加算を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所で働く10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを目指す。公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。
また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。
介護職員の人材不足は介護業界の慢性的な課題です。その解決を図るために、処遇改善を通じて介護職員が働きやすい環境を整えようと実施されているのが「介護処遇改善加算」です。
処遇改善加算とは、介護施設のためではなく、介護職員のために設けられた加算制度であることがわかります。

ピンハネは原則できない
処遇改善加算は、介護職員に対して給付されるものです。一旦事業所に入るという形を取っていますが、結局のところ介護職員が受け取るべき加算であることには変わりません。
事業所がこれを保有することは原則として許されていません。つまり、介護事業所が処遇改善加算をピンハネすることは「できない」ということです。
それでは、なぜピンハネを疑う声が出てくるのでしょうか?考えられる理由を次の項目で説明していきます。
ピンハネで考えられる原因
上記で説明した通り、ピンハネは許されていません。しかし、処遇改善加算は介護職員個人に直接給付されるものではなく、介護事業所を通して与えられるものであり、事業所の方針によりその配分に違いが生じることがあります。
処遇改善加算の具体的な配分方法には明確な規定がないため、例えば介護職員以外のスタッフへの配分を増やすと、その分介護職員に渡る加算の割合は減ってしまいます。
また、加算をどのように給料に反映するかの決まりもないため、月給ではなくボーナスに加算を上乗せしている場合もあるでしょう。
疑わしい場合でも、実際にはピンハネではなく、加算がわかりにくい形で給与に混じっていることが多いと言えます。
処遇改善加算のピンハネを疑うときの対処法

多くの場合、ピンハネが勘違いであるというのは上記で説明した通りです。しかし、それでも疑わしい状況が存在するかもしれません。
そのような不安を抱えながら職場で働くより、真相を探るべきです。ここでは、ピンハネを疑うときの対処法を解説していきます。
職場に確認してみる
ピンハネを疑うときには、職場で確認するのも一つの方法です。
ただし、感情に任せて「ピンハネしているに違いない!」と責め立てると、不必要な摩擦を生じさせてしまう可能性があります。確認の仕方には工夫が必要です。
就業規約などを確認し、処遇改善加算に関する記載があるかを見てみましょう。
就業規則を確認する
処遇改善加算の支給方法は、就業規則または賃金規程に記載されている必要があります。加算金の配分方法や支給形態(毎月の給与、賞与、一時金など)が明文化されていない場合、職員側は正確な支給状況を把握できません。
まずは「処遇改善手当」や「特定処遇改善加算」などの項目が、就業規則・給与規定にどう記載されているかを確認しましょう。記載が不十分な場合や曖昧な場合は、労務管理上の問題がある可能性があります。
事業所は加算金の配分に関して「周知義務」があるため、職員に説明する責任も負っています。不明点がある場合は、遠慮せずに管理者や人事担当者に説明を求めることが大切です。

処遇改善加算の対象なのか確認する
自分が処遇改善加算の対象者かどうかを確認することも重要です。制度上、加算は原則として「介護職員」に支給される仕組みですが、職種や雇用形態によっては対象外となることもあります。
例えば、事務職や調理員など介護以外の職種は対象にならないことがあり、非常勤職員や短時間勤務のパートは支給条件が限定されている場合もあります。
まずは自分の雇用契約書や職務内容を確認し、次に職場が公開している「処遇改善加算の配分方針」などをチェックしてみましょう。加算対象であるにもかかわらず、支給がない場合は、相談窓口や労働基準監督署への相談も検討すべきです。
専門家に相談してみる
ピンハネなどの事業所の不正を疑う場合は、労働基準監督署や弁護士に相談するのも良い手段です。専門家に相談する際には、相談内容を明確にし、可能な限り多くの証拠を提示しましょう。
具体的な根拠があることで、専門家も不正を判断しやすくなります。
ハローワークに行く
ハローワークを通じて就職した場合、提示された条件と実際が異なることがあれば、不正を訴えることが可能です。その際は、ハローワークが対応してくれます。
ピンハネなどの不正が疑われる場合には、ハローワークに相談してみるのも一つの方法です。


\ インストールから登録まで5分! /
処遇改善加算のピンハネによる罰則
処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善することを目的とした制度であり、その配分は厳格なルールに基づいています。
事業所が不適切に加算金を使用し、職員に還元していない場合、厚生労働省の定めるガイドラインに基づき、さまざまな罰則が科される可能性があります。以下では、具体的な罰則内容を詳しく見ていきましょう。
加算の返還命令と加算金の徴収が行われる
処遇改善加算を不正に運用した場合、最も一般的な罰則として「加算金の返還命令」が下されます。これは、支給された加算金のうち、職員に適切に分配されなかった分について国や自治体へ返金するというものです。
返還命令が下るケース
- 加算の支給ルールに反して、給与とは無関係な用途に使用した場合
- 就業規則や配分計画に記載されていない支給方法で運用した場合
返還命令に加え、「加算金に対する加算金(過少支給分に対する罰則的徴収)」が課されるケースもあります。これにより、事業所には大きな経済的ダメージが生じるため、注意が必要です。
行政指導や是正勧告の対象となる
ピンハネの疑いがある場合、まずは厚生労働省または自治体からの「行政指導」や「是正勧告」が行われます。これは、違反内容を事業所に通知し、改善を求める措置です。
行政指導の内容
- 支給方法の明文化(就業規則や配分計画の修正)
- 不足分の職員への支給
- 労務管理体制の見直し
改善が見られない場合や指導に従わない場合には、加算の取り消しや返還命令といったより厳しい処分へと発展します。ピンハネの事実が確定していなくても、内部告発や相談がきっかけで調査が入ることもあるため、透明性の高い運用が求められます。
悪質な場合は指定取り消しなどの重い処分も
処遇改善加算の不正受給が悪質と判断された場合、介護保険法に基づき「指定取消処分」が科されることもあります。これは事業所としての運営資格自体を失う非常に重い処分であり、経営継続が困難になることを意味します。
指定取消処分が下されるケース
- 故意に虚偽の報告書を提出した
- 長期間にわたり不正を継続していた
- 指導や改善勧告を無視し続けた
このような重罰を回避するには、加算制度に関する最新情報の把握や、就業規則への明確な記載、労務管理の適正化などが不可欠です。万が一の事態に備えて、第三者による労務監査なども有効です。
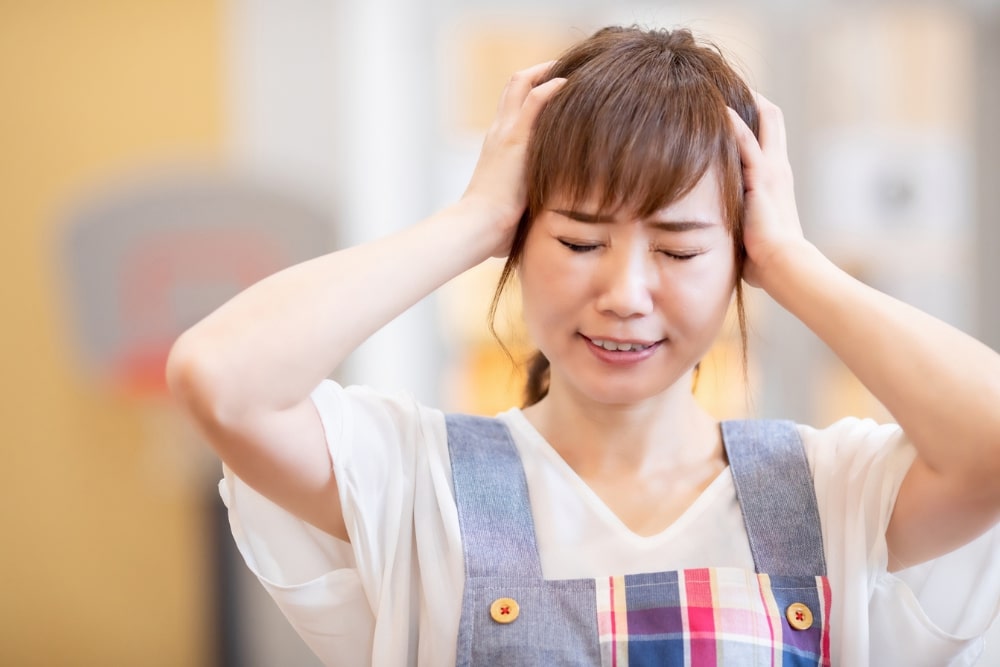
ピンハネでなく「処遇改善加算が少ない」と感じる理由
「処遇改善加算が職員にしっかり還元されていないのでは?」と感じる方は少なくありません。しかし、その原因が必ずしも“ピンハネ”とは限らず、制度の仕組みや支給方法に起因しているケースも多いです。
ここでは、加算が少なく見える代表的な3つの理由を紹介します。
加算額がもともと少ないケースがある
処遇改善加算は、事業所が受け取った介護報酬に応じて支給されるため、そもそもの加算額が少ないことがあります。とくに以下のような事業所では加算額が低くなる傾向があります。
- 利用者数が少ない小規模事業所
- 加算区分(Ⅰ〜Ⅳ)のうち、加算率が低い区分を取得している
- 処遇改善加算以外の加算(特定加算・ベースアップ加算など)を取得していない
加算額が低ければ、各職員に分配される金額も当然少なくなります。そのため、給与が大幅に上がらないからといって即「ピンハネ」と結びつけるのは早計といえます。
加算が賞与や一時金に組み込まれている
処遇改善加算は、必ずしも「月給」に上乗せされるとは限らず、賞与や一時金としてまとめて支給されるケースも多くあります。その結果、月々の給与明細に反映されないことで「もらっていない」と誤解されることがあります。
処遇改善加算の支給方法の一例
- 月給に一部上乗せ+年2回の賞与に加算金を分配
- 年1回の一時金として支給
- 退職時にまとめて支給(稀)
就業規則や支給規程にこのような支給形態が記載されていれば、合法的な運用とされています。給与明細や賞与明細を確認し、不明点があれば管理者へ確認することが大切です。

対象外の職種・雇用形態である
処遇改善加算の対象は原則として「介護職員」であり、事務職や看護師、調理スタッフなどは対象外となるケースが一般的です。また、パート職員や短時間勤務者は対象であっても、フルタイム職員と比べて支給額が少ない場合があります。
対象外や支給が少なくなるケースは以下のとおりです。
- 事務職や管理職(非介護従事者)
- 非常勤・週20時間未満の勤務
- 雇用契約上、加算対象外の取り決めがある
自身が処遇改善加算の配分対象となっているかどうかは、就業規則や給与規程を確認するか、職場に直接確認するのが確実です。

【ピンハネでなく給料が低いだけ?の場合】給料UPの方法

給料に納得ができないと、ピンハネを疑う人が多いです。職場が実際にピンハネをしていなくても、給料に満足がいかないまま働くのは辛いですよね。
そこで、こちらでは介護の職場で給料を上げる方法を解説します。
職場に交渉する
給料が低いと感じる場合、職場に交渉してみるのも一つの選択肢です。転職する必要がないため、職場での給料交渉はストレスを軽減できます。
ただし、交渉が必ずしも上手くいくとは限らないことを覚えておいてください。
給料を上げてほしい理由を丁寧に話し、「今後も長く勤めていきたい」という意思表示をすれば、給料を上げてもらえる可能性もあります。
転職する
現在の仕事で給料が低いと感じたなら、転職もおすすめです。転職活動をする際には、待遇などの条件をきちんと確認し、比較して選ぶようにしましょう。
介護の現場経験があれば、転職先として受け入れてくれる施設は多いです。
給料を上げたい場合、もともと給料の高い職場を選ぶか、副業OKの場所を選ぶのがおすすめです。
副業する
職場を変えずに給料を上げる方法の一つとして、副業もあります。コンビニのバイトなども選択肢に入りますが、在宅でできる副業もあります。在宅でできる副業としては、ライターや動画編集などがおすすめです。
ただし、職場によっては副業が禁止されている可能性もあるため、実施する前に確認してください。
私自身、介護職だけでなく、副業をして市場から収入を得ることも検討しています。自分で事業を持つことで、収入は青天井になるからです。
安定している介護の仕事をしながら副業にチャレンジをして年収を上げていきたいと考えています。処遇改善加算や資格手当など、政府に求めることも重要ですが、自身でも給与を上げる方法を考えていくことも大切だと思います。

介護単発バイトを始めてみる
転職のハードルが高いと感じる人も多いでしょう。そんなときは、介護単発バイト「カイテク」を試してみてはいかがでしょうか
カイテクは面接なし・給与即金の介護単発バイトアプリです。
現在、100,000人以上の介護福祉士など介護の有資格者が登録
- 面倒な手続き不要:面接・履歴書無し!
- 給与は最短当日にGET:アプリで申請・口座に振込!
- 転職にも利用できる:実際に働いて相性を確認!
- 専門職としてスキルアップ:様々なサービス種類を経験!
副業だけでなく、転職に悩んだ場合に試しにバイトで働くという利用方法も可能です。自分に合った使い方で、効率よく稼ぐことができます。

\ インストールから登録まで5分! /
処遇改善加算があっても給料に納得がいかない場合は、給料アップ方法を試してみよう!
職場の給料に納得がいかないという方もいるかもしれませんが、必ずしも職場がピンハネなどの不正を行っているとは限りません。
疑念がある場合には、職場や専門家に確認してみるようにしましょう。しかし、ほとんどの場合、ピンハネのような不正は行われていません。
それでも給料が低いと感じた場合には、この記事を参考に、自分に合った方法で月収を上げることを目指してください。







