ジャンル別記事
看護問題一覧の書き方|リスト作成の5つのポイントも徹底解説【記入例あり】
看護問題や看護計画立案について、苦手意識があることでうまく書けない経験をしたことがあるのではないでしょうか。
看護師の仕事をするうえで、病院でも在宅においてどの分野でも看護計画は必須です。看護問題が明確になっていないと、患者さんに必要な看護を実践することはできません。
これまで看護問題や看護計画立案が苦手だった看護師、また看護学生さんはぜひこの記事を参考にしてみてくだい。
また、看護職としてキャリアアップを目指したり、学んだ知識を活かしたい方は、「カイテク」で実務経験を積むのがおすすめです。履歴書・面接不要で働ける単発バイトが豊富にあり、無料で使えるので、ぜひ以下からお試しください。
看護問題の一覧・リスト化は適切なケア計画の立案と実行に不可欠

看護問題の基本について理解することは、看護職にとって不可欠です。看護問題の基本を把握し、それに対する適切な対策を講じることで、質の高い看護ケアを提供することが可能になります。
看護問題とは
看護問題とは、患者のケアに関連するさまざまな課題やトラブルのことを指します。日常の業務の中で直面する問題だけでなく、職場環境に起因する問題も含まれます。
このような問題は、患者の安全やケアの質に影響を及ぼすことがあります。看護問題の理解とそれに対する適切な対策を考え、実行することは、看護職として重要なスキルの1つです。
問題解決能力やチームでの連携が問われるため、日々の実務経験を通じてこれらのスキルを磨くことが求められます。

看護問題一覧・リストとは
看護問題一覧とは、患者の状態に応じて想定される看護上の問題を整理・分類し、優先順位を付けて対応方針を明確まとめたリストです。
看護師はこのリストをもとに、アセスメントから看護計画の立案・実施・評価までを体系的に進めることができます。
また、複数の問題を同時に抱える患者に対しても、重要度の高い課題から順序立てて介入できます。チーム内での情報共有がスムーズになり、業務の引き継ぎや多職種連携の場面でも有効です。
問題について理解し、対策を講じることが、質の高い看護ケアを提供するためには重要です。

看護問題を把握する重要性
看護問題を正確に把握することは、適切な看護計画を立案し、効果的なケアを提供するための第一歩です。
【看護計画の3つの要素】
- 観察計画(O-P)
- 援助計画(T-P)
- 教育計画(E-P)
問題が不明確なまま計画を進めると、ケアの方向性がずれたり、患者の状態改善につながらなかったりする可能性があります。
また、医師や多職種との情報共有においても、看護問題が整理されていると連携がスムーズになり、チーム医療の質向上にも寄与します。
さらに、看護記録や評価の場面で問題の経過を追跡しやすくなり、再入院防止や生活自立支援といった長期的な成果にもつながるでしょう。
看護問題一覧・リストの書き方
看護問題リストは以下5ステップで作成できます。
看護問題の提起をする
看護問題一覧を作成する第一歩は、患者の状態や生活背景から看護上の課題を明確にすることです。観察や面談、検査データなど多角的な情報をもとに「何が患者にとっての問題か」を提起します。
ここで重要なのは、主観的な訴えと客観的なデータをバランスよく捉えることです。また、看護問題を適切に捉えることや、看護診断の根拠を明確にし、個別性のあるケアを展開するうえで、以下の枠組みが役立ちます。
NANDA-I看護診断
NANDA-I看護診断は、国際的に標準化された看護診断分類です。看護問題(看護診断)を考える際には、NANDA-I看護診断がよく使われます。
NANDA-Iでは、以下13の診断名に分類されています。
- ヘルスプロモーション
- 栄養
- 排泄と交換
- 活動・休息
- 知覚・認知
- 自己知覚
- 役割関係
- セクシュアリティ
- コーピング・ストレス耐性
- 生活原理
- 安全・防御
- 安楽
- 成長・発達
「NANDA-Iの診断タイプ」
①実在型看護診断(問題焦点型看護診断)
実在型看護診断は、患者さんがすでに抱えている症状や兆候です。症状・兆候と関連因子の2つの指標で考えていきます。具体的には、目に見えるような「食欲がない」「体温が高い」などが該当します。
②リスク型看護診断
リスク型看護診断は危険因子のことです。患者さんの健康状態や家族との関係性などによって、今後起こるリスクを記載します。
たとえば、「褥瘡(じょくそう)ができやすい」「転びやすい」など、今は問題なくとも、今後問題を引き起こす要因となりそうな状態が該当します。
③ヘルスプロモーション型看護診断
ヘルスプロモーション型看護診断は、今の状態から回復していくことでより良い状態につながることを表す診断方法です。症状・徴候で認められている診断名や病名から考えていきます。
看護診断は、患者さんの現在の問題点を考えることが多いです。しかし、ヘルスプロモーション型の看護診断は、完治や寛解したときについて記載するのが特徴です。
ヘンダーソンの基本的欲求
ヘンダーソンの基本的欲求は、以下14の欲求をもとにしたアセスメントに役立ちます。
| パターン | 例 |
|---|---|
| 正常に呼吸する | 呼吸のリズムや深さ/呼吸の数 |
| 適切に飲食する | 食事回数や時間、内容/食事環境 |
| あらゆる排泄経路から排泄する | 回数/量/臭い |
| 身体の位置を動かし、またよい姿勢を保持する | 活動パターン/運動習慣 |
| 睡眠と休息を取る | 1日の休息・睡眠時間/兆候 |
| 適切な衣類を選び、着脱する | ADL/衣類の好み |
| 衣類の調節と環境の調整により、体温を生理的範囲内に維持する | 発熱/室内の温度 |
| 身体を清潔に保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する | 保清行動/爪・皮膚・毛髪の状態 |
| 環境のさまざまな危険因子を避け、また他人を侵害しないようにする | 認知機能/感覚 |
| 自分の感情、欲求、恐怖あるいは“気分”を表現して他者とコミュニケーションをもつ | 性格/視覚/聴覚 |
| 自分の信仰にしたがって礼拝する | 信仰宗教/価値観 |
| 達成感をもたらすような仕事をする | 社会的役割/ボランティア活動 |
| 遊び、あるいはさまざまな種類のレクリエーションに参加する | 趣味/過ごし方 |
| 正常”な発達および健康を導くような学習をし、発見をし、あるいは好奇心を満足させる | 年齢 |
ゴードンの機能的健康パターン
ゴードンの11の機能的健康パターンは、患者の健康状態を生活全体から評価する視点です。
- 健康知覚-健康管理パターン
- 栄養-代謝パターン
- 排泄パターン
- 活動-運動パターン
- 睡眠-休息パターン
- 認知-知覚パターン
- 自己認識-自己概念パターン
- 役割-関係パターン
- 性-生殖パターン
- ストレス-コーピングパターン
- 価値-信念パターン
栄養・代謝、活動・運動、睡眠・休息などに分かれ、包括的なアセスメントができます。特に在宅看護や地域看護で活用されており、個別性のある看護計画を立てるのに有効です。
PES方式
PES方式は、看護問題を「問題(P)」「原因(E)」「徴候・症状(S)」の3要素に分けて記述する方法です。
たとえば「活動 intolerance に関連した呼吸困難の訴え」といった形で、問題と根拠を明示できます。シンプルながら根拠を明確に伝えやすく、実習や臨床でも広く使われている方法です。
看護問題を細分化して判断する
看護問題(看護診断)は以下のように細分化して判断します。
- 疾患に伴う苦痛
- 投薬や治療に伴う苦痛
- 合併症に伴う苦痛
- 体動制限に伴う苦痛
- 精神的不安に伴う苦痛
- セルフケア不足(清潔維持や服薬管理が困難など)
たとえば「栄養不足」という課題も、「摂取量不足」「消化機能低下」「嚥下障害」などに分けると、より的確な介入が可能になります。
また、患者さんの身体だけでなく、投薬や治療による痛みも含まれます。さまざまな視点から患者さんの痛みを分類し、看護問題を適切に作成しましょう。
看護問題の原因を特定する
看護問題には必ず原因や関連因子があります。原因を特定するためには、以下のような複数の視点から分析します。
- 身体的要因(疾患・障害)
- 心理的要因(不安・抑うつ)
- 社会的・環境的要因(住宅環境や介護体制)
原因が曖昧なままでは、対策が表面的になり、根本的な解決につながりません。原因を明確にできれば、より効果的で持続性のあるケア計画が立案でき、再発防止にもつながります。
看護問題の優先順位を付ける
看護問題には優先順位を付けることが重要です。すべての問題に同時に対応することは難しいため、患者の生命や健康への影響が大きいものから順に対応する必要があります。
優先順位の具体的な基準は以下です。
- 生命の危険度が高いか
- 早期対応が求められるか
- 患者の生活の質に影響するか
命にかかわる看護問題(看護診断)を最優先にしましょう。看護問題は既往歴や身体的機能、薬剤の使用状況から判断していきます。
急性期患者を例にして、優先順位を付けると以下のとおりです。
看護問題:術後の強い疼痛、血圧の上昇
優先順位:
- 疼痛管理(鎮痛薬投与、リラックス誘導)
- 血圧管理(降圧剤投与、モニタリング強化)
- 創部感染管理(清潔保持、感染兆候の観察)
ケアを通じてリストの見直しをする
看護問題のリストは一度作成したら終わりではなく、定期的な見直しが必要です。ケアを実施する中で患者の状態は変化するため、改善した問題は削除し、新たに生じた問題を追加します。
評価のタイミングは、計画の見直し日やカンファレンス時、症状変化があった直後などが適しています。常に最新の状態に更新することで、ケアの質を維持し、患者のニーズに即した支援継続が可能です。
看護問題の書き方や定義を実践を通して学びたい方は、カイテクで単発バイトをしてみましょう。以下、カイテク利用者へのインタビュー内容も参考、カイテクの登録をぜひ検討してみてください。
Q:Tさんがつらい経験から立ち直られた姿を見て、とても嬉しく思います。Tさんはどのような方にカイテクをオススメしたいですか?
A:カイテクは時短や半日など本当にいろいろな働き方ができるので、ブランクのある人にも、子育て中の方、隙間時間に少しだけ働きたい方などには、とても便利なサービスです。
まずは事故なく1日を無事に終えられるように。そこからスタートしていけば、いつかきっと自信がついて、楽しく働くことができる日が来ると思います。
それに私はカイテクを活用して、これからチャレンジしたいこともできました。障害のある小児施設に、いつか行ってみたいと思っているんですが、まだ勇気がなくて。
いずれチャレンジして経験値をさらに増やしたいです。そういう意味でもカイテクは対価をもらいながら勉強もできるので、意欲がある方にとっては最適なサービスですよね。
パワハラで落ちていた私でも、カイテクで働くことですごく自信がつきました。
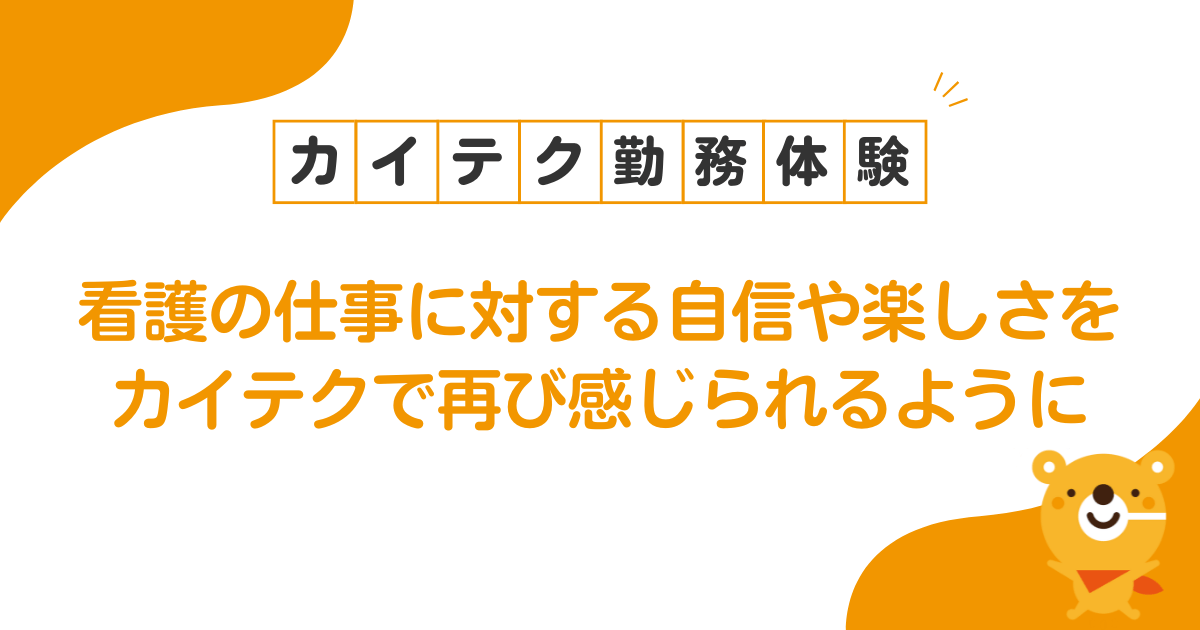

\ インストールから登録まで5分! /
看護問題一覧・リストを書く際の5つのポイント
看護問題リストを作成する際は、以下5つのポイントを意識しましょう。これらを理解しているか否かで、看護問題リストや看護計画の作成はもちろん、患者へのケアの質も向上します。
患者ごとの状況に合わせて問題を特定する
看護問題は、患者一人ひとりの年齢、疾患、生活背景、価値観に基づいて特定することが重要です。同じ疾患名でも、症状の進行度や生活環境によって必要な支援は異なります。
たとえば、高齢者の転倒リスク一つをとっても、「筋力低下によるふらつき」と「薬の副作用によるめまい」では介入方法が異なります。
画一的なリストをそのまま当てはめるのではなく、観察やヒアリングから得られた情報をもとに、患者固有の課題を抽出しましょう。この個別化がケアの質を高めます。
重要な問題に絞って記載する
すべての問題を網羅的に挙げると、優先度が分かりにくくなり、ケアの焦点がぼやけます。そのため、特に患者の健康や生活の質に大きく影響する重要な問題に絞って記載することが大切です。
重要度を判断する基準としては、生命への危険度、症状の急性度、苦痛の強さなどが挙げられます。また、あえて記載を減らすことで、限られた時間や人員の中でも効率的にケアを実施でき、成果の評価もしやすくなります。
主観的情報と客観的情報を組み合わせて分析する
看護問題を正確に特定するためには、主観的情報と客観的情報を組み合わせて分析することが不可欠です。
- 主観的情報:患者や患者家族からの訴え
- 客観的情報:医療従事者の判断内容(バイタルサインや診療内容、検査データ)
主観的情報だけでは感情や印象に偏る危険があり、客観的情報だけでは患者の生活背景や心理的側面を見落とします。両者を統合することで、問題の全体像を把握でき、より実効性の高いケア計画につながります。
チーム全員が共有・理解できる内容にする
看護問題のリストは、看護師だけでなく医師、リハビリスタッフ、介護士など多職種で共有されます。そのため、専門用語の多用や曖昧な表現は避け、誰が読んでも同じ解釈ができる内容にまとめることが重要です。
たとえば「ADL低下」だけでなく、「食事は自力で可能だが、入浴は全介助」と具体的に記載すると、介入方針が明確になります。
情報の可視化と共通理解は、チームアプローチの効果を最大化します。
完璧を目指しすぎず柔軟に見直しする
看護問題リストは一度作成して終わりではなく、患者の状態変化や治療経過に応じて随時見直す必要があります。完璧さを追求しすぎると、更新や修正が遅れ、現状と乖離した内容になりかねません。
むしろ「現時点での最善案」として作成し、必要に応じて柔軟に修正する方が、実践的で有効なツールとなります。状態改善による問題の解消や、新たな合併症の発生などにも迅速に対応できる体制を整えておくことが大切です。
看護問題一覧・リストの記入例
実際の看護現場では、患者の状態に応じて適切な看護問題リストを作成し、それに基づいた看護計画を実施することが重要です。ここでは、以下4つのケースに分けて具体的な記入例を紹介します。
記入例①:急性期患者の看護問題リスト
看護問題
- 創部痛による活動制限
- 術後の感染リスク
- 体動困難による血栓形成のリスク
患者目標
- 術後の疼痛スケール(NRS)で5以下を維持する
- 創部の感染徴候を認めない
- 1日3回のリハビリ運動を実施し、DVT(深部静脈血栓症)を予防する
看護計画
- 鎮痛薬(NSAIDs)の適切な投与と疼痛評価の実施
- 創部の清潔保持と毎日の感染徴候のモニタリング
- 早期離床を促進し、足の運動や弾性ストッキングの着用を指導
- 水分摂取を促し、血流を良好に保つ
記入例②:慢性期患者の看護問題リスト
看護問題
- 血糖コントロール不良(HbA1c 8.5%)
- 糖尿病性末梢神経障害による足のしびれ
- 食事管理の不徹底
患者目標
- HbA1cを7.0%以下に改善する
- 糖尿病性末梢神経障害の症状を軽減し、日常生活に支障が出ないようにする
- 栄養バランスを考えた食事を毎日3食摂取できるようにする
看護計画
- 医師と連携し、インスリンや経口血糖降下薬の適切な調整を行う
- フットケアを実施し、足の傷や潰瘍が発生しないよう管理
- 栄養指導を行い、糖質摂取量の調整をサポート
- 患者自身が血糖測定を定期的に実施し、自己管理できるよう指導
記入例③:在宅看護の看護問題リスト
看護問題
- ADL(活動能力)の低下による生活動作の困難
- 誤嚥性肺炎のリスクが高い
- 介護者(家族)の負担増加
患者目標
- リハビリを継続し、歩行器を用いた歩行ができるようにする
- 誤嚥を防ぎ、安全に経口摂取できるようにする
- 介護者の負担を軽減し、適切な介護環境を整える
看護計画
- 理学療法士と連携し、日常生活動作訓練を実施
- 食事形態をトロミ食に変更し、誤嚥予防のための姿勢指導を行う
- 家族への介護指導を実施し、レスパイトケアの利用を提案
記入例④:精神科患者の看護問題リスト
看護問題
- 気分の落ち込みと無気力状態が続く
- 服薬管理が自己判断で中断される
- 社会復帰に対する不安が強い
患者目標
- 日常生活の中で少しずつ活動量を増やせるようになる
- 決められた服薬スケジュールを守り、治療を継続する
- 社会復帰に向けた計画を立て、小さな目標をクリアしていく
看護計画
- 認知行動療法(CBT)を活用し、気分のコントロールをサポート
- 服薬カレンダーや服薬アラームを活用し、服薬遵守を促す
- 就労支援センターと連携し、段階的な社会復帰プランを立案
【分野別】一般的な看護問題
看護問題は、患者の状態や医療環境に応じて多岐にわたりますが、主に日常業務の中で頻繁に遭遇する課題が含まれます。ここでは、各分野で発生しやすい看護問題を整理し、対応策についても詳しく解説します。
高齢者の看護問題
高齢者は加齢による身体機能の低下や慢性疾患の影響を受けやすいため、以下のような問題が発生します。
- 転倒・骨折のリスク
- 嚥下障害・誤嚥リスク
- 認知症・記憶障害
- 排泄障害・便秘
高齢者の転倒を防ぐためには、環境整備が重要です。手すりの設置や、滑りにくい床材を使用することで、転倒事故のリスクを軽減できます。
また、誤嚥を予防するためには、とろみをつけた食事や適切な嚥下訓練が効果的です。認知症の患者に対しては、見守り体制の強化や、家族と連携したケアが求められます。
排泄障害については、水分摂取の管理や骨盤底筋トレーニングを指導することで、QOLの向上につながります。
小児の看護問題
小児看護では、成長・発達に伴う健康管理や親子支援が求められます。
- 感染症の管理
- 成長・発達の遅れ
- 食事や栄養管理
- 親のストレスケア
感染症予防のためには、手洗い・うがいの徹底、適切なワクチン接種が重要です。成長・発達に問題が見られる場合は、早期介入が効果的であり、必要に応じて専門機関と連携して支援を行います。
食物アレルギーを持つ小児には、食事内容を工夫し、適切な栄養摂取ができるよう支援することが大切です。また、長期入院する小児の家族には、カウンセリングや情報提供を行い、精神的な負担を軽減するサポートをします。
精神科の看護問題
精神科では、患者の心理的・社会的要因を考慮しながらケアを行う必要があります。
- 自傷・他害のリスク
- 服薬管理の徹底
- 対人関係の問題
- ストレスケア
自傷・他害のリスクを軽減するためには、安全管理を徹底し、定期的なモニタリングを実施することが不可欠です。また、服薬管理については、患者に薬の必要性を理解してもらうと同時に、家族と協力して服薬のチェックを行うことが有効です。
ストレスマネジメントには、認知行動療法やグループセラピーを活用し、患者が自身の感情をコントロールできるよう支援することが求められます。
栄養に関する看護問題
栄養不足や過剰摂取が、患者の健康状態に大きく影響を与えます。
- 低栄養のリスク
- 肥満と生活習慣病
- 摂食障害
栄養管理の基本は、適切な食事計画を立てることです。食欲が低下している患者には、少量でも高カロリーの食品を摂取できるようにする工夫が求められます。
嚥下障害のある患者には、とろみをつけた食事や誤嚥防止のための姿勢調整を行うことが有効です。栄養補助食品の活用も、エネルギー摂取を補う手段として検討すべきです。
外科・術後管理に関する看護問題
外科手術を受けた患者は、術後の回復過程で特有の看護問題を抱えることが多く、適切なケアが求められます。
- 術後疼痛管理
- 創傷治癒の遅延
- 感染リスクの増加
- 血栓塞栓症のリスク
術後の創傷ケアでは、感染予防が最優先となります。清潔なドレッシングの交換や、感染兆候の早期発見が重要です。疼痛管理については、鎮痛薬の適切な投与と、患者の痛みレベルの定期的な評価を行います。
また、離床を促進することで、血栓予防や筋力低下の防止につながります。患者の状態に応じたリハビリ計画を立て、無理のない範囲で運動を進めることが求められます。
在宅看護の看護問題
在宅での療養生活を送る患者には、入院中とは異なる看護問題が発生するため、医療者と家族の連携が欠かせません。
- 家族の介護負担の増大
- 医療機器の管理が困難
- 服薬管理の問題
在宅看護では、訪問看護や訪問介護の活用が欠かせません。家族への介護指導を行い、適切なケアができるようサポートすることが必要です。
また、家族の負担を軽減するために、レスパイトケア(介護者の休息支援)を提供することも効果的です。急変時の対応については、緊急連絡先を明確にし、必要な手順を家族と共有しておくことが重要です。
看護問題を正しく把握して一覧・リストを作成しよう
看護問題や看護計画立案は難しいと感じてしまっていた人も、看護問題や問題を細分化すること、看護計画の書き方についてご理解いただけたと思います。
看護計画は標準的なものがありますが、それに沿って担当している患者さん自身に必要なことを具体的に記述することで、実際の看護ケアに活かしていくことができます。また、患者さんの状態によっては追加も必要になってきます。
これを機会に看護問題一覧を理解して、患者さんに沿った看護計画が書けるようになりましょう。
カイテクは、「近所で気軽に働ける!」看護単発バイトアプリです。
- 「約5分」で給与GET!
- 面接・履歴書等の面倒な手続き不要!
- 働きながらポイントがザクザク溜まる!
27万人以上の看護師などの有資格者が登録しております!

\ インストールから登録まで5分! /







